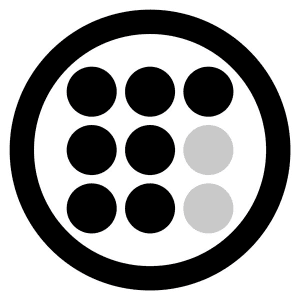日本ハムの高卒6年目・田宮裕涼が「打てる捕手」として台頭
開幕から熾烈なAクラス争いを演じている日本ハム。チームが順調なスタートを切ることができた要因として、田宮裕涼捕手の飛躍は外せないだろう。6年目となる今季は、すでに前年までの通算出場試合数を上回る57試合に出場。捕手として4割近い盗塁阻止率をマークする強肩を誇りながら、リーグ2位の打率.333を記録するなど、「打てる捕手」としてチームを攻守でけん引している。(数字は全て6月23日終了時点)
まず注目したいのが、打球性質別の成績だ。フライ打球は割合こそ35.6%と決して高くはないものの、打率.373と好結果をもたらしている。フライ打球の打率は守備の影響を受けないホームランを量産する選手ほど上がりやすい傾向があるなか、田宮が放った本塁打はここまで2本。いかに質の高い打球をヒットゾーンに飛ばしているかがわかるだろう。
さらに、ゴロやフライと比べてヒットになりやすいライナー打球の割合は、リーグ平均が例年10%程度に収まっている中、田宮は21.5%とパ・リーグの規定打席到達者で最も高い数値をマーク。適度な打球角度をつけられる高度な技術を有し、ライナーで打球性質別最多の26安打、打率.813と好成績を残していた。
角度をつけた打球で高打率を残すが、カウントによっては長打への比重を高めているようだ。カウント別の打球性質割合を見てみると、0・1ストライク時のフライ割合は2ストライク時よりも約14%高い数字をマーク。フライはライナーよりもヒットとなる確率こそ低いものの、長打になる可能性が高い。追い込まれるまではフライを打つことで長打を狙いつつ、2ストライクになると角度を下げて確率を高めようとする意図があるかもしれない。そのアプローチは結果にも反映されており、ここまで放った長打15本のうち11本は追い込まれるまでに記録。2本の本塁打はどちらも初球を捉えたものとなっている。
追い込まれても異次元の高打率…対応力はリーグ屈指
追い込まれる前後でのスタイルの変化は打球方向にも表れている。引っ張り方向への打球が追い込まれるまでは42.5%を占めるのに対し、2ストライクになると28.9%まで低下。一般に長打は引っ張り方向の割合が高くなりやすく、今季の田宮も長打の半分がライト方向への打球だ。追い込まれるまでは角度だけでなく、打球を放つ方向からも長打を狙っていることがうかがえる。カウントによってアプローチが変わること自体は珍しいことではないが、その変化がより顕著に出ていた。
追い込まれるまでは打球に角度をつけ、より引っ張ることを意識している田宮。その成果を純粋な長打力を示すISOを用いて見てみると、0・1ストライク時はISO.216をマーク。これはパ・リーグの規定打席到達者で7位の数字であり、同条件のリーグ平均がISO.140なことを踏まえると、追い込まれる前は高打率を残しながら確かに長打を放っていることがわかる。
一転して広角にゴロ、ライナー打球の割合が増える2ストライク時は、ISOはリーグ17位まで低下。しかし打率は同条件でリーグトップの.321とハイアベレージを記録。三振も成績に影響する2ストライク打率は、0・1ストライク時に比べて大きく低下する傾向にあるが、今季の田宮は追い込まれる前と遜色ない異次元の高打率をマークしている。追い込まれてからの対応力はリーグトップといっても過言ではないだろう。
カウントによって剛柔を使い分けることで、チームに欠かせない打者となった24歳。シーズン中盤を迎えてもその勢いは止まるどころか増す一方だ。抜群のバッティングセンスが光る背番号64からは今後も目が離せそうにない。(「パ・リーグ インサイト」データスタジアム編集部)
(記事提供:パ・リーグ インサイト)