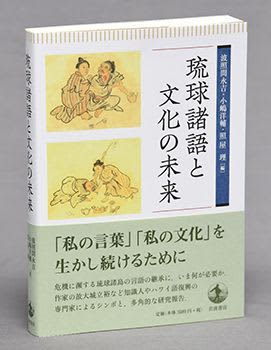
日本学士院会員の大阪大学・金水敏教授(日本語学)の研究にかつて加わった際、今は亡き母の、「石垣方言」を録音したことがある。文学が専門で言語学者ではない私に、金水先生はこう諭した。「言語を発音記号に落とせる研究者は世の中にいくらでもいる。貴重なのは『話者』。録音をしっかりとってほしい」。
父も母も他界した今、耳に残る二人の、平得と真栄里の言葉による会話のリズムが、その助言とともに頭の中をめぐる。
言葉は人と共にある。だから人が亡くなると、言葉も失われる。しまくとぅば(琉球諸語)も、継承がなされないまま、母語話者たちがこの世を去れば、消滅する。そうはさせじと考える、研究者や作家らによる名桜大学主催のシンポジウムをもとに、論考を集めたのが本書だ。
多岐にわたる分析や提言は、示唆に富む。発音の表記、正書法を確立する必要性が唱えられる。言葉の消滅による、文化への影響の懸念も示される。那覇や首里の言葉に収斂(しゅうれん)されない、多様なしまくとぅばゆえの課題も指摘される。言語と格闘してきた近現代の沖縄の作家や詩人たちの表現方法、あるいは台湾との比較やハワイ語復興の取り組みなどの報告もある。
琉球諸語を書き言葉として残す道は、恐らく現実的な継承方法のひとつだろう。英国マン島は、最後の母語話者が没した後、第2言語として学んだ話者が現れた事例だと聞く。一方で言語滅びて言語研究盛ん、という状況を想像してみる。それはやはり悲しい。人と共にあるからこそ言葉は生きて貴(たっと)いのだ。
本書には、シンポに登壇した故・大城立裕氏の、「丁寧語」創造の重要性を説いた報告が収められている。文字で書き起こされた大城氏の言葉遣い(話し方)から、私は在りし日の沖縄文学を牽引(けんいん)した作家の人となりを思い浮かべた。
沖縄の内側から言葉を創造し続けることが、滅びゆく琉球諸語を救う道だと複数の論者は強調する。時間はない。が、まだあきらめてはいけない。希望はある。言葉が人と共にある限り。
(本浜秀彦・文教大学教授)
はてるま・えいきち 1950年生まれ、名桜大学大学院国際文化研究科教授、沖縄県しまくとぅば普及センター長、琉球文学、文化学。
こじま・ようすけ 1976年生まれ、名桜大学国際学群教授、日本近現代文学。
てるや・まこと 1975年生まれ、名桜大学国際学群上級准教授、琉球文学。
