
「燕三条 工場の祭典」実行委員会の武田修美副実行委員長(写真左)と、山田立実行委員長(写真右)
「燕三条 工場の祭典」実行委員会は21日、11月5日から21日に新潟県三条市の廃工場で開催する「Tsubame-Sanjo Factory Museum」のコンセプトや展示内容について公表した。「工場の祭典」では例年、燕三条地域のものづくりの現場を開放してきたが、今回は新型コロナウイルス感染症対策のため、展示会形式での開催。山田立実行委員長は「燕三条地域のものづくりの歴史を体系的に表す内容となった」と自信を見せる。
金属加工業の一大集積地である新潟県燕三条地域のものづくりの現場を見学・体験できるイベント「燕三条 工場の祭典」は2013年から始まり、今年で9回目。そのオープンファクトリーが大きく注目されてきた取り組みだが、会期外には東京をはじめ、イタリアのミラノや、イギリスのロンドン、シンガポール、台湾・台北など、アジアやヨーロッパの各都市で燕三条のものづくりの魅力を伝える展覧会も実施してきた。今回は、その展示会が「地元へ凱旋するような」形であると山田実行委員長は話す。

「Tsubame-Sanjo Factory Museum」メインビジュアルは、熟練の職人と燕三条へ移住してきた若手に支えられたストライブが象徴的
「Tsubame-Sanjo Factory Museum」の会場となるのは、移転により廃工場となった旧・野水機械製作所。かつては同地域でも使用された研磨機を製造していた、2,000平方メートル超、天井高6メートルの大空間を活用した展示を行う。
展示会では燕三条で作られている約50種のアイテムに関する製造プロセス、製品の多様性、今と昔の比較を解説。また、江戸時代の和釘を起点とした同地域のものづくりの変遷を記した「工場の系統樹」や、実際に製品がつくられるまでの様子を写すスクリーンなども用意。実際の工場の見学はできないものの、見学よりも職人に近接できる映像コンテンツなどの趣向を凝らすことで新たな「工場の祭典」の形を創出する。
武田修美副実行委員長は「今まで世界中で展覧会をしてきたが、それらと異なるのは、実際の工場の『匂い』を感じられるところ。燕三条のものづくりを支えてきた工場の中で、職人たちとの繋がりや背景を感じることは、(ほかの展示会では)なかなかできない」と見所について話した。

「燕三条 工場の祭典」実行委員会の山田立実行委員長
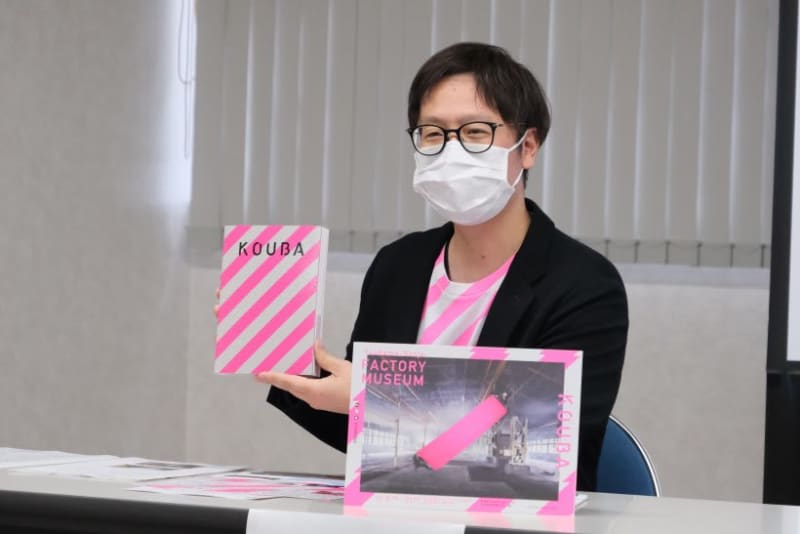
武田修美副実行委員長
また今回は、地域の小中学校からの来場が予定されていることから、事前に燕市と三条市の小中学校へ『工場の祭典 オフィシャルブック」(2019年発行)を計100冊寄贈した。
さらに、開催当日には地元の三条市立大学、新潟経営大学、長岡造形大学などの学生がガイドや設営として参加。それぞれがものづくりの現場を見て感じたことや、関わったきっかけなども交えた案内が考えられており、こうした次世代による紹介と継承もポイントの一つになると言えるだろう。
【関連リンク(会期や予約状況の詳細が記載)】
燕三条 工場の祭典 公式webサイト
【関連記事】
「燕三条 工場の祭典」実行委員会と株式会社いせん(新潟県湯沢町)が「観光庁長官表彰」受賞(2021年10月14日)
(文・鈴木琢真)

