
新潟県園芸振興大会の様子
新潟県と県農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会新潟県本部は10日、園芸生産の拡大や農業者の所得向上を図るための情報共有を行う新潟県園芸振興大会を開催した。
同大会では、県農林水産部やJAグループが園芸振興に関するこれまでの取り組みや課題を紹介。挨拶に立った花角英世知事は「県の園芸振興基本戦略の策定から3年目を迎えた。県内各地で、販売量1億円を目指して取り組みが進んでいる。園芸の生産拡大に取り組む地域やJA、生産者と話しをする中で、成果が着実に出てきていることを実感する」と話す。
一方で県農林水産部農産園芸課の神部淳課長は、新規取組者のさらなる獲得のための園芸参入塾や巡回指導、栽培面積拡大のための省力化や共同化の必要性などを今後の課題に挙げた。

新潟県の花角英世知事
会の中では、先進産地における事例の紹介として、山形県農林水産部園芸農業推進課の齋藤祐太郎主幹が登壇。山形県最上地域の事例を中心に山形県の園芸産地育成の取り組みを紹介した。
山形県は朝日山地や出羽丘陵の影響から各地域で降雪量や気温に差が大きく、各地域の特性に合った品目が選定されて栽培されているという。最上地域では、冷涼で湿潤な気候を生かしてニラやアスパラガスといった葉茎菜類の生産が盛んになっている。
ニラの販売額は2007年までに一度頭打ちとなったが、その後も、運搬方法の改善による夏期の荷痛みの低減や、農薬飛沫防止のための目印を圃場に立てるなど、ブランド価値の向上に取り組んだ。また、秋期の生産拡大や1戸あたりの栽培面積の増加により、2015年・2016年には10億円産地に成長した。
ネギやアスパラガスの産地拡大についても、気候条件に合致した品目の選定や、集出荷施設を核とした産地の拡大、生産者増加に対応した栽培技術の指導・病害対策のマニュアル化などの要点を紹介した。

山形県農林水産部園芸農業推進課の齋藤祐太郎主幹
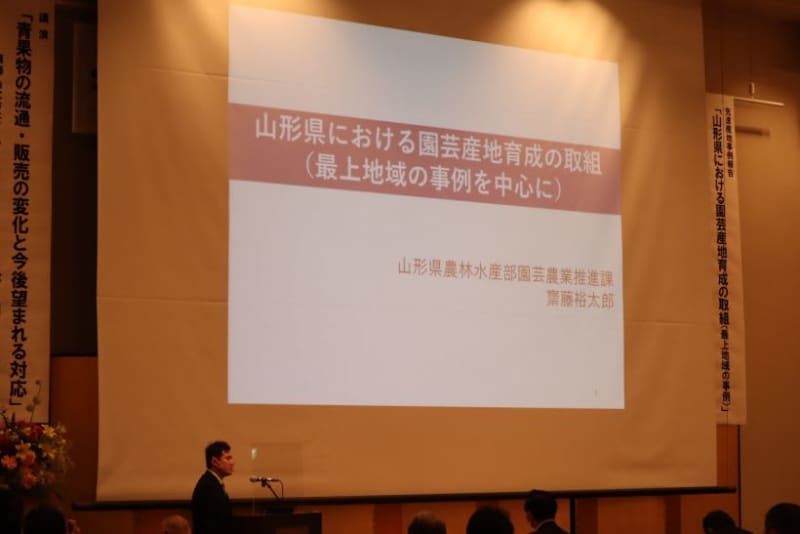
齋藤主幹による山形県の事例紹介
