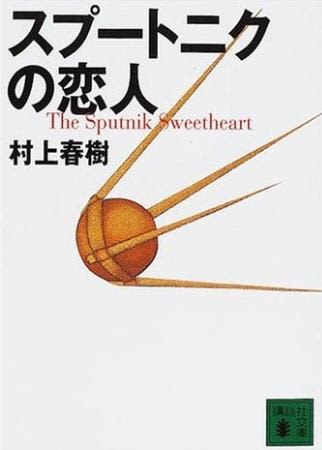
村上春樹作品には動物がよく出てきます。鼠、猫、犬、羊、象、カンガルー、猿…。そしてカラスも必ずと言ってもいいほど登場します。村上春樹のファンなら、これらの動物が出てくる、いくつか作品を挙げることができるかと思います。
蛇やトカゲなど爬虫類はあまり出てきていないと思いますが、でも両生類のカエルは出てきますし、ミミズなども出てきます。それも作中にチラリと出てくるわけではありません。その小説の中心に登場するのです。
例えば、カエルなら、『神の子どもたちはみな踊る』(2000年)の中の短編「かえるくん、東京を救う」を思う人は多いでしょうし、その作品には腹を立てると地震を起こす「みみずくん」も登場します。
このカエルやミミズも、急に出てきたわけではありません。デビュー作『風の歌を聴け』(1979年)の中で「鼠」が女の子と2人で奈良をデートしたことを語る場面がありますが、そこで「蝉や蛙や蜘蛛や、そして夏草や風のために何か書けたらどんなに素敵だろうね」と「鼠」は述べています。またそのデビュー作の最後には「この我々の世界などミミズの脳味噌のようなものだ」とのハートフィールドという作家の言葉を引用して、「そうであってほしい、と僕も願っている」という言葉が記されています。
動物専門の作家ではないのに、こんなに動物が好きな小説家はいないですね。
「鼠」に関してはデビュー作『風の歌を聴け』(1979年)から、第2作『1973年のピンボール』(1980年)、第3作『羊をめぐる冒険』(1982年)のいわゆる初期3部作に登場して、メーンキャラクターでもありましたし、そのイメージが強く読者に残っているためか、『羊をめぐる冒険』で「鼠」という人物が亡くなって以降、作品にほとんど出てきていないと思います。
さらに「羊」も『羊をめぐる冒険』に出てきましたが、同作中で村上春樹自身が描いたユーモラスなイラストつきで登場した「羊男」のインパクトが強くあるためか、あまり出てきませんね。羊男が出てくるのは『羊をめぐる冒険』以降では、村上春樹が文、佐々木マキが絵を担当した絵本『羊男のクリスマス』(1985年)などはありますが、長編小説では『ダンス・ダンス・ダンス』(1988年)に登場するぐらいかと思います。
それ以外で、一番多く登場するのは、最初に列挙した中では、やはり「猫」と「カラス」ではないかと思います。日常生活でよく出合う動物ですし、「犬」も日常の動物ですが、やはり「猫」か「犬」で言えば、村上春樹は「猫」派でしょう。ただし『風の歌を聴け』には「犬の漫才師」というDJが出てきますが…。
でも何しろ、学生時代に開いたジャズ喫茶の名前が「ピーター・キャット」という名前なのですから。その「ピーター」という名前はもしかしたら、イギリスの詩人T・S・エリオットの詩集『キャッツ ポッサムおじさんの猫とつき合う法』(1939年)の詩句から命名されているのではないかという妄想から、ここ何回か、村上春樹作品の中に登場する「猫」について考えてきました。例えば、なぜ作中の「猫」に魚系の名前が付けられているのかなどについての考察(妄想?)です。
今回のコラムはT・S・エリオットと村上春樹作品の関係を考える番外編という感じですが、これまでの延長線上で村上春樹作品の中の「猫」についてもう少し考えてみたいと思います。今回考えてみたいのは、異界へ誘(いざな)う猫というものです。そこから「猫」が村上春樹作品の中でどういう位置を占めているのかということを考えてみたいのです。
まずは『スプートニクの恋人』(1999年)に出てくる「猫」です。
「スプートニク」というのは、1957年10月4日、ソ連が打ち上げた世界初の人工衛星の名前です。そのスプートニク1号打ち上げの翌月3日には、ライカ犬を乗せたスプートニク2号の打ち上げにもソ連は成功。そのライカ犬は宇宙空間に出た最初の動物となりましたが、衛星は回収されず、宇宙における生物研究の犠牲となったことが『スプートニクの恋人』の本の扉に記されています。
このため、犠牲となった「犬」のことが目立つ物語となっています。例えば、古代中国では城壁の大きな門が出来上がると、古戦場から集められた人骨が門に塗り込まれました。さらに生きている「犬」の喉を短剣で切って、温かい血が門にかけられたのです。ひからびた骨と新しい血が混ざり合い、はじめて古い魂は呪術的な力を身につけることになったのです。
そんな話も記されているので、「犬」の印象が強い作品ですが、でも結構「猫」のほうもたくさん出てくる小説なのです。
それは、こんな具合です。同作には小学校の教諭をしている語り手の「ぼく」が好きな「すみれ」という女性が登場しますが、その「すみれ」がギリシャの小島で、突然煙みたいに行方不明となってしまうのです。
「すみれ」はミュウという女性の秘書のようなことをやっていて、「ぼく」もミュウからの国際電話で呼び出されてギリシャの島に向かいます。
ミュウの話によると、4日前の夜、突然、煙のようにすみれは消えてしまったのです。
「すみれ」とミュウはこの島に来て、8日目で、その4日目の朝も2人でビーチで泳いだり、カフェで話したりしています。そして、その日の新聞記事の中から「すみれ」が記事を選んで読み上げます。それは、飼い猫に食べられてしまった70歳の女性の話でした。
その女性はある日、心臓発作で倒れ、ソファに伏せたまま息を引き取った。それから1週間の間、猫たちは飢えに耐えかねて、死んでしまった飼い主の肉をむさぼり食べたという記事です。
それを受けて今度は、厳格なカソリックの女子校に6年間も通ったミュウがフランス人のシスターが語ってくれたという、猫と無人島に流れ着く話をします。
船が難破して、無人島に流れ着く。あなたと一匹の猫だけ。その島にはわき水もないので、食べ物と水がなくなったら死ぬしかない。みなさんどうしますか? と言って、シスターは「乏しい食べ物を猫にもわけてやりますか?」と聞きます。でもシスターは「いいえ、それは間違ったことなのです」「みなさんは神に選ばれた尊い存在であり、猫はそうではないからです。ですからそのパンは、あなたが一人で食べるべきなのです」と言ったそうです。そのことをミュウは語ります。
「それって、最後は猫を食べちゃってもいいということよね?」とすみれが言います。
それに続いて、すみれが「猫といえば、ひとつ奇妙な思い出があるのよ」と、ふと思い出したように言うのです。
ここからが、私の言いたい「異界へ誘(いざな)う猫」の話です。
それは、すみれが小学校2年生くらいのときの話です。すみれは、生まれて半年くらいのきれいな三毛猫を飼っていました。
その猫があまりに興奮して、すみれが縁側から見物していることにも気づかないみたいです。さらに時を追うごとに、それは真剣みが増してきて、まるで何かに取り憑かれたみたいになってきたそうです。
「猫の目にはわたしには見えないものの姿が映っていて、それが猫を異常に興奮させているんじゃないかって思えてきた」。やがて猫は木の根もとをぐるぐると走ってまわり始めて、そして松の木の幹を一気に駆け上がったそうです。
やがて日が暮れましたが、すみれは縁側に座ったまま猫が降りてくるのを待っていたのです。でも降りてこなかった。猫は結局もどってこなかったそうです。
「もどってこなかったの?」とミュウが尋ねました。すみれは「うん。猫はそのまま消えてしまったの。まるで煙みたいに」と答えます。
みんなは「猫は夜のあいだに木から降りてきて、どこかに遊びに行ってしまったんだって」と言いますが、でもすみれは「猫は枝にしがみついて、声も出せないくらい怯えているんだ」と思っています。すみれは木を見上げて、ときどき大きな声で猫の名前を呼びます。だが返事はありません。1週間ほどたって、すみれもあきらめます。
でもすみれは「松の木を見るたびに、高い枝にしがみついたまま、固くなって死んでいる可哀想な子猫のことを想像した。子猫はどこにも行けないまま、そこで飢えてひからびて死んでしまったのよ」とミュウに話します。
すみれとミュウが、港のカフェで、そういう話をした日の夜に、すみれ自身も、すみれが愛した猫と同じように「煙のように消えてしまった」のです。
実は、すみれはミュウに対して、強い恋愛感情を抱いていて、その晩、すみれがミュウに同性愛的な行為をするのですが、ミュウは心と頭ではすみれを受け入れながら、身体はすみれを拒否しているという状態でした。
そしてすみれは「煙のように消えてしまった」のです。
ここで「猫」の話が、すみれの異界への予告、誘(いざな)いになっています。
そして、すみれが消えてしまったギリシャの島は異界、死者の世界、霊魂の世界、魂の世界であることが記されていると思います。
飢えた猫たちが、飼い主の死体をむさぼり食べた話。また無人島に漂着して食べ物が少なくなっても、猫にパンを与えてはいけないというシスターの話。「それって、最後は猫を食べちゃってもいいということよね?」という、すみれの発言も、そのことを述べていると思います。
「ぼく」に会って、それらの猫の話をすみれとしたことを明かしたミュウが「そのときにただの害のない思い出話だと思っていたんだけれど、あとになってみると、そこで話されたことのすべてに意味があるような気がしてきた」と話したことを村上春樹は書いています。それは「猫」が異界への誘(いざな)いであることを、ミュウの言葉を通して語っているのだと、私には思えます。
さらにもう1つ、そのギリシャの島が異界の世界であることを示しているのは、その場面を描写する村上春樹の「4」へのこだわりです。村上春樹には数字の「4」に対する強いこだわりがありますが、この作品のギリシャの島の場面にも、そのこだわりが存分に発揮されています。
例えば、すみれが消えてしまったのは「ぼく」がギリシャの島に到着して、ミュウから話を聞く「4日前」のことです。
そしてすみれとミュウが、このギリシャの島に到着してから「今日で8日目」だそうですから、すみれはギリシャの島に到着して、「4日目」に「煙のように消えてしまった」ということになります。
僕も、それを聞いて「こんな小島で外国人が4日間も人目につかないでいるのは簡単なことではないはずだ」と思っています。
この「4」へのこだわりの指摘に疑念を抱く人もいるかもしれません。単に偶然に「4」が多く出てくるだけだろう…と。そういう方もいるかと思いますので、もう1つだけ紹介しますと、ミュウからの国際電話を受けた「ぼく」が、親しい同僚の女性教師に電話をして、急に不在となる理由として「親戚に不幸があって、一週間ほど東京を離れることになった」と言う場面があります。
「それで、どこに行くのか?」と彼女が訊くので、「四国」とぼくは答えています。つまり、これから、ぼくは「四国」(死国)、死の国に向かうと述べているのです。
もう1つ、死の国への誘いとしての「猫」を考えさせられたのは『1Q84』(BOOK2、2009年)の中の猫の話です。
村上春樹の『1Q84』(BOOK2)に『猫の町』という小説のことが出てきます。
主人公の天吾が認知症で入院している父親を千葉県千倉にある療養所に訪れるため、館山行きの特急に乗ります。列車が東京駅を出発すると、天吾は文庫本を取り出して読むのです。それは旅をテーマにした短編小説のアンソロジーで、その中に猫が支配する町に旅をした若い男の話がありました。それが『猫の町』です。
この『猫の町』は村上春樹の創作のようですが、『1Q84』によれば、その物語はあまり名を聞いたこともないドイツ人の作家が書いたというもので、第一次大戦と第二次大戦との間に書かれたものとなっています。
ストーリーは、青年が鞄ひとつで気ままな旅をしていると、列車の車窓から美しい川が見え、静けさを感じさせる町が見えてきます。川には古い石橋がかかっていて、その風景に心を誘われた主人公は、列車が駅に到着するとそこで降りるのです。
ところが駅には駅員がいません。青年は石橋をわたって町まで歩いていきますが、そこにも人の姿がありません。ひとつだけあるホテルの受付にも誰もいません。そこは完全に無人の町に見えます。
でも実はそこは猫たちの町だったのです。そして、日が暮れかかると石橋を渡ってたくさんの猫たちが町にやってきました。
その猫たちは買い物をし、ホテルのレストランで食事をして、居酒屋でビールを飲み、陽気な猫の歌を歌い、手風琴を弾きます。踊り出すものもいます。でも明け方近くになると、猫たちはそれぞれの仕事や用事を終えて、ぞろぞろと橋を渡って、元の場所に帰っていくのです。
青年は、この猫の町の不思議な光景を、もっと見たくて、そこにとどまるのですが、3日目の夜に「なんだか、人のにおいがしないか」と1匹の猫が言い出し、「そういえばこの何日か、妙なにおいがしていた気がする」と他の猫が賛同します。
「しかし変だな。人間がここにやってくることはないはずなんだが」「ああ、そうだとも。人間がこの猫の町に入って来られるわけがない」「でもあいつらのにおいがすることも確かだぞ」…などと言って、猫たちは、その人間のにおいの発生源を求め、青年がいる鐘撞き台にあがってくるのです。
絶体絶命です。猫たちはくんくんとにおいをかぎますが、「不思議だ」「においはするんだが、人はいない」「たしかに奇妙だ」「でもとにかく、ここには誰もいない。べつなところを探そう」と言って、首をひねりながら去っていきます。
つまり猫たちには彼の姿は見えないのです。でもこの町に残るのはあまりに危険なので、青年は朝になったら午前の列車で町を出て行くことします。しかし今度は列車が駅に停まらないのです。列車の運転手や乗客からは、駅の姿も青年の姿も見えないかのようです。
そして、そこに「彼は自分が失われてしまっていることを知った」と記されています。「ここは猫の町なんかじゃないんだ」と彼は悟ります。「それは彼自身のために用意された、この世ではない場所だった。そして列車が、彼を元の世界に連れ戻すために、その駅に停車することはもう永遠にないのだ」という言葉で『猫の町』の話は終わっています。
さて、この『猫の町』とは、何でしょうか。そのことを今回、考えてみたいのです。
この「猫の町」に入り込んでしまった主人公の「彼を元の世界に連れ戻すために、その駅に停車することはもう永遠にないのだ」というのは、『スプートニクの恋人』の「高い枝にしがみついたまま、固くなって死んでいる可哀想な子猫」につながるものがあると思います。「どこにも行けないまま、そこで飢えてひからびて死んでしまった」子猫です。
詩人、萩原朔太郎の短編小説に「猫町」という作品があります。主人公が軽便鉄道を途中下車して、猫ばかり住んでいる町に入っていってしまう怖い話です。『1Q84』が刊行された時、この「猫町」と『1Q84』の『猫の町』との関連を指摘する人もいました。
岩波文庫の『猫町 他十七篇』の清岡卓行さんの解説によると、「猫町」は文芸・文化誌『セルパン』の1935年8月号に発表された作品で、その発表の前には1931年9月18日の満州事変、また1932年1月28日の第1次上海事変がありました。
また発表の後の1937年7月7日には盧溝橋事件、同年8月13日は第2次上海事変が起こっていて、「猫町」の発表は「日中のいくつかの戦乱勃発の間に挟まれている」ことが分かります。
『1Q84』の『猫の町』も「第一次大戦と第二次大戦にはさまれた時代に書かれたものだと解説にはあった」と記されているので、確かにもしかすると萩原朔太郎「猫町」と少し関係のある作品なのかもしれませんね。
さらに清岡卓行さんも解説でかなりくわしく書いていますが、イギリスの怪奇小説作家、アルジャノン・ブラックウッドに「猫町」によく似た「古き魔術」という中編小説があるのです。この作品と『1Q84』の『猫の町』との関係を指摘する人もいました。
「古き魔術」も、あるイギリス人が毎夏恒例の一人での山歩きの帰途、超満員の列車が不愉快になって、北フランスの小さな町で下車する話です。
中世的な町並みの中の宿屋に泊まると、そこの女主人は巨大な猫のようですし、猫族のように優雅で身軽な宿屋の17歳の娘も登場しますし、町の人たちも猫に変身したりします。
「猫町」も「古き魔術」も、どちらも9月の山地での小さな町に、鉄道を途中下車して、入っていくと、そこは猫が支配する町であったという話です。ですから両作の類似点を指摘する文は、昔からあったようです。
そして「古き魔術」は「猫町」発表より27年も早く出版されていますので、萩原朔太郎が先行作品に影響を受けたのか、また偶然の結果か、いろいろ考えることができます。
さらに『1Q84』の『猫の町』との関連もどのようにあるのか…。それらのことに興味のある方は、当該の作品を読まれたらいいかと思います。(私はアルジャノン・ブラックウッドの作品は紀田順一郎訳「いにしえの魔術」で読みました)
ここでは、村上春樹作品の中での猫、また『1Q84』(2009年)の『猫の町』について考えてみたいのです。
『1Q84』の英語版が刊行された際、同作の中から幾つかの部分を村上春樹がピックアップし、執筆・再編集して、米国の「ニューヨーカー」誌の2011年9月5日号に「Town of Cats」という短編を発表しています。
村上春樹は短編から長編を書くことは、例えば「螢」から『ノルウェイの森』のように、いくつかの例がありますが、逆に長編から短編を制作したというのは珍しいですね。
長編『1Q84』から、作られた短編の題名が「Town of Cats」なんですから、やはり『猫の町』という話には、何か大切な意味が込められているのではないかと思います。
さてこの「猫の町」とは何でしょうか。
紹介したように天吾が列車の中で読んだ小説『猫の町』では最後に主人公が「ここは猫の町なんかじゃないんだ」と思います。「それは彼自身のために用意された、この世ではない場所だった」と書いてあります。この世ではない場所とは、異界のことでしょう。
そして『1Q84』の「猫の町」はかなり重層的書かれていますが、でも最も具体的なところとしては、死の床にある父親が療養している千葉県千倉の町が「猫の町」と重なっています。また「猫の町」は死にゆく父親の世界、また霊魂の世界という意味もあるかと思います。
入院している父親をしばらく看るために天吾は千倉に出かけ、比較的安い旅館を探して滞在し、父親の療養所に通います。「そのようにして海辺の『猫の町』での天吾の日々が始まった」と書かれています。
東京の高円寺の自宅アパートに戻った天吾が眠っていると、午前2時過ぎに千倉の療養所の看護婦からの電話で起こされます。父親が亡くなったのです。
天吾はその知らせを受けて、列車の時刻表などを見ながら、「猫の町」から帰ってきたばかりなのに、またそこに戻らなくてはならないと思います。
そのように「猫の町」は、療養所のある千倉、また父親の死の世界ということを示していると思います。
そして、この小説『猫の町』についても、私には「4」への村上春樹のこだわりがあるのではないかと思っています。
紹介したように列車の中で『猫の町』を読むのです。そこで「天吾はその短編小説を二度繰り返し読んだ」とあります。続いて面会した父親に「猫の町の話を読みたいのですが、それでかまいませんか」と言って、父親のために『猫の町』の朗読をしています。
さらに、東京・高円寺のアパートに戻った天吾が、天吾の部屋に潜んでいる「ふかえり」という少女作家から「ホンをよむかおはなしをしてくれる」と言われて、「『猫の町』の話でよければ、話してあげられる」と応えて、『猫の町』の話を始めています。
村上春樹は、その場面で「彼はその短編小説を特急列車の中で二度読んでいたし、父親の病室でも一度朗読した」と確認するかのように記しています。つまりふかえりに語るのは「4」回目なのです。ここにも『猫の町』が死の世界、霊魂の世界、異界であることが記されているのではないかと私は考えて(妄想して)います。
『スプートニクの恋人』の「猫」と同じように、『1Q84』の「猫」もやはり異界へ誘(いざな)う「猫」です。
さて、その異界に入り込んでしまうと、『猫の町』の主人公にとっては、列車が「彼を元の世界に連れ戻すために、その駅に停車することはもう永遠にない」のです。主人公は「猫の町」から脱出することができません。
天吾も「猫の町」に何度か行くのですが、でも彼は、列車に乗って「猫の町」に行き、そして戻ってきました。「幸運なことに小説の主人公とは、違って、帰りの汽車にうまく乗り込むことができた」と記されています。
『スプートニクの恋人』の「高い枝にしがみついたまま、固くなって死んでいる可哀想な」「どこにも行けないまま、そこで飢えてひからびて死んでしまった」子猫のように消えてしまった、すみれが、物語の最後に「ぼく」の家に深夜電話をかけてきます。
「ねえ帰ってきたのよ」とすみれが言い、「いろいろと大変だったけど、それでもなんとか帰ってきた。ホメロスの『オデッセイ』を50字以内の短縮版にすればそうなるように」と言います。
なぜ、天吾は「小説の主人公とは、違って、帰りの汽車にうまく乗り込むことができた」のか、なぜ煙のように消えてしまったすみれが「いろいろと大変だったけど、それでもなんとか帰ってきた」のか。その理由を考えてみたいのです。
でも、ここまででも、あまりに長いコラムとなってしまいました。「天吾」と「すみれ」の帰還の理由について、私の妄想を記すのは次のコラムにしたいと思います。
「村上春樹を読む」の読者で、そのことに興味がある方は、この帰還の理由について、来月まで一緒に考えてください。(共同通信編集委員・小山鉄郎)
******************************************************************************
「村上春樹を読む」が『村上春樹クロニクル』と名前を変えて、春陽堂書店から刊行されます。詳しくはこちらから↓

