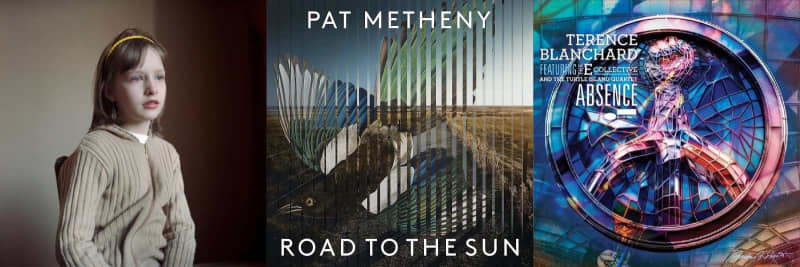
【特集】2021年、私の愛聴盤 ~ 藤本史昭
毎年恒例、BLUE NOTE CLUB執筆陣による今年愛聴したジャズ・アルバム3枚をご紹介します。
第一回目は、連載コラム「スタンダード名曲ものがたり」でおなじみのジャズ評論家の藤本史昭さんです。
___
文:藤本史昭
パット・メセニー『ロード・トゥ・ザ・サン』(Modern Recordings)
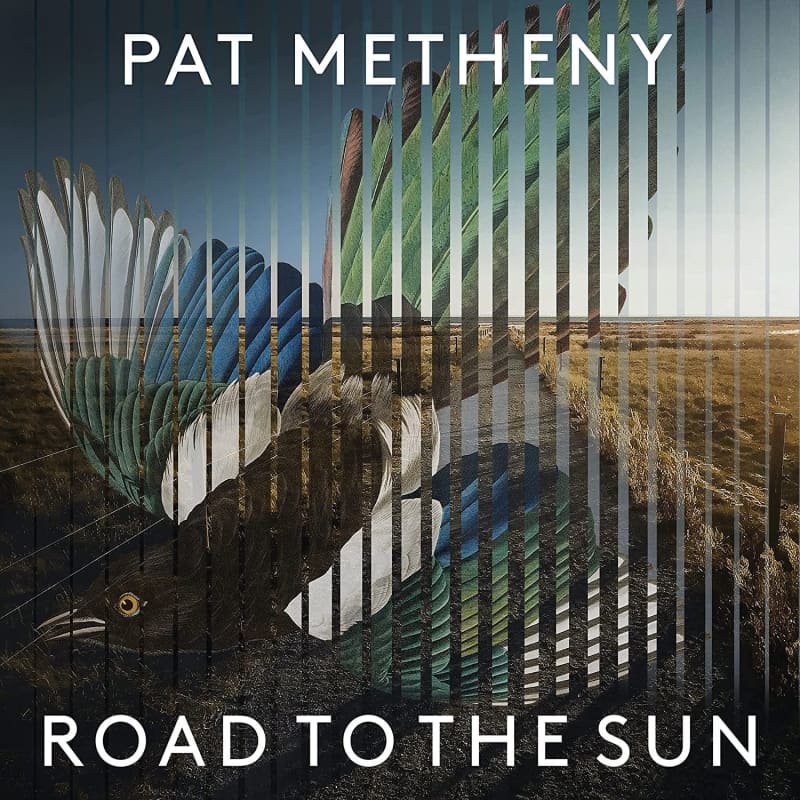
テレンス・ブランチャード『アブセンス』(Blue Note)

桑原あい『Opera』(Verve)

20~21年にかけてのパット・メセニーは、充電していたエネルギーを放出するかのように意欲作を連発した。久々のスタジオ録音でオーケストラと共演した『フロム・ディス・プレイス』。若く優秀なミュージシャンと流動的にコラボしていくプロジェクト「サイド・アイ」の第一弾『サイド・アイ NYC』。中でも特に印象深かったのが、作曲家としての側面をアピールしてみせた『ロード・トゥ・ザ・サン』だ。
「この世代でもっとも正確でソウルフルなクラシック・ギタリスト」と評されるジェイソン・ヴィオーと、メセニーをして「世界で最高のバンドの1つ」といわしめるロサンゼルス・ギター・カルテットのために書き下ろした楽曲を収めた本作は、すべてがスコア化されているという点でジャズとは呼び難い面もあるが、しかしそこには我々が慣れ親しんだメセニー・テイストが充満しており、彼自身のパフォーマンスをきいたのとなんら変わりのない満足感を与えてくれる。
薄々感じていたことではあるが、僕がメセニーの音楽を愛するのは、プレイそのもの以上にそのコンポジションゆえに、であるのかもしれない。とはいえ、1曲だけ自ら編曲演奏したペルトの〈アリーナのために〉も素晴らしい出来だが。
<動画:Pat Metheny: Four Paths of Light, Pt. 1>
この作品のように、今年は“書かれた音楽”、あるいは“書かれた音楽と即興のコラボ”に惹かれることが多かった。挾間美帆&DRBBの『イマジナリー・ヴィジョンズ』。上原ひろみ ザ・ピアノ・クインテットの『シルヴァー・ライニング・スイート』。ブラッド・メルドーとオルフェウス室内管の『ヴァリエーション・オン・ア・メランコリー・テーマ』。フローティング・ポインツとファラオ・サンダース、そしてロンドン交響楽団がコラボした『プロミセス』。
そんな中、熟達と新しさを兼ね備えた作編曲書法、そして錬磨された即興演奏で大きな喜びをもたらしてくれたのが、テレンス・ブランチャードの『アブセンス』だ。自身のグループE-Collectiveにタートル・アイランド・カルテットを加えた本作は、表向きはウェイン・ショーターへのオマージュを謳っており、事実12曲中5曲がショーター曲のカヴァーだが、その中身はといえばこれはもう完全にブランチャードの世界。
なるほどたしかに全編で――メンバーのオリジナル曲でさえ――ショーターを強く想起させる響きが鳴らされているけれど、しかしその響きは、長年にわたって映画音楽やオペラの分野でキャリアを積み上げてきたこの人ならではのフィルターを通して、実にイマジナティヴに増幅されている。精妙にコントロールされたエレクトリック・サウンドとなまめかしいストリングス。それに乗せて美しく咆吼するトランペット。それらを一分の隙もなくまとめ上げるブランチャードの手腕は、まったく見事としかいいようがない。
<動画:Terence Blanchard ft. the E-Collective and the Turtle Island Quartet - Absence>
上記2作品とは対照的に、その瞬間の感興に依ってピアノ1台で生み出されたのが、桑原あいの『Opera』だ。エレクトーン出身だったためずっとピアノを美しく鳴らすことにコンプレックスを感じていたという彼女が、クラシックのレッスンやソロ・パフォーマンスの経験を重ねた末、ようやく1つの手応えを得て着手した本作は、まるで音楽に殉死するかのような凄まじい集中力に貫かれていて、聴くたびに心を振るわされずにはいられない。
とりわけ、ピアニストが尋常ならざる思い入れを抱いて弾いたという〈ニュー・シネマ・パラダイス〉には、コロナ禍の最中どれほど慰められたことか。桑原のファンや友人である著名人たちのリクエストに応えたジャンルレスな選曲が話題になったが、そういうことは抜きにしても、これは彼女のキャリアのメルクマールとなる作品であろうと思う。ホール音響をそのまま活かしたすっぴんな録音も、音楽に対するこの人の誠実があらわれているようで好ましい。
