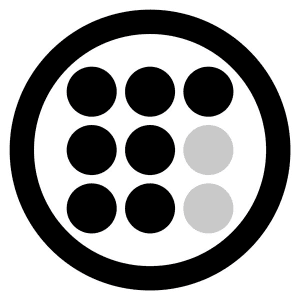2003年夏全国Vの主将で、硬式野球部長を務める松林康徳氏の進路指導のポリシー
茨城の常総学院高は、これまでプロ13人を輩出した野球名門校だ。一方で、2021年度は国公立大に118人、医学部に8人、2022年度も東大に2人が合格するなど、進学校としても知られている。学校としての目標は「4年制大学への進学」で、硬式野球部も例外ではない。では、どんな進路指導をしているのか。保護者が悩む進路についての連載「セレクトデザイン」で、硬式野球部の松林康徳部長に話を聞いた。
硬式野球部でも、4年制大学への進学を前提とした進路指導。高卒と大卒では平均的な生涯年収に大きな差が出るからだ。厚労省が公開した2020年の「賃金構造基本統計調査」でも、同世代で比較した平均年収は大卒のほうが最大で200万円近く高くなっている。同校からは近年、巨人・菊田拡和外野手(2019年ドラフト3位)、楽天・内田靖人内野手(2013年ドラフト2位)らが高卒でプロ入りを果たしているが、彼らは学業熱心で、成績も上位。その上で、プロ入りを選択していたと振り返る。
「プロに入って60歳まで終身雇用だったら、卒業後すぐに『プロに入れ』となりますけど、現実はそうではない」。プロを目指していても、大学は遠回りではないと考えている。
進学を前提とする進路指導の中で、大事にしているのは「目的を持つこと」。近年は、進学率が高まり“大学全入時代”に突入。「何をしたいのか」を明確にして入学することが、同世代との差をつける第一段階だと考える。硬式野球部での目的は、文武両道だ。
「大学でも野球部に入って文武両道を目指してもらうような指導です」。常総学院では、一般入試からは野球部に入部できず、特技推薦での合格者のみが入部できる決まりになっている。4年制大学への進学を勧める学校方針の中、学業だけでなく「野球ありきで入学しているので、大学でもその強みを生かしてほしい」と願う。
先輩たちがあいさつに来る際に後輩に進路指導するのが恒例になっている
選手たちが進路を意識するようになるのは、2年になってからだ。カギとなるのは、先輩の声。「基本的にOBがあいさつに来たら、大学の話を話してもらうようにしています」。実際の大学生の声を聞くことで、行きたい学校が明確になってくる。その後、2年の終わりごろに面談を通じて、進路の希望を調査する。
甲子園常連の強豪校のため、野球中心の学校生活かと思えば、意外にもそうではない。テスト前には必ず、ホール勉強と呼ばれる選手同士での勉強の進捗確認を行う。また寮でも、平日の2時間を自主練習もしくは自主勉強の時間を設定する。選手たちはテスト前や大会前など期間に合わせて、練習と勉強を両立させるのだ。
各教科の教諭たちも強力な味方だ。「野球部だから勉強しなくても大丈夫というのはないです。むしろ野球部だからこそ厳しく指導して頂いております」。学校にとっても野球部はシンボルであるため、決して勉強をおろそかにはさせないのだ。
「もちろん、大学に行かなくても将来幸せな人はたくさんいます。選択肢のひとつとして考えてほしい」と前置きするが、その中でなぜ大学でも文武両道を目指すのか。松林氏が願うのは、社会で活躍できる人材になってもらうことだ。そのためには、勉強、野球の一辺倒ではダメだと考える。「ゴールは高校野球ではないので。大学へ進学し、勉強する習慣をつけて、野球を通じて知見を広げてくれれば、将来の選択肢も広がると考えています」。常総学院の進路指導は、大学進学だけでなく、先のキャリアまで見据えている。(川村虎大 / Kodai Kawamura)
・左打ちは有利か、硬式は中学からやるべき? 高校球児も指導する元プロの見解は