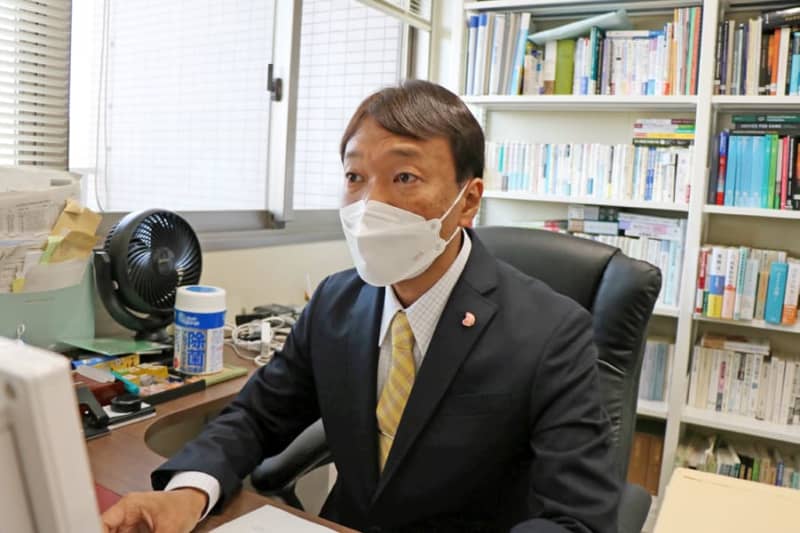
ロシアのウクライナ侵攻を巡る国際法の課題などを考えるセミナーが20日オンラインであり、長崎大多文化社会学部の河村有教准教授(刑事法)は、大統領の裁量で軍事行為を正当化できるロシアの現行憲法の問題点を指摘。「いかに法によって武力行使を容易にさせないようにするか、自国の法も含め国内法の在り方に一人一人が関心を持つことが重要」と訴えた。
河村氏はロシア憲法では大統領権限が肥大化し「大統領の決定が適正か熟議できるような手続きが保障されていない」と説明。言論の自由などは保障されているが、国土防衛や安全保障のため制限できる条項があるという。戦時中の日本も例に「戦争を容易にし、国家の安全を盾に人権を制約してしまう法が存在することを認識してほしい」と警鐘を鳴らした。
ロシアはウクライナ東部の一部地域の独立を一方的に承認、援助条約を結び、国連憲章が認める「集団的自衛権」の行使を主張し軍事侵攻を正当化。ウクライナの提訴を受け、国際司法裁判所(ICJ)は3月に侵攻を停止するよう命じたがロシアは無視している。
河村氏は、拒否権行使など国連で大きな権限を有した安全保障理事会の常任理事国が国際法の手続きを意図的に無視し、違反している現状を憂慮。「国際社会は手続きを順守させるためのルール化を検討する必要がある」と求めた。
国際人権セミナーは同学部主催。約70人が聴講した。

