
いつの時代も芸人は売れてなんぼ。若手は特に知恵を絞る。どんなことをしても人気者になりたい。明治初年頃は三遊亭圓朝(1839~1900)を頂点に、落語の名人上手が綺羅星のごとくいた。だが、政府は寄席を厳しく取り締まった。風紀が乱れるというのだ。権力は往々にして笑いを目の敵にする。自分たちが笑いの標的にされるのを嫌って。役人も政府高官も、自堕落な生活をしながら庶民には厳しかった。
明治3年「(東京)市中の寄席は、講談昔噺などに限って営業するのはよいが、浄瑠璃人形を取り交えたり、男女入り交じっての物真似などはいけない」と布告(小島貞二編『落語三百年』)」。さらに、明治9年には東京府庁は諸芸人に税金を課した。今と違って当時の芸人は地位も収入も格段に低かった。明治9年頃に東京の寄席は162軒ほどあったが、みんな小さなもので客足も伸びず、一晩で50人も入ればいい方だった。芸人は入った客の数で給金がもらえ、普通の芸人で客一人2文か3文。真打の給金が60文から70文だったが、圓朝ほか数人が100文で破格だったという。
明治14年3月、「諸芸新聞」に愛宕下の恵智十(えちじゅう=寄席)に、ステテコの円遊、へらへらの万橘、ラッパの円太郎、ペケレツの談志が出演して毎晩大入り客止め、という記事が載った(前掲書)。後に、彼らは珍芸四天王と呼ばれるが、まさにおかしな芸で、不振の寄席に大勢の客を呼び込んだ。
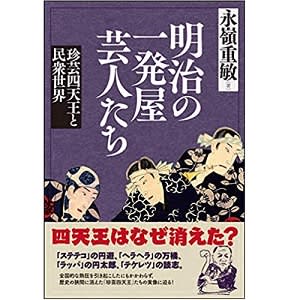
ステテコというのは下着で、膝の下まである股引のこと。尻端折りして、「アンヨを叩いてしっかりおやりよ、そんなこっちゃなかなか真打になれない」などと即興の唄を歌い、鼻をつまみ、膝を叩いて、寄席の高座で踊りまくったら、受けて、いっぺんに人気者になった。
万橘は羽織も手拭いも真っ赤。着物をはだけたらシャツも赤。扇子を開くとこれも赤。楽屋の太鼓に合わせて、後ろの羽目板を叩きながら「太鼓が鳴ったらにぎやかだ、大根(だいこ)が煮えたらやわらかだ、ヘラヘラヘッタラヘラヘラへ……」など言って歌い踊った。
円太郎は市中を走る鉄道馬車の馭者が鳴らすラッパを吹きならしながら高座に出て来て、都々逸やカッポレ、三下がりなんかを演じる合間にプップーと入れ、たまに「おばあさん、あぶないよ、プップー」と愛嬌を振りまいた。
四代目立川談志(生年月日不明~1889)。一席終わると羽織を後ろ前に着て、手拭いで鉢巻き、扇子を半開きで襟元に差し、座布団を半分に折って抱き、「そろそろ始まるカッキョの釜堀り、テケレッツノパァ…」と中国の二十四孝の「郭巨(かっきょ)の釜堀り」の故事をマイムでやった。
四天王は談志以外は圓朝の弟子。圓朝はこういう芸を快く思っていなかったのか、ふとそれを周囲に漏らした。その言葉が幕内に伝わると、やっかみも手伝って、円遊ボイコット運動が起こった。勢いづいた連中はある日、芸人13人連れ立って圓朝宅へ談判に。中に大師匠連も交じっていた。事前に察知した圓朝は、円遊を横に侍らせ、「まだまだ未熟者ゆえ、お引き立てのほどを……」と挨拶し、酒肴でもてなした。やって来た連中、すっかり調子が狂って何も切り出せず、酔って帰ったという。さすがは名人、弟子思いのエピソードも洒落ている。(落語作家 さとう裕)

