
大阪市廃止ってどういうこと? 市民レベルのミニ集会や講演会などが市内各地で開かれている。大阪市東成区で10月10日、市民グループ「すっきやねん大阪」が開いた集会では元大阪府副知事の小西禎一さんが解説した。小西さんは橋下府政改革チームのリーダーで「都構想」の制度設計にも携わった行政のプロ。要旨をお届けする。(新聞うずみ火 栗原佳子)
「都構想」「府市合わせ」「二重行政」、推進派がばらまく三つの言葉の幻想がある。
賛成多数になっても「大阪都」にはならない。地方自治法の条文にも「二重行政の解消」「成長を加速」などの文言はない。二重の意味で「都構想」という表現は誤りだ。
府と市はいつもけんかしている「府市合わせ(不幸せ)」。大阪市がなくなればスピーディーに知事が決め成長が加速すると推進派はいう。
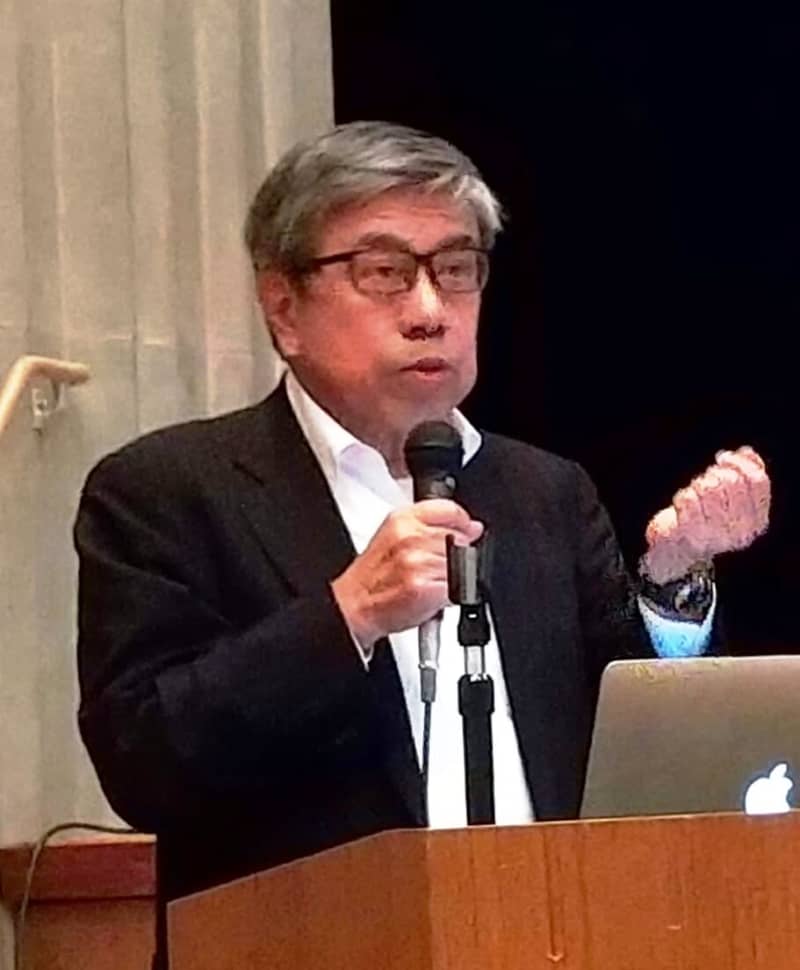
「止めることが対案」と話す小西さん
だが、府市は協力して都市基盤整備や産業振興をはかってきた。確かに磯村隆文市長と太田房江知事が言い合いをしたこともあるが、行政は知事と市長だけがやるのではない。大阪市と府の立場の違いがあり意見が一致しないことがあるのは当然で、その不一致を協議調整して一致点を見出すことによって住民にとってよりよい選択をすることができる。「府市合わせ」で市がなくなれば成長が加速するというのは論理的に間違いだ。
また、推進派は司令塔を一元化することで物事が早く進むという。しかし、地方自治制度は都道府県と市町村の二層制。大阪府と市町村が協力連携して地域の発展、安全安心の確保、福祉の向上をはかっていく。司令塔の一元化というなら、大阪の成長に特別区や市町村は関わってはいけないということになる。地方自治制度に反している。
二重行政として推進派がいつも挙げるのが市のワールドトレードセンター(WTC)と府のりんくうゲートタワー。バブルに踊らされた施策の失敗で二重行政だったからではない。インテックスと国際会議場も二重行政だというが、国際会議を持ってこようと思ったら展示場と会議場は両方必要だ。図書館も体育館も二つある方が市民にも府民にもいいはずだ。しかも松井市長は議会で「いまは二重行政はない」と答弁している。

道頓堀川で行われた水上パレード
政令指定都市の大阪市を廃止して、市域を四つに分割し特別地方公共団体の特別区を設置するのが「都構想」。特別区の実体は権限も財源も大幅に縮減された不完全な自治体だ。まず権限が制約され、多くの仕事を失う。一般市の権限である上下水道、消防、都市計画さえない。だが財政負担は引き続き市民が負う。府に移管される仕事の財源はいまの大阪市の財源を使うことになっているからだ。財源7割を失い、約6割を府の交付金に頼らざるを得ない。
市民の共有財産である大阪市そのものを失い、権限を失い大事な財産も失うのに負担だけ継続させられる。淀川区8割、天王寺区5割の職員が間借りするが、いつまで間借りできるわけもなく、特別区はいずれ庁舎を作る。それを前提に試算すると初期コスト1300億円。壮大な無駄だ。
感染症対策や防災対策も基礎自治体の区域が四つに分割されて大丈夫なのか。大阪府も都市づくりのパートナーを失い、新たに「特別区」の補完という仕事が増える。「都構想」は大阪市域に集中投資する都心中心主義。府域全体の発展をめざしてきた大阪府を変質させるし、府民にとっても不幸せ。推進側は、反対なら対案を出せというが、とんでもない構想なので、止めることが最大の対案だ。

