この夏は世界各地が40度を越える記録的な猛暑に見舞われ、地球温暖化対策の必要性を訴える声が高まっています。欧米ではエコな移動手段として、また配送手段としても鉄道の利用を見直そうという動きがありますが、そのためには安全で安定した運用のためのインフラ整備が不可欠となります。
鉄道会社の多くは線路の安全を確保する保線作業に多くの時間とコストをかけており、電車が走らない夜間に集中して行われる線路点検などでは整備員の安全確保も求められます。そこで、点検作業をできるだけ自動化する方法の一つとして、ドローンを活用する研究開発が進められています。
世界トップレベルの鉄道大国である日本では、JR東日本、KDDI、プロドローンの3社共同による「スマートドローン」を活用した線路設備点検の効率化に向けた実証実験が2020年2月に実施されています。線路の上空をドローンが自律飛行し、搭載されたカメラで設備の状態を撮影するというもので、ドローンは遠隔地の係員が操作することで、伝送された映像を使用して昼夜を問わず点検ができることを実証しました。


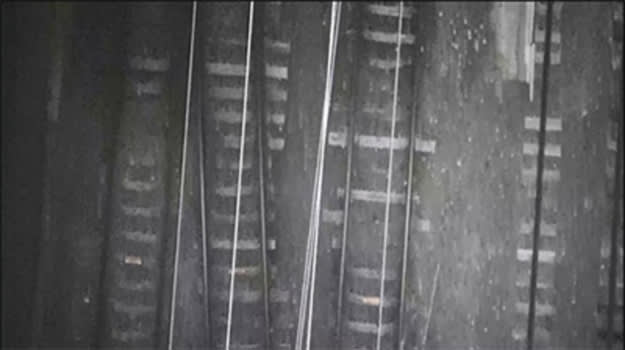
実証実験の目的は、携帯電話の通信網を利用して離れた場所から操作できるスマートドローンを活用し、定期点検はもちろん、これまでは異常を検知した場合は整備員が現場に急行して目視で確認していたのを、まずはドローンで確認できるようにすることです。日本の鉄道は線路だけでなく架線の確認も重要なので、空を飛べるドローンは有用だとされています。
現在、多くの鉄道会社が点検作業にドローンを活用していますが、線路よりはトンネル内や橋りょうといった場所が対象であることが多いようです。ドローンの自動飛行による点検は、BVLOS(目視外飛行)の規制があることが課題でしたが、そのあたりはまもなく緩和が進むことから、これから本格的な活用が始まる可能性があります。
2021年11月に名古屋鉄道が行った実証実験では、災害時に通常は作業員が2時間ほどかけて行う距離の初期点検作業を、ドローンを使用して10分ほどに短縮しています。市街地の地上を営業する路線では初めての取り組みで、ここでもドローンの開発はKDDIとプロドローンが協力しています。現在、踏切周辺のカメラ映像をAIで分析し、異常を検知するシステムと併せて開発が進められており、2023〜24年の実用化を目指しています。

しかし、海外の鉄道会社となると状況は大きく変わります。欧米の鉄道は日本に比べると比較的長距離を走るものが多く、ドローンで点検するには運用距離が足りないという課題があります。そこで注目したいのが、ノルウェーを拠点とするNordic Unmanned社が開発している、線路上を走る鉄道専用点検ドローンの「
」です。

The Staaker Railway Droneの見た目はいわゆる普通の大型のクワッドローター型のドローンですが、足の部分に車輪が付いていて、線路の幅にぴたりと合せて機体を載せることができます。本体にはカメラとセンサーが搭載されていて、通常は線路上を走行しながら線路の状態を点検し、作業員は離れた場所から現場を監視するか、蓄積されたデータを分析することで異常がないか確認できるようにしています。平均速度は時速20kmで、バッテリーの消費電力が抑えられるうえに高く飛ぶ必要がないのでバッテリーも大型化が可能になり、約7時間約200kmの距離を昼夜を問わず移動できます。

本ドローンが最もユニークなのは、電車が運行している時間帯でも使用できることにあります。線路上を点検している時に電車が近付くと空にふわりと飛び上がり、通過した後に再び線路上に自動で着地することができるというわけです。複数の並行する線路を移動しながら点検することも可能で、点検効率を大幅に高められるとしています。
https://www.youtube.com/watch?v=srBggRXdrAM 開発に協力した米国の大手貨物鉄道会社の一つであるBNSF鉄道は、「この画期的なシステムは世界の鉄道のインフラ点検に革新をもたらすだろう」と自信を持って取り組んでいます。将来的にはドローンを水素燃料で動かすことも検討しているそうで、さらに長距離を効率良く点検が行えるようユースケースを増やしているところだとしています。
今は既存のドローンをそのまま使用しているように見えますが、利用が拡がれば線路を走るのに適した機体が新たにデザインされるかもしれませんね。
