
夢を追ってアメリカに渡った兄は、銃撃事件に巻き込まれて突然亡くなった。29年前の出来事だが、裁判は今も終わっていない。千葉県内を中心に活動する弁護士の伊東秀彦さん(42)は、兄を殺害した男の裁判の情報を得るため、私費で通訳を雇い、専門用語と格闘してきた。
米国まで足を運び、兄を撃った被告にも向き合った。弁護士として法廷に立ってきた自分ですらパニック状態になり、内容はほとんど記憶に残らなかった。
国内外の事件を問わず、被害者への支援は十分とは言えない。被害者や家族には、どのタイミングで、どんな支援が必要か。伊東さんは弁護士として、また遺族として試行錯誤を続けている。(共同通信=大森瑚子)

▽突然の知らせ「お兄ちゃんが撃たれた」
1994年3月の早朝、寝室に現れた母親は取り乱した様子だった。「お兄ちゃんが撃たれた」。米ロサンゼルスで日本人留学生2人が銃撃され、伊東さんの兄拓磨さん=当時(19)=が巻き込まれたと外務省から連絡があった。
自宅にはすぐにマスコミが殺到した。「奥さん、写真」。うろたえる母が言われるがまま兄の写真を手渡す姿をぼんやり見ていた。「こうやって写真が世間に出ていくのか」。事件の実感がわかず、人ごとのよう感じていた。
裏口から隣の家の中を通してもらい、着の身着のまま現地へ向かった。病院のベッドで対面。間もなく死亡が確認され、両親の泣き叫ぶ声が耳に残っている。
▽「映画に関わりたい」。夢の途中だった兄
ぜんそく持ちだった兄は外遊びが制限され、屋内で絵を描いたり、映画を見たりして過ごすことが多かった。「手先が器用で図工や絵が得意。好きなことを見つけたら自分で道を切り開くタイプ」。ぜんそくに苦しむ中でも、絵や映画に励まされているように見えた。「いつか映画制作に関わりたい」と学校選びから願書の提出まで自力で進め、アルバイトで資金をためた。1993年夏に米国の映画大学に進んだ。
直前の92年には、米ルイジアナ州に留学中だった高校生服部剛丈さんが射殺される事件があり、両親は心配したが、「最終的には兄の熱意に押され、送り出した」。

▽突然「犯罪被害者遺族」になった
当時中学1年生だった伊東さんは、突然「被害者遺族」になった。間もなく、主犯のレイモンド・バトラー被告が逮捕された。18歳だった。
バトラー被告はギャングのメンバーで、低所得者用の住宅に暮らしていた。「金持ちの留学生が狙われた」とする根拠のない報道もあった。伊東さんは「兄が自力でつかんだ道。悔しかった」と振りかえる。96年には一審で死刑判決が言い渡された。家族と墓前で「やっと裁判が終わったよ」と報告した。
法律や犯罪被害者に関わる仕事の重要さを実感した。「経験を生かせるかも」と考え、司法試験に挑戦。2005年に弁護士登録した。
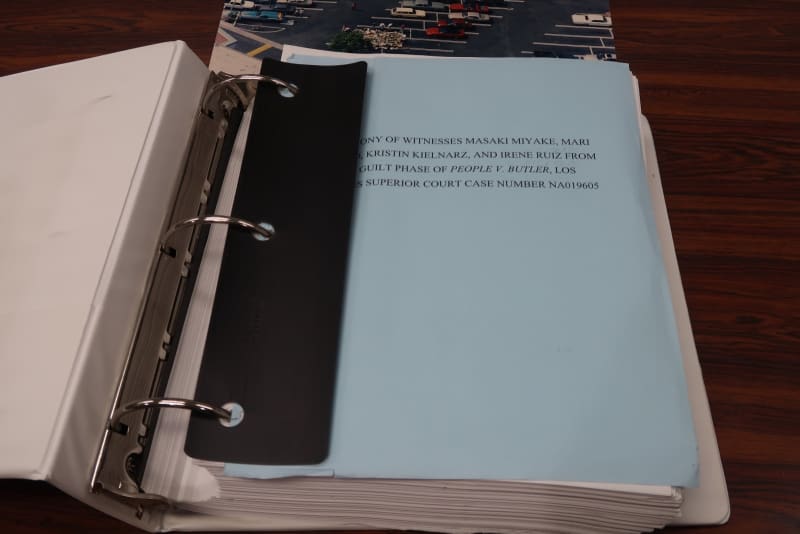
▽弁護士の道へ。今も続く裁判
翌年、兄を撃ったバトラー被告の死刑執行状況を、外務省を通じて問い合わせてみた。すると、実は裁判が終了しておらず、被告の刑が未確定だったと知らされた。
「家族の知らないところで裁判が続き、兄の名が読まれ続けていたのか」
ショックは大きかった。
バトラー被告は別の殺人事件でも起訴されるなどしており、裁判は複雑化していた。外務省から米国の担当検事を紹介してもらい、状況を直接問い合わせた。メールのやりとりは専門用語が多く、私費で通訳を雇った。「補助制度もないため金銭的負担は避けられない。当事者によって情報格差もある」
2012年2月には、差し戻し審での情状証人として渡米し、陪審員裁判に出廷した。この時の通訳の渡航費用も私費だった。
審理では、バトラー被告から直接質問される機会があった。「初めて会いますね」「私についてどう思っていますか」。簡単な質問が2問ほどだったが、加害者を前にパニック状態になった。やりとりをしたはずだが、自分が答えた内容はほとんど覚えていない。「なぜ遺族である自分が、こんな状況に置かれるのか」。気持ちの整理はつかなかった。
事件から29年が経過した今も、裁判が終結したとの連絡はない。

▽語る当事者、語らない当事者
伊東さんや家族は、これまで事件について積極的に発信してこなかった。「悲しみが癒えない中、日々の生活に精いっぱいで発信などを考える余裕はなかった」と振り返る。当時はインターネットも一般的ではなく、事件の記録や報道の痕跡はそう多く残っていない。
一方、事件について発信する当事者もいる。弁護士として犯罪被害者や遺族の支援に当たる中で痛感するのは、事件の情報が流通することで生じる誹謗中傷への対応の難しさだ。事件に巻き込まれた被害者は、報道による影響について考える余裕がない。近年はSNSの普及で、一気に情報が拡散し、被害者に関する臆測や誤った情報が拡散されてしまう。中には悪意を潜ませたものもある。
報道にどれくらい情報を提供するか、担当弁護士として被害者らの意向を確認する機会も多い。「知ってもらいたい気持ちもあるが、ネット上の反応が怖いから控える」と述べる当事者は少なくないという。
事件を語る当事者と、語らない当事者の差はどこにあるのか。
伊東さんは、発信する当事者も「決して気持ちに余裕があるわけではない」と指摘する。時間の経過や人との出会いなど、事件を語り出す理由は人それぞれだ。
多くの人に正しく事件を知ってもらうことは風化を防ぐことにもなる。それだけに、偏った情報や偏見に基づく中傷は伊東さんにとって「気持ちを踏みにじるもので許せない」ものだ。

▽当事者の裁判への思いとは
実務家としての経験から「裁判への思いは、当事者によって本当にさまざま」と感じることが多いという。自身と家族は判決の内容よりも、裁判が速やかに終わることを望んでいた。理由は、兄を「事件の被害者という社会的な存在」から「家族内で静かに弔う存在」に戻したかったから。一方で、どれほど時間がかかっても、望むような判決を勝ち取りたいという被害者や家族もいる。
当事者の人生は裁判後も続く。「裁判での救済には限界がある。地域で暮らしていく上で継続的な支援を考える必要がある」と伊東さん。費用や人員の確保を考えると、当事者に長く寄り添う仕組みを整えることができるのは、行政しかないと指摘する。
伊東さんは被害者支援の条例作りにも奔走してきた。2022年版犯罪被害者白書によると、被害者支援に特化した条例を制定している政令市は11、その他市町村では453にとどまる。
伊東さんは都道府県単位だけではなく、より住民に近い市町村単位での条例整備も重要と訴える。地域によって起きる犯罪の種類、被害者の国籍や年齢層は変化するからだ。各地から人が集まる観光地なのか、外国人が多く住む場所なのか、どんな産業が盛んか―。条例が地域性に合わせたものにならなければ、被害者への細やかな対応はできない。
「それぞれの頑張りや運に頼らず、必要な支援に導く制度の存在が重要。実現に向けて歩み続けたい」

