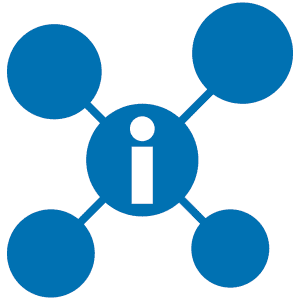■集団感染で出撃できず
「大君の御盾(みたて)となりて散らんとも 思いは遠し故郷の野辺」。17歳で特攻隊員に選ばれた伊藤義末(よしまつ)さん(95)=茨城県高萩市=は1945年3月、家族に宛てた遺書に、そんな辞世の句をつづった。
44年4月、海軍飛行予科練習生(予科練)として入隊。飛行機の操縦に必要な気象学、手旗信号などを徹底的にたたき込まれた。
戦況悪化が続く45年2月末、練習生たちが格納庫に集められた。「君たちの出番」。こう切り出した上官は「国のために頑張ってくれ」と続けた。特攻志願者を募ると、全員が即座に手を挙げた。「本当は挙げたくなかったけれど、考える余地はなかった」
■最後の面会却下
「志願」から1週間後、分隊長から正式に特攻隊員に命じられた。
思い出すのは温かい家族の笑顔。「一度家に帰って親、兄弟に会ってからの特攻が本望」。隊員たちと直訴したが、「最後」の面会はかなわなかった。
両親への感謝、自分が特攻隊員となったこと、古里への思い…。さまざまな思いを巡らせながらしたためた遺書を分隊長に託し、3月下旬、九州地方に向かう軍用列車に乗り込んだ。
向かった先は長崎県。訓練で乗り込んだのは飛行機ではなく、爆薬を乗せて敵艦に突っ込む木製ボートの水上特攻艇「震洋」だった。体当たりや砲撃の訓練は約3カ月間続いた。
訓練のさなか、所属部隊は山間の仮兵舎へ移転。環境は劣悪で、部隊全員が伝染病に集団感染。佐世保軍港内の海軍病院へ入院した。
病院では、看護婦(当時)から、沖縄戦の敗北を聞かされた。当時の日本は特攻で連合軍に大打撃を与え、有利な条件で講和に持ち込もうとしていた。「もし病気にならなかったら、沖縄で特攻していたかもしれない」。病に命を救われた。
その後、療養中の部隊に現場復帰の命令が下り、8月8日に特攻の出発地となっていた鹿児島県へ出発。全長約5メートルの特攻艇には250キロの爆薬を積んでいた。翌9日、米軍は長崎市へ原子爆弾を投下。長崎に残っていれば、任務を前に自分たちもどうなっていたか分からないと振り返る。
■喜び震えた再会
鹿児島へ向かう途中、部隊長の指示で長崎へ引き返した。数日後の新聞記事には「復員」の文字。意味が分からず尋ね、終戦を知った。
「やっと終わったか」「これからどうなってしまうのか」。生き残った安心と先の見えない将来。交錯する思いを抱えて自宅を目指した。
高萩に戻ったのは19日。玄関では、両親が「せがれの幽霊が立っている」。今生の別れと思っていた両親との再会。喜びに打ち震えた。
「こんなに苦しい体験をするのは愚かで、あほらしい。どんな理由があろうと、戦争は絶対にやってはいけない」。反戦への思いはこれからも変わらない。(おわり)