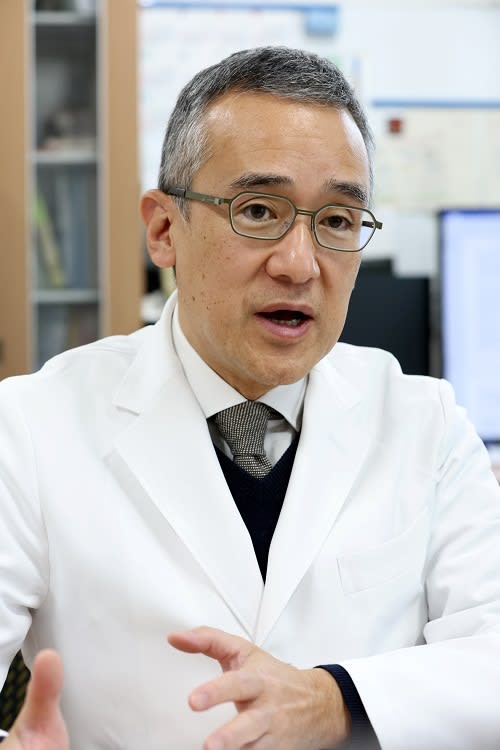
能登半島地震の被災地で避難者の感染症対策に当たった長崎大学病院の泉川公一教授が10日、本紙の取材に応じた。断水、停電、灯油不足で十分な対策を取れない避難所もあったが、「厳し過ぎるとストレスになる。百点満点は目指さずに70点で大丈夫」と助言したという。
泉川氏は日本環境感染学会の災害時感染制御支援チーム(DICT)の責任者として地震発生翌日の2日に長崎を発ち、3日午前に石川県庁の災害対策本部に入った。7日に長崎に戻るまで、本部で情報を収集しながら電話相談に応じ、避難所も巡った。
その中には断水のためトイレの水を流せず手作業で便を取り除いて地面に埋めている避難所がある一方、学校のプールの水をトイレ用に使っているケースもあった。換気をするにも停電などで暖房が使えず、寒さのため十分に窓を開けられないところもあった。
泉川氏は「避難から1週間くらいで感染症が広がるケースが多い」と話し、新型コロナウイルスなどの感染者が現在も増えているという。
一方、ほとんどの避難所が手指消毒用のアルコールを備えていた。コロナ禍を経験する前の2016年の熊本地震ではこうした光景は見られず、大きな変化だった。
6日は輪島市を担当していた災害派遣医療チーム(DMAT)の要請を受け、避難所の県立輪島高を訪問。コロナ、インフルエンザ、ノロウイルスの感染者別に隔離用の教室を設けていたほか、避難者は屋内外でスリッパと靴を履き替えていた。泉川氏は「例えばトイレに入った靴で枕元まで移動するのは非衛生的で感染リスクが高まる」とし、「屋内外で履物を替えることで理想に近い対策ができていた」と指摘した。
日本環境感染学会のホームページでは感染対策のマニュアルを公開中。泉川氏は「あらかじめ読んでおけば被災時の対応も変わってくる」と話している。

