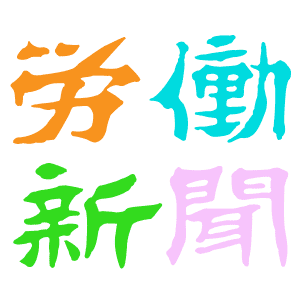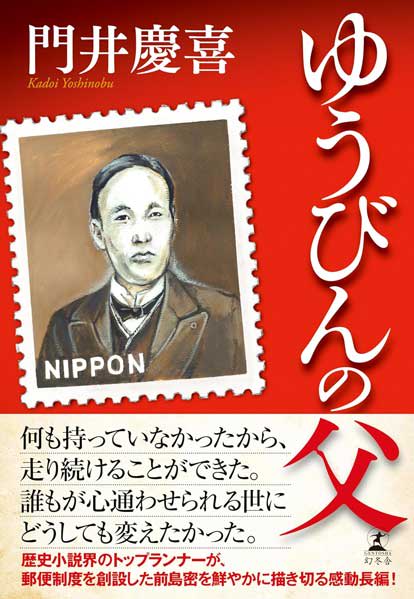
長い「自分探し」が奏功
宛名を書いて切手を貼って投函すれば、確実に相手に届く――郵便制度とは考えてみればとてつもないシステムだ。物流や宅配事業もそうだが、いくらネットが発達しても、物理的な「配達」がなければこの社会は成り立たない。
そのシステムを作り上げたのが、1円切手の肖像でも有名な前島密である。本書はその前島密の幼年時代から、郵便事業が実現するまでを描いた評伝小説だ。
密が明治新政府に登用されたのは明治2年、30歳代半ばである。当時は駅逓と呼ばれていた郵便事業に密が携わることになったのは翌3年。それ以前のことについて私はまったく知識がなかったのだが、本書を読んで驚いた。前島密の前半生ときたら、目まぐるしいにもほどがある!
幼くして父を亡くした密(幼名・上野房吾郎)は広い世間を知りたくて糸魚川の叔父の家で医者をめざすことになる。しかしそれにも満足できず江戸に出て蘭方医、漢方医のもとを渡り歩く。蘭方なら長崎ということで旅に出るが、そこで外国語に触れ、世界を見るなら船だとばかりに函館に航海術を学びに行く。ロシア軍艦対馬占領事件の教訓から英語の重要性を知り、長崎で英語塾を開く。薩摩に招かれて蘭学を教える。幕臣前島家の養子となり、神戸にいるとき戊辰戦争が起きて東帰。駿府に移るが勝海舟の引き合いで明治新政府の改正掛に出仕……。
ちょっと落ち着け、と言いたい。
今いる場所に見切りをつけるのが早い。これだと思ったらすぐに動く。持ち前の行動力で狙った場所に入り、専門家から指導を受け、各所で塾頭を任されるまでになりながらも、また次を探す。つまりは、長すぎる自分探しである。
それがどうして郵便の父に? 面白いのがそこだ。日本各地を渡り歩く中で、親に出した手紙の半分は届いてなかったことを知る。勝海舟ほどの人がわざわざ江戸から長崎まで本を取りに来るのに出くわす。当時の物流の拙さと、それがどんな不利益をもたらすかのエピソードが、本筋とはかかわりなく彼の人生のところどころに顔を出すのである。そうつながるのかと膝を打った。
長い自分探しがここで活きる。飛脚とはまったく異なる郵便事業を立ち上げる様子はプロジェクト小説として実にエキサイティング。同音異義語がないという理由で選んだ「ゆうびん」という言葉の由来や、時間を守るための工夫も面白いし、飛脚の問題点を整理したり外国に学んだりする様子には感心しきり。なるほどゼロからシステムを組み上げるとはこういうことかと唸った。
何より、薩長土肥が幅を利かせていた明治新政府で越後の農民の息子が郵便システムを主導したという事実に注目。後ろ盾やしがらみがないからこそ自由に旅することができたのかもしれない。その旅が、遠隔地を結ぶことの必要性を教えた。情報に取り残される地方の悩みを教えた。
確かにこの時代にあって30年の自分探しは長すぎる。だが旅の経験がことごとく郵便に活かさていくのを見るにつけ、すべてはこのためだったのだと思えるのだ。
目標が見えずに燻っている人に、ぜひ本書をお読みいただきたい。力の湧く評伝小説である。
(門井 慶喜 著、幻冬舎刊、税込2000円)
選者:書評家 大矢 博子
レギュラー選者3人と、月替りのスペシャルゲストが毎週、書籍を1冊紹介します。“学び直し”や“リフレッシュ”にどうぞ。