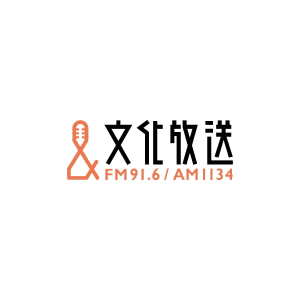ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」(文化放送・月曜日~金曜日15時30分~17時)、5月30日の放送で、20年ぶりのデザイン刷新となる紙幣について日刊スポーツ文化社会部記者の久保勇人が解説した。
鈴木敏夫(文化放送解説委員)「(新紙幣の発行が)7月3日です。およそ1ヶ月後に迫ってきました。千円、5千円、そして1万円札が20年ぶりにデザイン刷新となりました」
長野智子「まず『なぜいま?』という。世の中はキャッシュレス時代に突入しようとしている中で、どういうことなんでしょうか?」
久保勇人「紙幣は日本の場合、国立印刷局というところがつくって、日本銀行が発行しています。日銀や財務省は、なぜ変えるのか、という疑問に対して『いま流通している3種類のお札が、発行してから相応の時間が経っている』と。(前回の刷新から)20年になるわけですね。この間、印刷技術はかなり発達していて、悪いことを考える人の偽造のリスクが高まっていると。それを防止するために、日銀の方々は『偽造抵抗力』を確保していく必要があるので、20年というタイミングで新しいお札を出すことにした、ということです」
長野「理由として納得できますね! 具体的に変更されるのはどういうところですか?」
久保「日本の印刷技術は世界トップクラスなんですけど、その中でも最先端の技術が、いろんなところに盛り込まれています。いちばん大きな変更は肖像ですね。1万円札は渋沢栄一さん、5千円札は津田梅子さん、千円札は細菌学者の北里柴三郎さんに変わります。裏面は1万円札が東京駅、5千円札が藤の花、千円札は北斎の波の浮世絵です」
長野「こういう肖像ってどう決めるんですか?」
久保「肖像を使うのが日本の基本なんですけど、誰を選ぶかというと、やはり国民が世界に誇る日本人として広く認識していることがひとつ。教科書なんかにも取り上げられている、評価が定まっている、ということですね。それから実物と間違えてはいけないので、写真やしっかりした絵画が残っている、そういう人から選んでいるそうです」
長野「そうなんですね!」
久保「もう1個、大きな変更点として、世界初の偽造防止技術として、1万円札と5千円札はこれまで四角いホログラムがついていたんですけど、今度は短冊型のストライプ型のホログラムになります。なぜ世界初かというと、紙幣を傾けると角度によって、1万円札の場合は渋沢栄一さんの顔の角度が変わって見えるんです。そういうのを使うのは世界で初めてということですね」
鈴木「3Dホログラム……」
久保「千円札にはこれまでなかったんですけど、今回の新しいお札にはパッチ型、これまで5千円札や1万円札についていた四角い小さなホログラムがつくことになります。そのほか『10000円』という数字がすごく大きくなったり、様々な変更点があったりします。それは日本銀行さんや国立印刷局さんのホームページで詳しく解説してあるので見てください」
鈴木「(『10000円』の表記を見て)字が大きすぎて本物のお札に見えないぐらいですね」
久保「子供銀行券かな、と一瞬思ってしまうんですね(笑)」
長野「手触りも違うんですか?」
久保「違うんです。いちばん大きな点はユニバーサルデザインといって、いろんな方が等しくお札を使えるようにということで、視覚障害者向けに触ってわかるものであるとか。そういう工夫が今回のお札ではされているそうです」