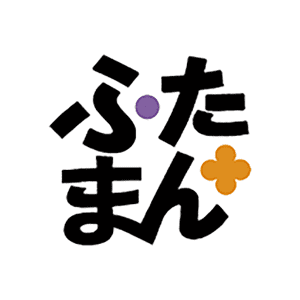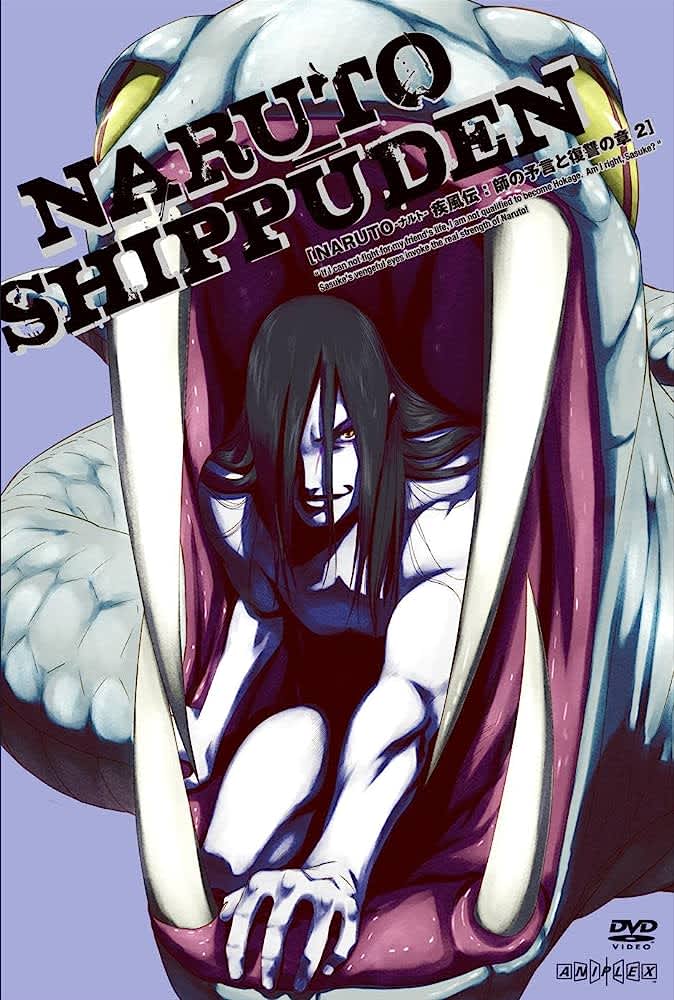
バトル漫画やアニメには数多くの師弟が登場し、多くの場合は良好な関係を築いている。中でも師匠が自分を越えた弟子の成長を喜ぶ流れは王道であり、強敵との戦いに必要な儀式ともいえるだろう。
しかし、そんな王道パターンから外れた師弟関係も存在する。弟子が師匠に特別な感情を抱いておらず、力を得られれば用済み……と考えているようなケースだ。今回は、そんな師匠を踏み台にするような行動をとった弟子を、どんな形で裏切りを見せたのかとともに紹介していきたい。
■『NARUTO-ナルト-』大蛇丸
まずは、岸本斉史氏による『NARUTO-ナルト-』の大蛇丸だ。大蛇丸の師匠は三代目火影の猿飛ヒルゼンで、ナルトの師匠である自来也や五代目火影の綱手の師匠でもある。彼らが後に「伝説の三忍」と呼ばれるようになったのは、ヒルゼンの指導の賜物でもあるのだろう。
そんな大蛇丸たちは戦争を経てそれぞれ別々の道を歩んでいく。大蛇丸は禁術である不老不死の研究に没頭するあまり、人の命を何とも思わなくなってしまった。その結果、上層部からマークされ、ヒルゼンがその始末を命じられる……。その際ヒルゼンは大蛇丸を殺せず逃がしてしまったのだが、その後も大蛇丸は改心するどころか、逆に木ノ葉の里を壊滅させようとした。
恩を仇で返すとはまさにこのことで、大蛇丸は「穢土転生」を使用して初代火影と二代目火影を口寄せし、ヒルゼンにぶつけてきた。尊敬するふたりを自らの手で倒すのは、ヒルゼンにとって辛いことだっただろう。
なぜそこまでして、大蛇丸はヒルゼンを敵対視していたのか? それははっきりとは描かれていないが、大蛇丸はヒルゼンの存在が許せなかったのだろう。見逃されて生き永らえたのも気に食わず、ヒルゼンの愛情が偽善だと思っていたのかもしれない。
いずれにしても大蛇丸は屈折した考えの持ち主なので、ヒルゼンの気持ちを理解できなかった。そんなふたりの決着は、「屍鬼封尽」によってヒルゼンの命と引き換えに大蛇丸が両腕を持っていかれるというものだった……。
■『マッシュル−MASHLE−』イノセント・ゼロ
次は、甲本一氏による『マッシュル−MASHLE−』に登場するイノセント・ゼロだ。イノセント・ゼロは、かつて魔術界の頂点に立つアダム・ジョブズの一番弟子としてウォールバーグとともに名を馳せていた。
しかしウォールバーグが人類の平和のために魔術を使ったのに対し、イノセント・ゼロは自らのためにその力を使い、ふたりは対極の存在として敵対する結果になってしまった。
イノセント・ゼロは自身を高次の存在に導くために、自身の子どもたちすら利用するような外道だ。ウォールバーグはそんな彼の計画を阻止するために戦うことになる。
その際、イノセント・ゼロは自身が蘇らせたアダム・ジョブズを部下のネクロス・マンスに操らせ、ウォールバーグと戦わせた。これは先ほど紹介した『NARUTO』の大蛇丸を連想させるような状況である。イノセント・ゼロはネクロス・マンスを戦わせることで、あえての師弟対決を演出したのだ。死体をまるでおもちゃのように扱う非道なところも、大蛇丸と同じで悪趣味である。
イノセント・ゼロは、ウォールバーグが最も嫌がる方法を取り、心を折ってやるつもりだったのかもしれない。しかし、ウォールバーグはまったく動じず冷静にみずからの魔術で葬り去っていたので、イノセント・ゼロの思惑は外れた。
■『北斗の拳』ラオウ
原作:武論尊氏、作画:原哲夫氏による『北斗の拳』にも命がけの師弟対決がある。それが、リュウケンとラオウとの直接対決だ。ラオウはリュウケンの養子で、北斗4兄弟の長兄として北斗神拳にすべてを捧げてきた。
北斗神拳は一子相伝を掟としており、伝承者が決まった場合それ以外の者は拳を封じなければならない。しかしラオウはその掟を平然と破り、「おれはだれの命令も受けぬ!! たとえ神の命令でもな!!」と主張してその拳で覇権を握ろうとする。
リュウケンはそんなラオウを止めるべく、彼に自らの拳を振るうことになった。その際にはラオウすら習得していない奥義「七星点心」を披露。ラオウは何もできずに攻撃を食らい続けた。
しかしとどめを刺そうとした瞬間、リュウケンは病の発作のせいで動きが止まってしまい、ラオウが逆襲。最終的にリュウケンは命を落としてしまう。こうして親子関係と師弟関係を終わらせる結果になったが、そこに怨恨のような感情は存在しないように思われる。
北斗神拳のような一子相伝の暗殺拳を伝承する際、師弟が命のやりとりをするのはそれほど不思議なことではない。サウザーも南斗鳳凰拳を受け継ぐ際には、師匠のオウガイを殺している。たとえ師弟といえど、時にはお互い命を奪われる覚悟を持つ必要があるということなのだろう……。
師匠を裏切る弟子には共通して、大きな野望がある。そのため、師匠のこともそのための踏み台くらいにしか思っていないのだろう。弟子をとるときにも人を見る目が問われるのかもしれない……。