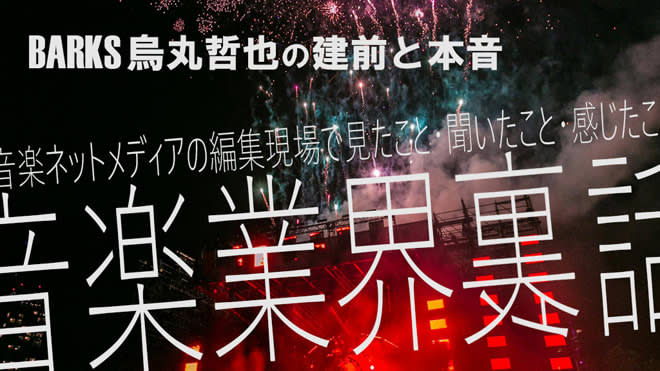
ありがたいことに「イヤホンのレビューはしないんですか?」というお声がけをいただく。「またレビューしてください」「の話を聞きたいです」というお話も未だにいただくことがある。廉価版から高価なハイエンドに至るまで、イヤホン/ヘッドホンのレビューを2011年から6年間ほど続けてきたけれど、ある時に糸が切れたようにレビュー記事を上げなくなった。自分なりに熱量高く、徹底的に聴き込んで丁寧なレビューを心がけてきたけれど、どうしてぱったりとやめたのか。
そもそも何故レビュー記事を上げてきたのかといえば、音楽は少しでもいい音で聴いたほうが楽しいし、受け取る情報量は豊かであればそれだけ感動の振れ幅も高まると思っていたからだ。なにより、いい音は気持ちいい。いい音は楽しい気分にさせてくれるし、その心地よさは快楽そのもの。だからこそ、いい音が楽しめるアイテムはしっかりと情報共有したいと思った。
もともとゴリゴリの理系だったから、音楽=空気振動という物理現象を力学的アプローチで追求するオーディオの文脈は、自分にとってとても明快な領域だった。…のだけど、スペックが突き詰められ微細な要素にメスが入るにつれ、理屈に対して自分の理解がおぼつかなくなっていった。開発費なんて指数関数的に大きくなっていくのだから、ハイエンドとなれば多大な開発費を投じて微細な違いを追求していたりする。そこにこそ商品の価値があるのだけど、聴いてみても「あれ?よく分かんないな」となることがある。「ちょっと時間をおいてみよう」「食事してから改めて聴き込んでみよう」と時間をおいて気分を変えると、初めてその精細な差異が認識できたりもした。まさにそこが問題だった。
「気分転換したら分かった?それってどういうことだ」と。これまでも、体調によって聴こえ方が違うことを知っていながらそこに深入りはせず、物理現象として音質をレビューを続けていた。
音=音楽は脳の知覚現象にすぎないってのに。
いい音を出すハードウエアを探すのではなく、いい音と感じる自分のコンディションを探ったほうが、いい音への近道だと直感した。もはや音楽を出力するイヤホン/ヘッドホンのスペックよりも、受容体である自分の認知・知覚能力に注力しなければ、ハイエンド・オーディオを使う意味がない。もはやボトルネックは人間側にあると疑った。「空腹は最上の調味料」と言われるように、いわば「耳が飢餓状態」になれば音楽はより感動的に響くのではないか。いい音を求めるのであれば、音響工学よりも脳科学や音響心理学からアプローチしたほうが本質に迫れると確信した。
音楽がビビッドに響き、より大きな感動や喜びを感じるのは「脳の報酬系が刺激されている状態」であるという事実を踏まえれば、健全で理想的な音楽リスニングとは何か、そして最高に気持ちいい音楽体験とはどういうことか…と、追求すべき対象はハードウエアからどんどんと遠のいていく。
そこからは「誰もいない森で木が倒れたら音はするのか」といった禅問答のような話に触れ、その先に待っているのは、思いもよらぬ量子力学だ。脳科学とか音響心理学を飛び越えて、モノの摂理を問うような根源的な話に帰着していくことになっていく。
その結果、我々の日常はあくまで「人間という生物の感覚器官によって認識する形で存在しているように見えているだけ」に過ぎなくて、本当は「何でもあり」という圧倒的な事実が見え隠れしてくる。そうなると、オカルトのように揶揄される「プラシーボ効果」なんてものも、「そりゃ、そういうことだってあるだろうよ。むしろ否定する根拠がない」という境地になってしまう。あれだけ「思い込み」といった不確定要素を徹底排除して、冷静で公平に人的ブレを無くしたレビュー記事を心がけてきたというのに、「プラシーボなんてあるに決まっているでしょ。むしろそこいちばん大事よ」なんて心境に帰結してしまったわけだ。もはやシビアなレビュー記事を書く情緒ではない。
「じゃあ、音楽を極上に楽しむにはどうすればいいの?」と問われても、正解は見つかっていない。多分、正解などないというのが真理だと思っている。報酬系ホルモンを自在にコントロールできるはずもなく、それができたらもはや人間でもない。ケミカルで操作したら廃人になる。そういうことだけがはっきりと分かった。
もちろん素晴らしいイヤホン/ヘッドホンは普遍的に素晴らしい。ポリシーを掲げトライ&エラーを基に根拠を示した優れたプロダクトはたくさん存在し、もちろんそれらは素晴らしく気持ち良い音を出力する。それも事実だ。そして多くの人がそれを心地良いと認識するのも、紛れもない真実だ。

ただ、好きな音楽を聴くことで「健やかな気持ち」や「感動」や「喜び」を得ているものと思っていたけど、本当は心の奥に隠された「健やかな気持ち」や「感動」や「喜び」を顕在化させてくれるトリガーとして、音楽が作用しているんだと思っている。逆説的だけど「自分が健やかじゃなければ、そもそも音楽から感動は得られないんだ」「残されている健やかな自分を引っ張り出してくれる、最高のデトックス・アイテムが音楽なんだ」と思ったことが、音質探求を重ねた数年間で得たもののひとつの答だった。
文◎BARKS 烏丸哲也

