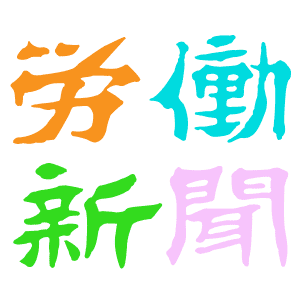狩りの奥に謀略も恋も
顕現である。
少し古風な言い方になるが、印象としてはそうだ。小説にはいろいろあって、人物を描いたり、物語を紡いだり、さまざまな作家がいる。
その中でも、空気や匂いといった、見えないものに雰囲気を出す作家はいる。この作品がまさにそうである。
ただの土くれを盛り上げて人の形にして命を吹き込むのが反魂だが、そういった雰囲気がこれにはある。
本書は、狼の多い奥州で「狼狩」を担当する奉行所の物語である。人間ではなく狼の犯罪に立ち向かうというのがまずはわくわくする。
狼狩奉行が実在したのかは定かではないが、あってもおかしくはない。奥州という土地だけにいかにもありそうだ。
歴史小説でも、狼に焦点をあてたものは少ない。かといって単純に狼狩りの小説ではない。狼狩りという「日常」の奥に、人情もあり、謀略もあり、友情や剣劇、恋愛もあるというなんとも盛沢山な小説だ。
それでいてくどくもない。
このくどくないというのは案外大切である。修練というよりも天性の素質があるからだ。その意味ではこの作者には天性があるのだと思う。
エピソードも文化風俗をきちんと理解して書いている様子がある。あれこれと並べたてるのは簡単なのだが、ネタバレを含んでしまう可能性が高いのであえて触れない。それだけ緻密にできているということだ。
そして「狼狩」の名の通り作中では何度も狼を狩っている。罠を仕掛けてから仕留めるのだが、それも細かい。
狼というのは森の王である。生態系を支配する生き物だ。人間がいなければ鹿や猪の数を管理するのは狼の仕事である。
近年、猪などが増えすぎるのは狼がいないからだ。しかし江戸時代の人間にとっては、狼は飼育している馬を食い荒らす害獣だ。狩らなければならない。
狼に憎しみはない。自然に対する愛もある。また、狼を倒すことを格好良いとも思っていない。
仕事だから殺す。
そこは淡々と描いている。やりすぎない。残酷でもない。うまくバランスをとっているといえるだろう。
動物小説のような緻密さを持ちつつ、それが家中の陰謀につながっていくのは構成力のなせる技だ。そして作中にこまごまと描かれる森や崖の描写が良い。
自然というのは描くのが案外難しいのだが、ちゃんと書いていて、書きすぎていない。そして最後の最後にきちんと余韻を残しつつ、自然で終わるところに読後感の良さがある。
そしてこの小説は品が良い。この品というのは自分でコントロールするのは難しい。体の奥から出るものだからだ。
品が良いため、読んでていやな部分がなく、面白さだけを文字の奥から拾うことができる。絶対にお勧めできる小説である。
同時に、武士という社会から逃れられない運命をきちんと受け止める登場人物たちに、労働者の気持ちをかぶせることもできるのである。
(東 圭一 著、角川春樹事務所 刊、税込1650円)
選者:時代小説家 神楽坂 淳(かぐらざか あつし)
1966年広島県生まれ。『大正野球娘。』でデビュー。主な著作に『うちの旦那が甘ちゃんで』、『金四郎の妻ですが』、など。最新刊は『夫には 殺し屋なのは内緒です 2』(講談社文庫)。8月8日、『包丁源氏物語』(角川春樹事務所)が発売予定。
レギュラー選者3人と、月替りのスペシャルゲストが毎週、書籍を1冊紹介します。“学び直し”や“リフレッシュ”にどうぞ。