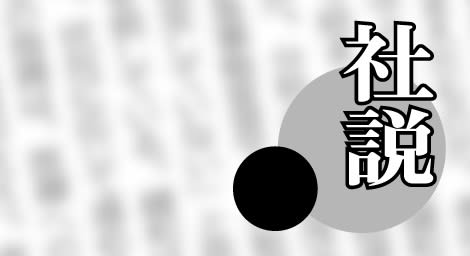
同性婚を認めていない婚姻制度の下で、当事者に寄り添った判断といえよう。
長崎県大村市が男性の同性カップル世帯に対し、住民票の続柄欄で世帯主と同居するパートナーを「夫(未届)」と記した。これは婚姻届を出さない男女の事実婚のカップルに用いる表記だ。同性カップルの場合は「縁故者」「同居人」と記すが、市は当事者の希望を受けて「内縁の夫婦に準ずる」と判断した。
2人は「励みになる」と喜ぶ。行政の書類で認められたと意義を感じ、年金などの手続きで活用したいという。
すぐに男女の事実婚と同じ扱いになるわけではない。市長は住民票の記載について、自治事務として自治体の裁量で判断したとした。一方、権利保護にどのように反映させるかは、行政機関などが個別に判断すると説明する。
それでも市の対応は、停滞した同性婚の議論に風穴をあける大きな一歩である。
同性カップルは暮らしのさまざまな場面で不利益を被っている。パートナーの入院や病状の説明時に病院側から家族だとみてもらえるか、懸念が拭えない。法律婚にある相続や税制上の優遇措置、事実婚でも認められる年金や社会保険の扶養の対象外だ。尊厳の問題も大きい。それだけに、市の判断が「画期的」との声が上がるのは当然だ。
切実に困っている住民を身近に知る自治体だからだろう。社会の実態に合わせた権利保護を少しずつ進めてきた。同性カップルを公的に認めるパートナーシップ制度は2015年、東京都渋谷区と世田谷区が創設した。現在は全国で390を超す自治体が導入し、公営住宅への入居などをサポートしている。
大村市の判断を受け、栃木県鹿沼市が7月から同性カップルにも事実婚で使う続柄表記を選べるようにすると発表した。杉並区と世田谷区も検討する。倉吉市は既に昨年10月に始め、受理の有無は公表していない。政府へのプレッシャーを意識した動きではないか。
司法でも、性的少数者の権利保護を重視した判断が相次ぐ。今年3月に札幌高裁が同性婚を認めない民法の規定は憲法違反と断じたのは、象徴だ。昨年6月には名古屋地裁が、現状を放置していることに対し「立法の裁量を超えている」とも指摘した。犯罪被害者給付金の受給資格や同じ名字への変更を認めるなど、個々の権利を積極的に広げようとの判断が続く。
しかし政府は「憲法上、想定されていない」と従来通りの見解を繰り返す。制度設計に向けた議論は進んでいない。背景には、自民党の保守系議員を中心に「伝統的な家族観が壊される」という、感情的な反対がある。家族の形は多様化し、異なる価値観への理解は進んだ。世論とのずれは大きくなる一方だ。
当たり前の権利を少数者に認めない社会のままで、いいはずがない。不利益を直視し、法整備の議論を速やかに始めるべきだ。もはや社会の要請であり、住民票の表記をきっかけにしたい。

