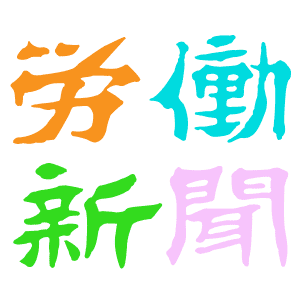関係省庁が集まって今春から議論を進めてきた「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム」が、中間取りまとめを明らかにした(関連記事=男女間賃金格差 解消へ行動計画策定要請 金融など5産業対象 政府プロジェクトチーム)。男女間賃金格差の縮小に向けて、複数の業界へアクションプラン策定を要請する方向性を示している。対象になる5産業の人事部門にとっては、ただでさえ悩ましい課題にさらに注文が付く…ことになるのかも知れない。
現状で30~40%にも及んでいる賃金格差が、1年や2年で埋まらないのは実務家でなくとも理解できる。最大の要因は担っている職務・ポストの違いにあるはずで、一息での解消など望むべくもない。個別企業というより社会全体の対応として、結婚・出産・育児というイベントを経ても男女差が生じない環境を整え、継続的に高位のポジションをうかがう女性を増やしていくことが求められよう。これまでの努力と同様に。
理想を実現するためには、既存のリーダー像を見つめ直すことも欠かせない。たとえば、部門ごとにあらかじめ“3年後の女性管理職数”を設定して育成に取り組んでいる大東建託㈱では、候補者に対して支援型のリーダーシップの有効性を説くケースも多いという。
同社では従来、管理職が先頭に立って部下たちを引っ張る権威型のリーダーシップが当たり前だった。自身も10年にわたって係長職を務めた経験を持つ女性部長は、「ああいう風にはできないし、女性としてなりたくない」と女性社員たちの本音を代弁する。翻って今の若手が“権威型”を求めているはずもなく、指導よりサポートを主体としたマネジメントもある、と伝えているそうだ。
政府のプロジェクトチームでは、女性の働き方の違いによる「生涯可処分所得」の試算も行っている。夫婦とも正社員で働き続けた世帯では4.92億円になるのに対し、妻が出産時に離職し、そのまま再就職しなかった世帯は3.25億円に留まるという。どうせなら、夫婦それぞれについて課長まで昇進した場合、部長まで昇進した場合の試算なども知りたいと思うのは、欲張りなのだろうか。