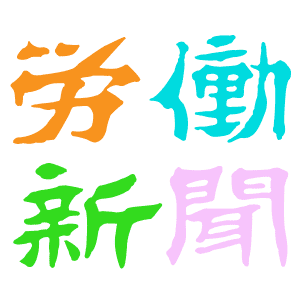最近、私の仕事で多くなっているのが、職場巡視、安全衛生教育や労働安全衛生法に基づく労働災害防止に関する業務である。社会保険労務士の業務としては少し異質であるかもしれない。しかし、労働安全衛生にかかわる業務は、究極の労働条件に関するものであると思っている。賃金や労働時間も大切であるが、生きていくために働いているのに、働くことで死んだり怪我をしたりしたら本末転倒である。
福岡県社会保険労務士会のホームページには「社会保険労務士は労働基準法・労働安全衛生法に定められた規定に加えて、労働時間や労務管理・労働環境・社員教育といった、あらゆる『ヒト』に関する面から会社を支え、労働災害ゼロを目標に、快適な職場環境を整えるお手伝いをいたします」と書かれているが、これらの後半部分の実践である。
職場巡視などで有意義な点は、そこで働く人たちの生の声を聞けることである。
「この職場で危険な箇所はないですか」と問いかければ、「通路に資材が置かれたままでつまずいた」、「脚立で落ちそうになった」などいろいろな話を聞くことができる。それらの生の声から、労働者が働くうえでのリスクを軽減させ、安心して働けるように職場環境の整備につなげられるのである。
そもそも、社労士の業務は社労士法第2条で、労働および社会保険に関する法令に基づいての申請書や届出書の手続き代行、帳簿書類等の作成および労務管理や労働相談などと定められている。それらの法令のなかには当然、安衛法が含まれている。
しかし、安全衛生に関する業務を苦手としている社労士が多い。先日も知り合いの社労士から「労働安全衛生関係のことは苦手なので、お願いできますか」と安全衛生関係の仕事を紹介された。社労士試験の科目を定めた同法第9条では、その1号に「労働基準法及び労働安全衛生法」を掲げている。折角、安衛法を勉強したのにもったいないことである。
安衛法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を整えるための法律であり、近年、注目されているのが化学物質対策や健康管理である。また、ハラスメント対策、過重労働対策、メンタルヘルス対策などは、いろいろな場所で説明を求められるのではないだろうか。
今後、DXの影響として社労士業務のIT化が図られ、変化が求められていくなか、労働者が安全安心に働けるように労働安全衛生に関する業務にも目を向ける必要があると思う。
グッジョブ社労士事務所 合田 弘孝【香川】