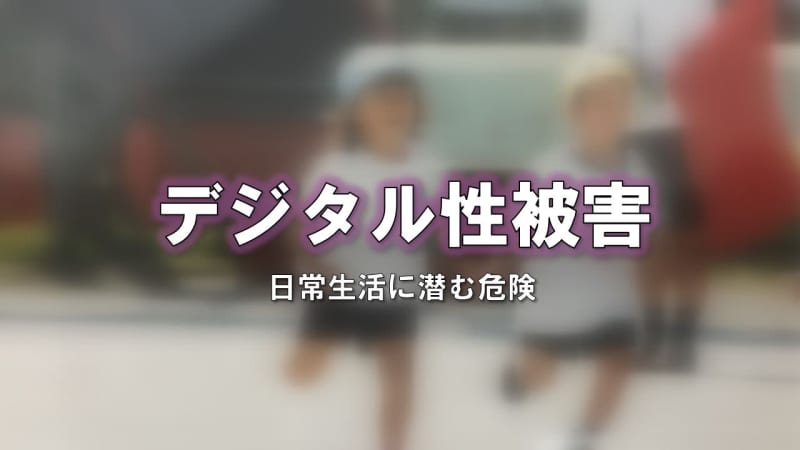
こども家庭庁と文部科学省が全国の保育園や幼稚園などに対し、ホームページなどに、子どもの性的な部位を含む画像を掲載しないよう、またそうした画像が残っている場合には削除をするよう呼びかける通知を出しました。
背景には、第三者により画像が性的な目的で使用されている実態があります。日常生活にも危険が潜んでいる「デジタル性被害」の問題、どんなことに気を付ければいいのでしょうか。
▽こども家庭庁と文部科学省が注意喚起
5月7日に出された通知では、施設のホームページにこどもの画像等を掲載するにあたっては、こどもの権利を守る観点から、十分な配慮が必要であり、性的な部位(性器・肛門・これらの周辺部、臀部又は胸部)を含む画像等が掲載されるようなことは、あってはならないことだと指摘しています。
そして、各保育所等において改めてホームページ等を確認し、そうした画像等が残っている場合には、至急削除すること。
不特定・多数の人が閲覧可能な状態にしないことはもとより、その保育所等のこどもの保護者に閲覧できる者が限定される場合等を含め、不適切な使用がなされないようにすることなどが呼び掛けられています。
チャイルドリテラシー協会 今西洋介 代表理事(小児科医・新生児科医)
「そういう画像のコレクターがいるといいますか、画像が保存されたり、掲示板に貼り付けられたりとかして、小児性愛者やそういう人たちのグループの中で、被害があったということがこども家庭庁の調査で分かったんです。
多分、保育園側からすると悪気がなかったりする。
「水遊びしたよ」「プール楽しかったよ」という毎日の写真をあげているだけなんですけど、小児性愛者から見ると格好の餌食となって、それがデジタル性被害に繋がってしまう。二次的な性被害発生に加担することになってしまうので、それやめましょうということですね」
こうした動きを受け、ホームページが不特定多数の人が見られる状態ではなく、アクセスキーが無いとページにアクセスできないような仕組みを導入している保育園等も多いといいます。
チャイルドリテラシー協会 今西洋介 代表理事(小児科医・新生児科医)
「いわば、これまでは無法地帯だったわけです。画像も、子どもの人権といいますか、子どもの許可を得て掲載してるわけじゃない。やはり、一度ネットに流れた画像はなかなか完全消去できない。子どもたちの将来にも影響を及ぼしますから、子どもの人権を守るという意味でも良い動きかなと思います」
▽実際どんな被害が発生している?
「セーファーインターネット協会」に話を聞きました。
セーファーインターネット協会は、インターネットユーザーが、ネット上の違法有害情報を見つけた際に通報するホットラインです。
協会によりますと、2023年に把握した「違法・有害情報」約1万1800件のうち、半数以上にあたる58%が「児童ポルノ」(※実在する18歳未満の子どもの画像)で、保育園や幼稚園などに通うような小さな児童と思われる、水遊びやトイレトレーニングなどの画像が散見されるということです。
協会では、提供を受けた情報は、ガイドラインに照らして分類を行い、違法な情報や有害な情報と判断した場合、該当する情報が掲載された国内、海外のサイト運営者などに対して、迅速な削除措置を要請する対応をとっています。
▽小児科医と考える「日常生活にも潜む危険」…対策は?
保育園等のホームページだけでなく、子どもたちの写真が悪用される可能性は日常生活の身近なところにも潜んでいます。それは、公園などでの盗撮被害です。
チャイルドリテラシー協会 今西洋介 代表理事(小児科医・新生児科医)
「例えばプールや海、公園のジャブジャブ広場など水遊びができる場所で、子どもを狙って、全然親じゃない人が写真を撮っていたりする。不自然な一眼レフで撮ったりとか、そういった被害も実際あります。親として、まさかと思っている所で盗撮されたりするので、なるべく着替えなど配慮していただきたいと思います。
ただ、最近は『撮影禁止』と大きい看板が設置されていたり、社会全体での意識も変わってきています。
最終的には、子どもの権利を守るっていうことですから、子どもの許可を得てないのに子どもの体をさらすことは、性教育の観点からもよくないので、社会全体で問題意識をもっていただければと思います」

