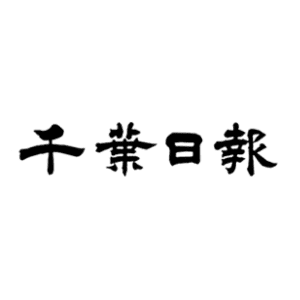浦安市伝統の「浦安三社例大祭」は15日、みこしの渡御が始まった。もともと4年に一度開かれていたが、新型コロナ禍により前回は中止となっていたため8年ぶりの開催。朝から晩まで大小約80基のみこしが旧市街地の元町に繰り出し、「マエダ、マエダ」の独特の掛け声で町を練り歩いた。浦安が漁師町だったことを今に伝える伝統文化。街は祭り気分一色となり、大勢の見物客も押し寄せた。
三社例大祭は清瀧(同市堀江)、豊受(同猫実)、稲荷(同当代島)の三つの神社の合同祭で、埋め立て前からの市域である東京メトロ東西線・浦安駅周辺の元町地区が舞台。大正時代末期の約100年前から同日開催となり今に至る。
3神社の宮みこしや各町内会の小みこしを担いで地区ごとに練り歩く。かつては「暴れ祭り」とも呼ばれ10年以上中断した歴史も。現在は各地域のみこしが交わらないよう渡御ルートが決められている。
4年前の2020年、3神社の宮司を務める黒川彰吾さん(40)は同年1月の先代宮司の急逝に伴い急きょ後任に就任し、祭りの準備に奔走したが、コロナ禍により中止となった当時の苦渋を今も覚えている。
氏子を代表する総代長が亡くなったり、総代の退任が相次いだりと支え手の苦労も経て、ようやく復活した三社祭。「自分も宮司として初の祭り。今後も続けられるよう担ぎ手のマナーなど基本ルールの徹底を神社ごとに申し合わせた」という。
15日は、午前9時に三つの神社から宮みこしが出発。軽快な祭り囃子に合わせ法被に足袋、はちまき姿の担ぎ手たちが神社ごとの渡御ルートを巡る。みこしを高く持ち上げたり、地面すれすれまで下ろして回転させて上に放り上げたりする派手な見せ場も披露され、観客から歓声が湧き起こった。
豊受神社の山崎常雄総代長(80)は「担いだ経験のない若い世代も多い。どんどん参加して祭りの味を覚えてもらいたい。新しく来た人にも浦安の古くからの祭りの文化を知ってほしい」と期待する。
祭りは16日までで、各神社に宮みこしが戻る夕方から夜にかけての「宮入り」で熱気は最高潮に達する。