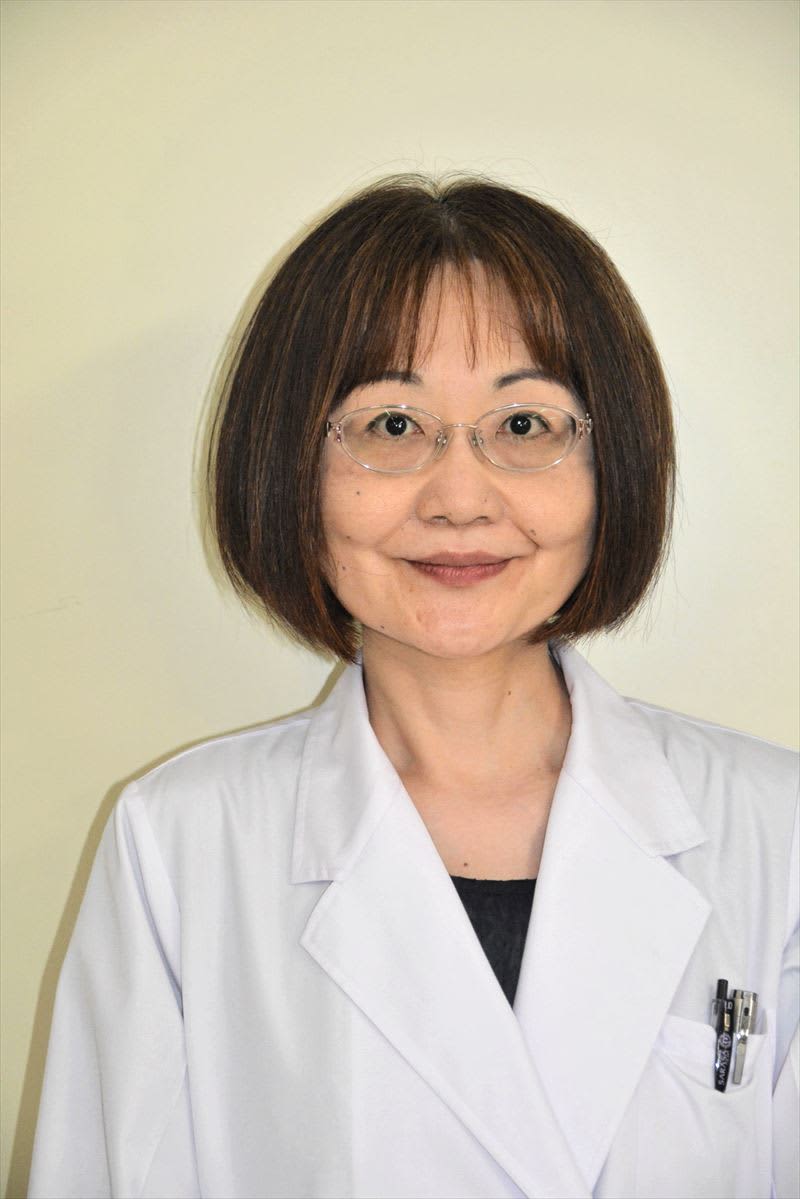
奥羽大歯学部口腔(くう)感染免疫学分野の玉井利代子教授(52)らの研究グループは、骨粗しょう症の治療薬が顎の骨髄炎を引き起こす仕組みを解明した。玉井教授は「高齢者をはじめ治療薬の服用が必要な人は特に口腔ケアによる感染予防が重要」としている。
骨粗しょう症の治療薬は種類にかかわらず服用すると骨髄炎を発症しやすい傾向にあるという。特に高齢者に多い症状で、食事や会話の障害にもなり得る。
研究は安価で一般的に普及しているビスホスホネート系治療薬「アレンドロネート」を使用した。治療薬を投与すると白血球が持つタンパク質「MyD88」が増えた。このタンパク質が炎症反応を促進する分子を生み出し、口内の細菌感染による顎の骨髄炎を悪化させると結論付けた。
玉井教授らは15年ほど前から、骨粗しょう症と顎の骨髄炎の関連性を研究してきた。成果は今月、口腔科学の国際的な学術雑誌に掲載された。

