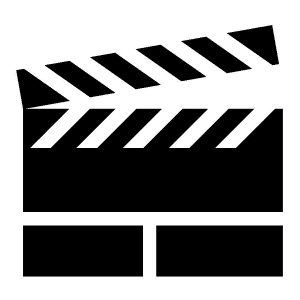作家・佐藤愛子の同名ベストセラーエッセイ集の映画化作「九十歳。何がめでたい」(公開中)から、新たな場面写真が公開された。場面写真では、真剣に執筆に打ち込む姿や、担当編集者の吉川を振り回したり、子犬を抱えて母性あふれるまなざしを注いだりと、草笛光子が演じた愛子のさまざまな表情が切り取られている。


草笛が演じた本作の原作者である佐藤愛子は、現在100歳。昨年には自身の幼少期をつづった最新刊「思い出の屑籠」を出版したほか、今年5月に発売になった「増補版 九十八歳。戦いやまず日は暮れず」では、100歳の心境を問われ「今はもう、消えかけた提灯下げて夜道を行く(笑)」と語るなど、いまなおユーモアたっぷりな姿を見せている。
そんな佐藤は、1923年に大衆小説の大家である佐藤紅緑の娘として生まれ、父の影響もあって幼少期から小説に慣れ親しむ生活を送った。戦時中には長女を出産し、1950年に処女作「青い果実」を発表。その後、夫との死別と2度目の結婚を経て、1960年には次女の響子が生まれる。60年代には「ソクラテスの妻」「二人の女」(63)で芥川賞候補に、「加納大尉夫人」(64)で直木賞候補に選出され、ついに「戦いすんで日が暮れて」(69)で直木賞を受賞。一方で、再婚した夫が破産したことにより離婚、多額の負債を背負うことになるが、その借金を返済するために出演したテレビ番組や講演で当時の世相を厳しく批判する姿が評判を呼び、エッセイの執筆依頼が増えていくようになった。その後も、女手一つで娘を育てながら数々の小説、エッセイを書き続け、今日までに「幸福の絵」(79)で女流文学賞、「血脈」(2000)で菊池寛賞、「晩鐘」(15)で紫式部文学賞を受賞し、2016年には本作の原作である「九十歳。何がめでたい」を刊行、翌年には旭日小綬章を受章している。
本作では、そんな波乱万丈な愛子の人生を、断筆宣言をした90歳の頃に再び筆を取り「九十歳。何がめでたい」がベストセラーとなるまでを軸としながら振り返っている。佐藤は「九十歳を過ぎ、『晩鐘』という小説を書いた後は、もう私の胸の中にあるものを総ざらえで出し切ったと思って、毎日ぼんやり過ごしていたんですが、そんな時に女性セブンから連載エッセイの依頼がありました。特に新しいことを考えて書いたわけでも、何か特別な思いを込めたものでもなく、相も変わらず憎まれ口を叩くという、そんな気分でしたかね。私はいつも自然体を心がけているだけです。そんな『九十歳。何がめでたい』を原作にして、どんな妙ちくりんな作品が出来上がるのやらと楽しみにしています」と、佐藤らしい言葉で期待を寄せている。
愛子役を演じる草笛光子は、撮影前に本人と会食の機会があったという。「お食事の最後に、「貴方が私を演じるのも、悪くないわね」とおっしゃってくださいました。ホッとしながらも責任の重さを感じ、身が引き締まる思いでした。とはいえこの年になったら、気取っても飾っても仕方ありません。言いにくいことを歯に衣着せずズバッと言う原作そのままに、気負わず演じることにしました」と、当時の心境を振り返っている。

「九十歳。何がめでたい」の主演を務めるのは、昨年90歳を迎えた草笛光子。“世の中を痛快に一刀両断する90歳の作家”に挑む。物語は、数々の文学賞を受賞してきた佐藤愛子が、作家生活を引退して来客もなくなり、鬱々と過ごしていたところに、冴えない中年の編集者・橘高がエッセイの依頼を持ち込むところから始まる。ヤケクソで始めた連載は、「いちいちうるせえ︕」と世の中への怒りを赤裸々に書いた内容が意図せず大反響を呼び、愛子の人生は90歳にして大きく変わっていくのだが・・・という内容となっている。
【作品情報】
九十歳。何がめでたい
2024年6月21日(金)より全国公開中
配給:松竹
©2024『九十歳。何がめでたい』製作委員会 ©佐藤愛子/小学館