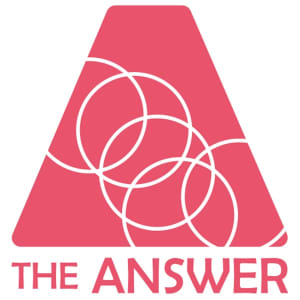リーグワン初優勝の東芝ブレイブルーパス東京・薫田真広GMインタビュー後編
14シーズンぶりの王座奪還に成功した東芝ブレイブルーパス東京。現場から、チームをサポートする側に回った薫田真広GM(ゼネラルマネジャー)は、優勝までの躍進をどう支えてきたのか。インタビュー後編では、社員という境遇の日本選手の意識改革を促し、トッド・ブラックアダーHCを“勝つ指揮官”に変えたチーム変革、そして王者としてのこれからの挑戦を聞いた。(取材・文=吉田 宏)
◇ ◇ ◇
GMの仕事として、モウンガ、フリゼルというビッグネームを開幕戦からフルコンディションで投入出来たことが、結果的にチームの快進撃を大きく後押しした。その一方で、彼らレジェンド以外の、とりわけ日本人の社員選手の意識改革も、優勝するためには欠かせないポイントだった。
薫田GMの仕事ぶりを紹介する前に、あらためてリーグワンと参入チームの運営形態とGMの役割に簡単に触れておこう。
リーグワンは、2003年から18シーズン続いたトップリーグを発展的に解消して2022年に誕生した全国リーグだ。旧リーグを敢えて刷新した大きな理由の1つは、将来的なプロ化を見据えながら、チームに従来の企業スポーツ以上の事業化を求めていることだ。具体的には、チケット販売も含めた試合の開催権、ホストエリアでの普及活動などが参入チームに義務付けられている。親会社への依存を減らすことで、企業側の都合や経営状況などでチームに廃部や活動縮小など深刻な影響が及ぶのを軽減しようという思惑がある。言い換えれば、どっぷりと企業に依存する体質からの脱皮こそがリーグワン設立の意義だ。
だが実情を見ると、23-24年シーズンにディビジョン1に所属した12チームの中で、事業会社化していたのはBL東京、静岡BRの2チームのみ。埼玉WKのような母体企業の関連会社の傘下で運営されているチームもあるが、その大半は、いまだにトップリーグ時代までの形態に近い親会社の一部門や「ラグビー部」という位置づけだ。リーグ首脳も母体企業の大きな支援が欠かせないことは認めているのが現状だ。
チームをいち早く事業会社へ転換させたBL東京だが、会社の経営・運営を統括する社長と共に、強化エリア中心にチーム管理して、選手の補強・獲得、環境の整備などを担うのがGMの仕事だ。薫田GMは、現役時代からの数々の酒席での“伝説”でも知られる親分肌のリーダーとして、常にチームの強化に尽力してきた。いまもBL東京の“ラスボス”的な存在は変わらないが、豪快、剛腕と同時に繊細さも持ち合わせているリーダーだ。
監督時代に、本人からこんな話を聞いたことがある。「外国人選手でも、午前中はグラウンドを使わせず、極力ジムワークなど屋内でのトレーニングをさせている」。プロである外国人選手がどんな時間にグラウンドを使っても構わないはずだが、まだまだ企業スポーツという環境に浸かっていた時代だ。東芝府中工場で働く大半の社員が出勤して働き始めた朝から、外国人だとしてもラグビー部のメンバーが“遊んでいる”というネガティブな声も必ずあることに配慮してのことだった。試合明けの月曜日は、休暇を取っていても、どんなに疲れ、痛みがあっても職場に行って、試合の報告、そして応援への感謝を伝えることも選手に科した。
そんな繊細さは、GMとしての仕事にも発揮している。
「チーム強化を1、2、3とフェーズで区切りながらやっています。ここまでフェーズ1として私自身が力を注いできたのは、チームの練習強度を上げていくことと、選手の競争する意識をどう高めていくかです。そういう意味では、やはり成果主義、つまり結果を出した選手に対してしっかり評価をする仕組みを作ることが、すごく重要だと思っています。それを数年かけてやってきた」

断行した意識改革「悪い言い方をすると、社員選手は傷の舐め合いをしている」
GMも認めるモウンガの加入が、BL東京を「勝つチーム」に変貌させたのは間違いない。だが、この司令塔が動かす“駒”がしっかり機能しなければ、優勝まで辿り着けたかは分からない。決勝戦で優勝を決めるトライをマークしたCTB森勇登は、ほぼ全ての試合でメンバー入りしながら、その半数以上はベンチスタート。しかし、チーム関係者から「出れば必ず何かやってくれる」と評価されるように、攻守に好判断のプレーをみせ、出場時間が限られる中でチーム2位の8トライをたたき出している。
モウンガの加入で、SOからほぼ経験のなかったFBに定着した松永拓朗、激しいフィジカルとスピードで魅せたWTB桑山淳生、そしてBK級のスピードが武器のFL佐々木剛らも、森と同様に入団4年目以内の若手選手。チーム、母体企業が苦境の中で、府中にやって来た。この若手の成長の背景にあるのが、選手の意識改革に他ならない。チームを現状よりもさらにワンステージ高いレベルに上げるためには避けて通れない挑戦だ。たとえ社員選手だとしても、どこまでプロ選手と同等の向上心、意識の高さを持って自分を進化させていけるか。そんなマインドセットの向上にGMという立場で力を注いできた。
「悪い言い方をすると、社員選手は傷の舐め合いをしているということです。『いつまで経っても、良い人だけど勝てないね』という選手像が出来上がる中で、どうやってそれを変えていけるかが重要だった」
薫田GMらしい、すこし厳しめの説明だが、プロ化とアマチュアという2つのフィールドの間に横たわる大きな溝については、日本ラグビーの課題と捉える指導者は少なくない。エディー・ジョーンズHCも、2015年までの日本代表時代に厳しく指摘していたこの国の弱点が、社員選手がラグビーに向き合わなくてはいけない時に「社業」に逃げ場を作っていたことだった。プロかアマかという是非論ではなく、プロ化が加速する世界のラグビーの中で勝ち抜くためには、プロと同等かそれ以上の強化が、個々の選手の成長に必要なのは当たり前だ。
社員選手ばかりの時代に現役だった薫田GMだが、日本代表の主力として世界に挑み続け、指導者としても国際クラスの強化、コーチング、チーム運営を学ぶ中で、日本選手のラグビーに取り組む姿勢には足りないものがあることをしっかりと認識している。
選手がラグビーに取り組む姿勢を、以前ならコーチやスタッフが口やかましく“説教”していたのがトップリーグ時代までの日本の姿だった。だが、リーグワンという新しい時代を迎える中で、薫田GMはその「姿勢」やグラウンド内外での貢献度を数値化して、チーム運営、強化に取り込んでいる。
「まだ完璧なものじゃないですけど、2020年のシーズン後にGMに就いてから、選手評価については私が担ってきた。いまもシーズンが終わり、選手1人ひとりの成果を数値化しているところです。リーグワン公式戦は勿論ですけれど、練習試合の全てのスタッツも数値化、順位化して、出場回数、プレー時間、HCの毎試合の主観的な評価などもポイント化しています。後はグラウンド内外の事業貢献ですけれど、これも全てポイントに換算します。選手評価は当然どのチームもしていますが、ウチの場合は7月の賞与で反映させることになります。これは社員に対してのやり方ですが、プロ選手にも反映されます。数値化をすることで、選手のマインドを変える事って、すごく大事かなと考えています」
チームとしての活動の中で、選手の取り組みを全て数値化した、いわば“薫田エンマ帳”がGMのパソコンの中に蓄積されている。修正を加えながらも制度を導入して3シーズン。選手もこのようなシステムで自分たちが評価され、成果や課題をしっかりと認識する中で、ラグビー選手としての成長を積み上げてきた。このような“エンマ帳”で鍛えられ、昨季のチーム躍進の中で輝いたのが、先に挙げた入社4年目前後の若手たちだ。選手に求められること、評価を可視化することで、ラグビーに取り組む姿勢が明らかに変わったことが、今季の優勝の隠れた原動力なのかも知れない。
ブラックアダーHCに求めたのは「勝つこと」にこだわる姿勢
14シーズンぶりの優勝には、チームを5シーズンに渡り強化を進めてきたトッド・ブラックアダーHCの存在は欠かせなかった。NZ代表主将、そしてクルセイダーズの黄金時代を率いたカリスマリーダーを、薫田GMはこう評価する。
「トッドが突出しているのは、人を信じること。うまくコーチングチームを回し、俯瞰した立場で、個々に役割を与えてきたことが機能したと思う。新しいディフェンスコーチのタイ・リーバらの良さを引き出したのもトッドの手腕。選手に対しても、しっかりと話を聞くタイプ。対話を重んじて、哲学的に話をするのも良さですが、そこをラグビーのプレー面でそれぞれのコーチが埋めていく。そういう関係性を上手く機能させていた」
ブラックアダー・薫田コンビの信頼関係は厚いが、この指導者に全てを放り投げて強化を任せたわけではなかった。
「哲学者タイプの指導者の特徴ですが、0とか100とかをはっきり言わない。良く言えば各リーダーに任せ、俯瞰してみることに良さがある一方で、日本のチームで、そのやり方だけでどこまで選手たちに響くのかという話は何回もしてきました」
GM自身が監督として勝つチームを率いた経験も踏まえて、ブラックアダーHCのチームへのアプローチが、果たして日本でも適切なのかという疑問があった。個々が高い経験値、スキルを持ったNZやイングランドならオーケーかも知れない。だが、日本でどこまでブラックアダー流で勝つチームになれるのか――そんな疑問を常にHCにぶつけながら、強化が進んだ。
「実は、今までのトッドのキャリアをみると、HCとしては一度も優勝してない。トッドを見ていて感じたのは、いわゆる最後の最後で勝つ時の勝負師という部分をおそらく失っているのかなということです。ただしウイニングカルチャーというのは、オールブラックスやクルセイダーズのキャプテンで、わかっているはずなんです。それをなぜHCとして出せないのかと、ずっと思っていたんです」
GMとして現場に求めたのは、「勝つこと」にこだわる姿勢だった。
「22-23年シーズンの前のことです。トッドはミーティングとかでも、選手に優勝しようとかチャンピオンになれとは言わないんです。その代わり、我々は日本で一番優れたチームになろうと話していた。だから、そんな事を話しても、日本人には響かない。だから、チャンピオンを目指すという意思を選手に伝えるべきだと話したんです。その後のミーティングから、トッドもチャンピオンという言葉をバンバン使っていた。それからですね、チーム全体が具体的に優勝をターゲットとして見据えたのは」
選手に明確な目標を提示すること、勝ちたいという思いをしっかりと伝えることがいかに大切か。これは日本のラグビー界で成功体験を持つ薫田GMだから出来た助言であり、チームに正しい方向性を持たせたのだろう。同時に、GMとして昨季はコーチ陣に明確に伝えたメッセージもあった。
「選手の成長と、勝負できるという感触は 首脳陣の中に昨季は絶対あったんですよ。 後は、ずっと トッドにプレッシャーをかけたのは、2023-24年のシーズンにオーナーに対して、ファンに対して、いわゆるステークホルダーに対して、自分たちの存在意義を示さなきゃいけないということでした。トッドたちが思ってる以上に示さなきゃいけないんだとね。勝負師として我々は今年勝負する、何が何でも勝つということです。そういうものは選手の前では言わないですけど、トッドにはすごく話しましたよ。お前は優勝して男になるしかないんだとね」
自分自身の経験値、それに裏打ちされた信念を、相手がどんな経験値があるか、ないのかに関係なく、しっかりとぶつけることが出来るのが、このGMならではの資質だろう。GMという立場で考えれば、やるべき事は明白だった。グラウンドの外を見れば、東芝グループとしての苦境は続いている。東京SGとのプレーオフ準決勝3日前の5月16日には、東芝本社が最大4000人の従業員削減を発表。本社機能も東京・港区から神奈川・川崎市に移行する。昨年末の非上場化に続き、再建への模索が続いている。この状況の中で、チームがどんな貢献を出来るのか。GMの中での答えは明確だったはずだ。
「決して予算が減っているわけではないし、大幅に増えたということもない。身の丈に合った中での強化で、なおかつ結果を残すことが全てだと思ってやってきました。こういう状況で、我々にオーナーが投資をしている意義というのをしっかりと認識して戦う必要はありましたね。問われていたのは、新生東芝の強いシンボルとしての存在意義です。だからチーム内では『強さを示そう』と話してきました。強さというのは勝つだけじゃなくて、逆境を跳ね除ける力をグランド上のパフォーマンスで示すことです。その結果として、優勝しなきゃいけなかったんです」
そんなチームとして背負うミッションを、海外からやって来たプロコーチ、選手にもしっかりと伝え、逆境の中で戦い、勝利を掴んだBL東京のストーリーは、大スポンサーである母体企業にとっても最高の“リターン”になったはずだ。
薫田GMが見据える、優勝したBL東京の「これから」
最後に、優勝がチームにもたらすもの、そして「これから」のGMとしての取り組みについて聞いた。
「まず日本のラグビー、リーグワンという観点で見ると、3シーズンで違うチームが優勝したことは価値があると思います。我々のチームにもたらされたのは、色々な意味での可能性が広がったことでしょうね。そういう意味では、今まで長く経験できなかったことが 戦略的に仕掛けられるというのは非常に大きい。後は事業面での反響の大きさですね。ここは、リーグワンが立ち上がる前と今とでは圧倒的に違う」
事業面ではチームに大幅な変化が起きている。母体企業からの数字を除いた昨季のスポンサー、チケット、グッズなどの事業売上げ6億2400万円は、前シーズン比153%増。平均観客数も1万人を超えた(168%増)。ファンクラブ加入者1万2564人は200%近い上昇をみせた。これらの数字に、「優勝」という追い風を加えると、オフシーズンから営業、事業面でも大きなチャレンジが待ち受けている。
秩父宮、味の素スタジアムという従来のホストスタジアムに加えて、長らく合宿地として拠点化している鹿児島、そしてチームのアイコンでもあるリーチマイケルの“第2の故郷”北海道での試合開催なども戦略的な構想として浮上する。「王者」という肩書が使える今オフ、そして新シーズンだからこそ打つべき手は少なくない。そして、GMとして「連覇」という大きな挑戦にも思いを馳せる。
「これまでと同じなんですけど、プレーオフに残る残るために何が必要かということを考えていくことです。来季は6枠になるプレーオフを戦える主力30人をどう揃えるかが一番大事なことです。ここには代表に何人引っ張られるかも影響してくる」
若手の成長には触れたが、どのチームも遂げたことがない連覇のためには、さらなる選手層のクオリティーアップは不可避なことだ。昨季のS東京ベイ同様に、相手のマークも当然厳しくなる中で、再び常勝軍団という時代を築くことが出来るのか。チームは祝勝行事を経てオフシーズンを迎えようとする中で、敏腕GMにオフはなさそうだ。
吉田 宏 / Hiroshi Yoshida