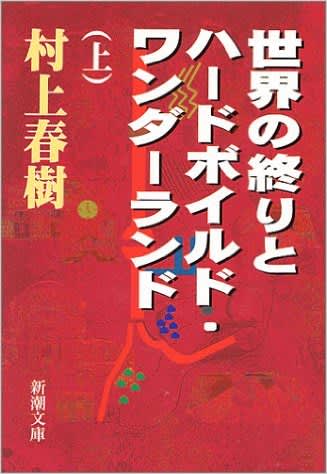
3月20日の夕刻、宮城県沖を震源とするM6.9、最大震度5強の地震がありました。先月、2月13日夜にもM7.3、最大震度6強を観測した地震があり、そのことから前回のコラムを書き出しました。ほんとうに地震が多いですね。
その回も「地震」と「村上春樹作品」というテーマで書きましたが、今回もそれに続いて、「地震と村上春樹作品 その2」です。
☆
今月で東日本大震災(2011年3月11日)からまる10年が経ちました。村上春樹作品で「地震」の出てくるものは少なくないです。その「地震」への村上春樹の関心は、随分前の作品まで遡ることができます。
前回は『ノルウェイの森』(1987年)に登場する関東大震災についてのことなども紹介しました。同作に出てくる「緑」という女性が、小学校3年の時と5年の時に家出をして、福島の伯母の家に行くのですが、それを迎えに来た父親が、東京に帰るまでの電車の中で話してくれた関東大震災の体験についてでした。
「地震」をめぐる話は『ノルウェイの森』の1つ前の長編『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(1985年)にも出てきます。
『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は、私(小山)が最初に村上春樹にインタビューした作品でもあり(同じ作品で2度インタビューしました)、とても印象深い物語です。その<『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』が村上春樹作品では一番好き>という読者と話しても、「地震」と『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』というと……?との読者が多いのですが、でもとても重要な場所に出てきます。村上春樹作品全体を考えていくうえでも重要な意味を持っていると思います。
☆
『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は「世界の終り」の話と「ハードボイルド・ワンダーランド」の話が交互に展開していく物語です。その「ハードボイルド・ワンダーランド」の方に「地震」について、こんな会話が書かれています。
「私」と博士の「太った孫娘」の2人が地底の闇の中を進んでいくと、何か音が聞こえてくるのです。太った娘が「何か音が聞こえるわ。耳を澄ませて!」と言います。
暗闇の奥からの響きに耳を澄ませると、それは「かすかな地鳴りのようでもあり、何かどっしりとした重い金属がこすりあわされる音のよう」でもあります。「大きな虫がじわじわと背中をはいあがってくるような、不気味で冷ややかな感触のする音だった。人の耳の可聴範囲にやっと触れるほどの低い音の響きだ」と記されています。
何かが起りつつあるという予感のようなものがあたりに充ちる中、「私」が「地震でも起るのかな」と言うと、「地震なんかじゃないわ」「地震よりずっとひどいものよ」と「太った娘」が言うのです。
同作の21章は、この「『地震なんかじゃないわ』と太った娘が言った。『地震よりずっとひどいものよ』」という言葉で終わっています。『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は、単行本では1冊本ですが、文庫版は上下2分冊となっています。そして、太った娘が言ったことは文庫版上巻の終わりの言葉でもあります。
☆
この会話の中の「地震」が単なるレトリックでないことは、下巻の「ハードボイルド・ワンダーランド」の話の最初の言葉が「『地震なんかじゃないわ』と彼女は言った。『地震よりずっとひどいものよ』」というように反復されていることからも明らかです。
10年間にもわたった連載「村上春樹を読む」の最終回に、この『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の中の「地震」の言葉について考えておきたいのです。
その場面は、続けて以下のようにあります。
「それは私がこれまでに耳にしたこともないほどの激しい悪意に充ちたおぞましい音だった。
私がその音についていちばんおぞましく思ったことは、それが我々二人を拒否するというよりは手招きしているように感じられたことだった。彼らは我々が近づいていることを知っていて、その喜びに邪悪な心を震わせているのだ。そう思うと、私は走りながら背筋が凍りついてしまうような恐怖を感じた。たしかにそれは地震なんかではなかった。彼女が言うように、地震よりもっとずっとおそろしいものなのだ。しかしそれが何であるのか私には見当もつかなかった」
そのような言葉が書かれているのです。ここに「地震」は確かに「おそろしい」ものだが、でもそれ以上に「おそろしく」「おぞましく」「邪悪な心を震わせている」ものが「私」と「太った娘」を手招きしているように感じると、村上春樹は記しているのです。
☆
「おそろしく」「おぞましく」「邪悪な心を震わせている」もの、それはどんなものでしょうか。
この場面の後、まもなく「私」と「太った娘」は地上に脱出するのですが、「太った娘」の祖父である「博士」がこんなことを「私」に言います。
「科学者というものは知の鉱脈を前にするとそれ以外の状況が眼中になくなってしまうきらいがあるです。またそれなればこそ科学も間断なき進歩を遂げてきたわけだ。科学というものは極言するならば、その純粋性の故に増殖するのであって……」と話します。
続けて、「博士」はこう言います。
「科学の純粋性というものがときとして多くの人々を傷つけることがあると言いたかっただけです。それはあらゆる純粋な自然現象がある場合に人々を傷つけるのと同じことです。火山の噴火が街を埋め、洪水が人々を押し流し、地震が地表の一切を叩き潰す――しからばそのような類いの自然現象が悪かと言えば……」
☆
「科学というものは極言するならば、その純粋性の故に増殖する」「科学の純粋性というものがときとして多くの人々を傷つけることがある」とは、直接的には同作で「シャフリング」という仕事をしている「私」が受ける人体実験的な手術のことなどを述べているのかと思いますが、東日本大震災(2011年3月11日)と福島第1原発事故の後に読んでみると、地震と原子力発電とその原発事故のことを述べているようにも感じるのです。
なにしろ、科学の純粋性が多くの人々を傷つけることがあることと、洪水が人々を押し流し、地震が地表の一切を叩き潰すような自然現象のおそろしさとが並べて語られているのですから。村上春樹の頭の中には、原子力発電所の事故のことも考えられていたのではないかと思えてくるのです。原子力爆弾のことも考えられていたのではないかと思うのです。
つまり、東日本大震災と原発事故のことを考えると、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は予言的な作品なのです。それも、かなり村上春樹が考え続けていたことを記した作品なのではないかと思えるのです。
☆
例えば『騎士団長殺し』(2017年)には「イデア」が「騎士団長」として形体化し登場しますが、その「騎士団長」と「私」との会話の中で「E=mc2という概念は本来中立であるはずなのに、それは結果的に原子爆弾を生み出すことになった。そしてそれは広島と長崎に実際に投下された」ことが語られています。
そして、この『騎士団長殺し』の最後には、東日本大震災と原発事故のことも登場します。でも、そのようなことが、東日本大震災と原発事故を契機にして、初めて村上春樹が考えたことではないということがよくわかる『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の言葉なのです。
科学が、その純粋性の故に増殖するし、科学の純粋性というものがときとして多くの人々を傷つけることがあるという考えが、『騎士団長殺し』より30年以上前の作品に記されているのです。
☆
『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の「世界の終り」の街には「東の森」が出てきますが、その「東の森」の中にある発電所は「風力発電所」です。『海辺のカフカ』(2002年)に出てくる発電所も「風力発電所」です。
それが「風力発電所」であることは、原子力発電ではない力によって、この世界は維持されていかなくてはならないということを、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』を書いた時点で、村上春樹が考えていたということではないでしょうか。
☆
さらにエッセイ集『村上朝日堂はいかにして鍛えられたか』(1997年)の最後に置かれた「ウォークマンを悪く言うわけじゃないですが」という文章の中で「原子力発電所に代わる安全でクリーンな新しいエネルギー源を開発実現化すること」を村上春樹は提案しています。
「もちろんこれは生半可な目標ではない。時間もかかるし、金もかかるだろう。しかし日本がまともな国家として時代をまっとうする道は、極端にいえば『もうこれくらいしかないんじゃないか』と、五年間近く日本を離れて暮らしているあいだに、実感としてつくづく僕は思った」と村上春樹が書いていることも、東日本大震災と原発事故の後、注目されました。実に原発事故が起きる14年も前の発言です。
このエッセイにある「五年間近く日本を離れて暮らしているあいだに」とは、1991年から1995年まで米国東海岸に村上春樹が住んだことですが、この間に書かれた長編が『ねじまき鳥クロニクル』(1994年、1995年)です。
その『ねじまき鳥クロニクル』では、ノモンハンの「歴史」を「僕」に伝えにくる間宮中尉は広島出身であり、原爆で妹と父を失い、ショックで母も2年後に亡くなったという人です。そして「僕」が戦う相手である、日本を戦争に導いたような精神の持主・綿谷ノボルが「長崎」で倒れています。このように村上春樹作品は「広島」と「長崎」という日本が受けた2度の原爆による惨禍を意識して、書き続けられているのです。
☆
今回の「村上春樹を読む」は「地震と村上春樹作品 その2」という形で書きたいと、このコラムの冒頭で述べました。
ですから「地震」について、記さなくてはなりません。既に紹介した言葉ですが、以下の言葉から、「地震」について、もう少し考えてみたいと思います。2つとも少し長いですが、もう1度、引用します。
「彼らは我々が近づいていることを知っていて、その喜びに邪悪な心を震わせているのだ。そう思うと、私は走りながら背筋が凍りついてしまうような恐怖を感じた。たしかにそれは地震なんかではなかった。彼女が言うように、地震よりもっとずっとおそろしいものなのだ。しかしそれが何であるのか私には見当もつかなかった」
「科学の純粋性というものがときとして多くの人々を傷つけることがあると言いたかっただけです。それはあらゆる純粋な自然現象がある場合に人々を傷つけるのと同じことです。火山の噴火が街を埋め、洪水が人々を押し流し、地震が地表の一切を叩き潰す――しからばそのような類いの自然現象が悪かと言えば……」
という言葉の意味を考えてみたいのです。
☆
その入り口として、村上春樹が阪神大震災をテーマにして書いた連作短編集『神の子どもたちはみな踊る』(2000年)の「かえるくん、東京を救う」のことを紹介したいと思います。
「これはあまりぱっとしない中年の銀行員のアパートを、ある日巨大な蛙が訪れるという、かなり奇妙な筋の物語です」。そのように村上春樹自身が『若い読者のための短編小説案内』(1997年)の文庫版(2004年)の冒頭に置かれた「僕にとっての短編小説」の中で書いています。
さらに「本を刊行したときには、とくにそういう印象もなかったのですが、時間が経つにつれて、『かえるくん、東京を救う』の存在意義が、この短編集の中で確実に重くなってきたようです」とありますし、その作品集の中で「どうやらそのときの波のてっぺんに到達した、中心的な作品である」とも加えています。
同作は、その「かえるくん」が東京安全信用金庫の新宿支店に勤務する「片桐」の力を借りて、3日後に起きる東京直下型の地震を未然に防ぐ物語です。
地震の原因は、地下50メートルにすむ巨大な「みみずくん」の心と身体の中で「長いあいだに吸引蓄積された様々な憎しみ」の力です。その「みみずくん」と「かえるくん」が闘う際に、地下の暗闇の中は「かえるくん」に不利なので、「片桐」は「足踏みの発電器」を用いて「その場所に力のかぎり明るい光」を注いでいます。
『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』や『海辺のカフカ』の発電所が「風力発電所」であったこと、この「片桐」の「足踏みの発電器」による「明るい光」に、同じような村上春樹の一貫したエネルギー観を受け取ることができます。
☆
ただ、ここで考えてみたいのは、「地震」が地下50メートルにすむ「みみずくん」の心と身体の中で「長いあいだに吸引蓄積された様々な憎しみ」の力で起きると村上春樹が記していることです。
普通に考えれば、地震は地下で起きる岩盤の「ずれ」により発生する現象です。もちろん、村上春樹はそんなことは十分わかっていますが、でも地下の闇にすむ「みみずくん」の心と身体の中で「長いあいだに吸引蓄積された様々な憎しみ」の力で起きると書いているのです。
ここに、私は『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』で記された、地下の暗闇の中で「私がこれまでに耳にしたこともないほどの激しい悪意に充ちたおぞましい音」と響き合うものを感じるのです。
その音の源である「彼らは我々が近づいていることを知っていて、その喜びに邪悪な心を震わせているのだ。そう思うと、私は走りながら背筋が凍りついてしまうような恐怖を感じた。たしかにそれは地震なんかではなかった。彼女が言うように、地震よりもっとずつとおそろしいものなのだ」という言葉と響き合う考えです。
☆
「科学の純粋性というものがときとして多くの人々を傷つけることがあると言いたかっただけです。それはあらゆる純粋な自然現象がある場合に人々を傷つけるのと同じことです。火山の噴火が街を埋め、洪水が人々を押し流し、地震が地表の一切を叩き潰す――しからばそのような類いの自然現象が悪かと言えば……」と村上春樹は書いていました。
これを語る「博士」によれば、「科学の純粋性というものがときとして多くの人々を傷つけることがある」のですが、「火山の噴火」や「洪水」や「地震」という自然現象が人々を傷つけるのと同じで、その自然現象を悪とは言えないように、「科学の純粋性というものがときとして多くの人々を傷つけること」が「悪とは言えないのではないか……」ということを言いたいのかもしれません。
☆
でも村上春樹は、その自然現象である「地震」も「みみずくん」の心と身体の中で「長いあいだに吸引蓄積された様々な憎しみ」の力で起きると考えているのです。ですから「かえるくん、東京を救う」の「かえるくん」と「みみずくん」の地下の暗闇の闘いは、それぞれの「心」の闇の中の闘いなのだと思います。
そして『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』という長編は、「心」という大切なものを取り戻す物語です。他人に預けてはいけない、自分の「心」という大切なものを取り戻す物語。他人には預けることができない大切な、自分の「心」というものを発見する物語です。
でも、私たちは自分の大切な「心」を自分以外の何かに預けて生きてはいないでしょうか。
例えば、効率性を追求する社会の集団性の中で、自分の「心」を「効率追求社会」の側に預けていないでしょうか。会社員ならば、会社組織に「心」を預けて生きてはいないでしょうか。1つの原理を信じて、その原理だけですべてを測り考えるような原理主義に「心」を預けていないでしょうか。「純粋性」ゆえに「ときとして多くの人々を傷つけることがある」「科学」というものに「心」を預けて生きていないでしょうか。
このように、自分の「心」という大切なものを<他人に預けてしまう世界に誘い、手招きするもの>こそが、あの地底で「私」と「太った娘」の二人が聞いた「音」の姿でもあるでしょう。「彼らは我々が近づいていることを知っていて、その喜びに邪悪な心を震わせている」のです。その先にあったものが原発事故だったのではないでしょうか……。
☆
この連載の最初は東日本大震災が起きた直後、同大震災の発生から2カ月後の2011年5月から始まりました(前回同6月と記しましたが、調べてみると、さらに1カ月前から始めていました)。
その東日本大震災、福島第1原発事故から3カ月後の2011年6月9日。スペイン・バルセロナのカタルーニャ国際賞授賞式の受賞スピーチで、村上春樹は、歴史上唯一、広島と長崎に核爆弾を投下された経験を持つ日本人にとって、福島第1原発事故は2度目の大きな核の被害であることを述べ、我々日本人は核に対する「ノー」を叫び続けるべきだったと語って、大きな話題となりました。
そしてなぜ「2度の原爆の惨禍を体験した日本社会から『核』への拒否感がどんな理由で消えてしまったのか」。それについて、村上春樹は「理由は簡単です。『効率』です」と語っています。なんと6回も「効率」という言葉を使って、村上春樹は話していました。
それは「効率」というものに、自分の大切な「心」を預けてはいけないという村上春樹の発言でした。
その原発事故や核爆弾についての発言が、村上春樹にとって、唐突にあらわれてきたものではないことを『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は示しているのです。「科学の純粋性というものがときとして多くの人々を傷つけることがある」という言葉の中に、既に、深く考えられていたということです。
「地震」という自然災害を考える時、それが起きたことは自然の力で、人間の力は関係がないと考えがちです。でも紹介したように、その「地震」は地下にすむ巨大な「みみずくん」の心と身体の中で「長いあいだに吸引蓄積された様々な憎しみ」の力で起きると考えるのが、村上春樹です。
そして、東日本大震災と原発事故で「地震」災害が、私たちの「心」の姿と<関係がないことではない>ことが、明らかになったのです。
☆
「喜びに邪悪な心を震わせている」暗闇の中の音との闘いは、我々自身の「心」の深いところでの闘いです。
カタルーニャ国際賞の受賞スピーチでも、村上春樹は、福島第1原発事故について「原子力発電所の安全対策を厳しく管理するべき政府も、原子力政策を推し進めるために、その安全基準のレベルを下げていた節が」あることを述べると同時に「しかしそれと同時に我々は、そのような歪んだ構造の存在をこれまで許してきた、あるいは黙認してきた我々自身をも、糾弾しなくてはならないでしょう」と話しました。
原発事故は「日本が長年にわたって誇ってきた『技術力』神話の崩壊」であると同時に「そのような『すり替え』を許してきた、私たち日本人の倫理と規範の敗北」でもあったと語りました。原発事故も「我々日本人自身がそのお膳立てをし、自らの手で過ちを犯し、我々自身の国土を損ない、我々自身の生活を破壊しているのです」とも語っていました。
これらはすべて、「我々」の「心」の闘いでもあるのです。
☆
そして、その闘いの場である「心」とはどういうものでしょうか。それを『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の中の言葉から紹介してみましょう。
『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の「世界の終り」の「僕」と「影」の対話の中で「心というものはそれ自体が行動原理を持っている。それがすなわち自己さ。自分の力を信じるんだ。そうしないと君は外部の力にひっぱられてわけのわからない場所につれていかれることになる」と「影」が「僕」に話しています。
その「世界の終り」の話に登場する図書館の司書の女の子が「私には心がどういうものなのかがよくわからないの」というと、「僕」は彼女に対して「心というものはただそこにあるものなんだ。風と同じさ。君はその動きを感じるだけでいいんだよ」と答えています。
デビュー作『風の歌を聴け』(1979年)のタイトルに繋がる言葉ですね。きっと、今回の「村上春樹を読む」で書いたことは、村上春樹がデビュー以来、考え続けてきたことなのではないかと思います。
☆
前回も予告しましたが、今回で10年間、毎月連載してきたこのコラム「村上春樹を読む」を終了します。こんなに長く、よく書いてきたなぁ……と正直思います。
村上春樹の新作長編が発表されたりしたら、番外編を書くかもしれませんし、別な形で村上春樹作品を貫くものについて書いてみたいとも考えていますが、一応、これで連載終了です。
愛読してくださった読者の方々に深く感謝いたします。ありがとうございました。(共同通信編集委員 小山鉄郎)
******************************************************************************
「村上春樹を読む」が『村上春樹クロニクル』と名前を変えて、春陽堂書店から刊行されます。詳しくはこちらから↓

