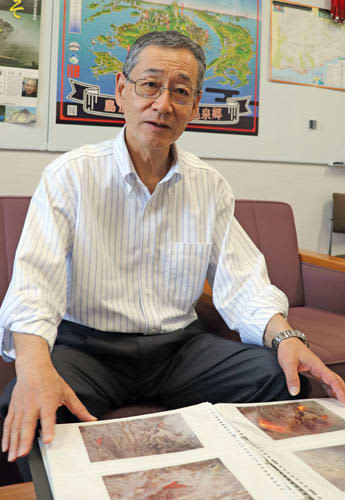
「住民が火山を知ることが一番大切。火山と共生する以上、自ら町のリスクを知り、災害を自分事として考えてほしい」-。九州大地震火山観測研究センターで雲仙・普賢岳と向き合ってきた清水洋さん(65)=同大名誉教授=。今春、大学を退き、37年にわたる研究生活は、普賢岳噴火災害の歴史とほぼ重なる。43人が犠牲となった1991年6月3日の大火砕流惨事から31年。清水さんが問いかける火山との共生とは-。
群馬県出身。少年時代、浅間山の噴火災害を経験し、火山学者を志した。85年、同大島原地震火山観測所(現・同センター)の助手に採用。「火山のホームドクター」と呼ばれた太田一也所長(当時)のもとで研究と観測に心血を注いだ。
あの日-。地震計の中継点だった島原市立第三中の屋上で機器を点検していた。普賢岳中腹まで垂れ込める雨雲から突如、噴煙が突き破って迫ってきた。大火砕流だった。監視カメラなどがあった山間部の北上木場農業研修所にも行く予定だったため、消防団員ら多数の犠牲に衝撃を受けた。「自分の命もなかったはず」
世間と距離を置き、ひたすら火山学を究める-。そんな研究姿勢を180度変えたのが、大火砕流の直後の出来事。91年6月12日未明、溶岩ドームの頂上で爆発的噴火が起き、噴石が広範囲に降った。傾斜計は山の膨張をとらえ、そのデータを気象庁に送った。
しかし、公式発表前に報道機関に漏れ、不正確な情報が伝わった。一部の報道陣が島原から撤退し、デマやうわさが市民の間で飛び交った。県立島原温泉病院(当時)は入院患者を市外の病院に搬送したが、転院先で半数以上が亡くなったと、のちに知った。
「知り得たデータは正しく伝えないと悲劇を生む。研究が社会に与える影響の大きさを嫌というほど味わった」。研究者はデータと向き合うだけでなく、刻々と変化する情報を発信し、自治体の防災対策と共有する-。苦い教訓は島原発の火山防災のモデルになった。一方で、噴火規模や終息の予測に関する期待に応えられず、もどかしさも常につきまとった。
約5年半に及ぶ噴火災害で「火山のホームドクター」の必要性が認識された一方、大学の独立法人化の影響などで研究費や人員削減が続く。「噴火予知は天気予報のレベルに到底及ばない。観測を続けることで成果が出る。研究は国家百年の計で進めるべきで、防災はある意味、国防。次の噴火に備えるために、国の支援と国民の理解が求められる」
悲惨な記憶の風化が危惧される中、島原で火山を見つめ、未来へ警鐘を鳴らし続ける清水さんの信念は揺るがない。
