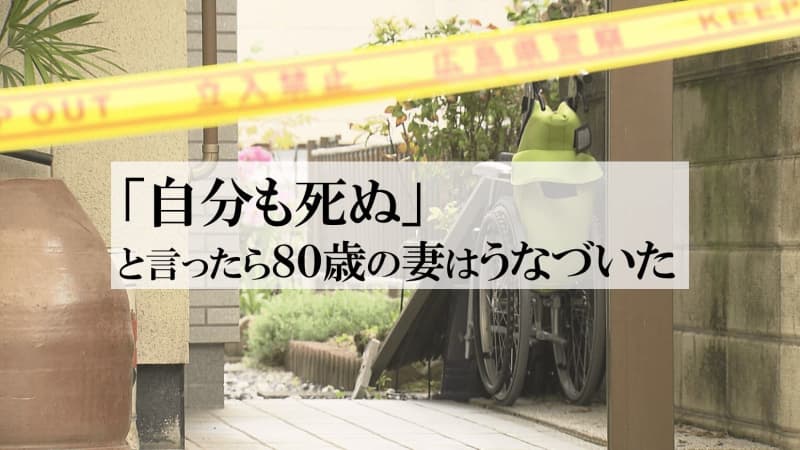
「2年が経ちますね。私は、”あの方”がどのような状況で介護をされていたのか知りたかった。妻は77歳、私は83歳でしたからね、うちも老老介護だったので…」
そう話すのは、広島市安佐北区に住む山田夏樹さん(85)です。
「老老介護」とは、一般的に、介護をする側もされる側も65歳以上の状態のことをいいます。
(山田さん)
「私の妻は、60歳のころに若年性アルツハイマーと診断され、それから20年ほどが経ち、おととし亡くなりました。亡くなる6年ほど前から『要介護5』の認定を受けていました。寝たきりで会話もできない、好きだったカラオケも忘れていきました。102歳まで生きた母の介護も同時にやっていた時期もあり、横並びのベッドに横たわった2人の世話をするのは大変でしたが、”あの方”も本当に苦労されとっちゃったんだろうなと思います」
山田さんが言う「あの方」とは、同じく広島市安佐北区に住んでいた、村武哲也さん(当時72)のことです。
(山田さん)
「あの方は、今はどうされとるんですか?」
(記者)
「事件についての判決を受けた後の秋に、お亡くなりになったと聞いています」
(山田さん)
「そうですか…。事件についての新聞記事を読んだとき、私とあの方は、状況に差はあったかもしれないけど、何も違わないんじゃないかと思っていました」
山田さんのいう事件とは…。
2021年4月、広島市の住宅で72歳の夫が自宅での「老老介護」の末に、長年連れ添った80歳の妻を殺害する事件が起きました。あれから2年…。裁判で明らかになった事実や地域での取材を基に、事件を振り返ります。
”承諾殺人” 夫妻を知る人からは介護の事情…
2021年4月30日、広島市安佐北区の住宅で、当時72歳だった村武哲也(むらたけ・てつや)さんが、自宅で、長年連れ添った当時80歳の妻・亥聖子(いせこ)さんの首を、家にあったマフラーで絞めて殺害しました。
哲也さんが病院に来ないことで連絡を受けた介護支援専門員が2人の自宅を訪れたとき、哲也さんは手首に傷を負った状態で見つかりました。
警察は、回復を待って、哲也さんを「殺人」の疑いで逮捕しました。
事件の発生が警察によって報道機関に明かされた5月、現場付近の住民を取材して聞いたのは、村武夫妻の「介護」の事情でした。
(向かいに住む森脇康則さん・2021年)
「介護ねぇ、奥さんが脳梗塞で倒れられて、それからずっと村武(哲也)さんが見ておられたんじゃけど、ようされとったですよ」
捜査の結果、哲也さんが検察に起訴された罪名は「承諾殺人」。
哲也さんは、亥聖子さん本人の承諾を得て、殺害した罪に問われることになりました。72歳と80歳の高齢同士2人っきりで暮らし、介護をしていたという哲也さん。
当時私は、哲也さんに、事件をなぜ起こしてしまったのか聞きたいと思い、広島拘置所で面会を申し入れました。
面会室に通されると、アクリル板の仕切りの向こうの扉が開き、拘置所の職員が、車いすに座り腕に点滴がつながれた男性を連れてきました。哲也さんです。
(記者)
「体調はどうですか?」
(哲也さん・拘置所で面会時)
「全身が痛む」
「これ以上は ようはならん…」 妻は悲観的に
哲也さんは、10年前から直腸がん、5年ほど前から胃がんを患っていると、淡々と自身の体調を語りました。
左手首には、妻を殺めたあとに自分でつけたという傷があり、ガーゼがあてられていました。
私は哲也さんに、生前の亥聖子さんの病状について尋ねました。
(哲也さん)
「妻は6、7年前に脳梗塞を患い、左半身の麻痺が出ていました」
(記者)
「しだいに麻痺が出てきたのですか?」
(哲也さん)
「急にです。妻が、『今日買い物に行ったとき、倒れたんじゃ』と言ったので、近くの病院の夜間救急に連れて行き、そこで脳梗塞と診断されました」
哲也さんと亥聖子さんの間に子どもはいませんでしたが、50年以上連れ添い、元気なころには2人で釣りにも行っていたそうです。
しかし、病は進行し、事件の前は亥聖子さんの腰の痛みがひどくなり、哲也さんは1日6回、痛み止めの座薬を入れていたと話します。
いつごろからだったのかは聞けませんでしたが、亥聖子さんは「これ以上はようはならん…」と、悲観的になっていたそうです。拘置所で哲也さんは、にじんだ涙をトレーナーの袖でぬぐいながら、事件当日のことを明かしました。
(哲也さん)
「その日の朝は、女房はうつろで会話もなかなかできる状態じゃなかった。女房に『今日、死ぬかい?』と聞くと、『いいよ』と言った。『自分も死ぬ』と言ったら女房はうなづいた」
哲也さんは、ベッドに横になっている亥聖子さんの首をマフラーで絞めました。
(記者)
「亥聖子さんは、抵抗しなかったのですか?」
(哲也さん)
「まったく…。女房も体力もないし、こっちもないし。もうこれ以上は無理じゃと思った。本当は2人で逝く予定だった…。すぐ逝けんかったことを謝りたい」
誰かに相談はできなかったのか。哲也さんは、近所の人や親族に相談できる環境だったことは否定しませんでした。しかし一方では…。
(哲也さん)
「自分で何とかしようという思いがあった」
「もっと簡単に援助を受けられる世の中に」
2021年6月24日、広島地方裁判所で始まった裁判。
被告人質問で、「当時を振り返ってどうしていたらよかったと思うか」と尋ねられると、哲也さんは「もっと方法はなかったか…。でも無かったと思う」と答えました。
弁護人が最終弁論を終えたあと、裁判官は村武さんに「最後に何か言いたいことはありますか」と問いました。
(哲也さん・裁判で)
「もっと簡単に介護の援助を受けられる、そんな世の中になったらいいなと思います」
逮捕からおよそ2か月後、哲也さんに判決が言い渡されました。
(裁判官)
「主文、被告人を懲役3年に処する。この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する」
これまでの証拠から、裁判官は、哲也さんが自らもがんを患って闘病生活を送りながら、体が不自由な亥聖子さんを献身的に介護していたことを認めました。
そのうえで、「亥聖子さんは次第に衰弱し精神的にも落ち込んで『死にたい』などと漏らすようになっていた。被告人は、介護の負担が増していくと同時に被告人自身の体力も低下し、状況の好転が見込めないなか、心身ともに限界を感じて犯行に及んだ。しかし、承諾があったとはいえ、人を殺害する行為は決して許されるものではない」と指摘しました。
一方で、裁判官は、犯行に至った経緯や動機については、「酌むべき点が多分にある」と、こう述べました。
(裁判官)
「介護支援専門員から亥聖子さんを施設に入所させることを提案されるなど、被告人の負担を軽減し得る選択肢もあったなか、自ら在宅介護を続けることを選び、結果的に本件犯行に至ってしまったことは悔やまれる。介護を続けたのも、妻の意思と、妻の面倒を最後まで見たいという被告人の思いによるものであり、強く非難はできない」
判決を言い渡した後、裁判官は、哲也さんに次のように声をかました。
(裁判官)
「村武さんは、別の罪を犯すことはないと思います。長いこと奥さんのために尽くしてきたと思いますが、これからは自分のことを第一に考え、体を大事に、心穏やかに過ごしてください。それでは、閉廷します」
裁判の関係者や傍聴席の私たちが立つと、哲也さんは、手で支えながらゆっくりと車いすから立ち上がり、「ありがとうございます」と言って一礼しました。
哲也さんが一通り傍聴席に目をやった後、拘置所の職員は車いすを押し、哲也さんを法廷から連れて出ていきました。
判決はそのまま確定し、哲也さんは入院しました。
しかし、事件の関係者によると、全身がガンにむしばまれていた哲也さんは、その年の秋に亡くなりました。
「我が身のことのように…」「夫妻のことは記憶から消えない」
2022年の4月、私は、村武夫妻の自宅がある住宅地を訪れました。
自宅のチャイムを鳴らしてみましたが反応はありません。外にあるガス栓には「閉栓中」と書かれていました。
向かいに住む森脇康則さんは、村武夫妻との思い出を話してくれました。
(森脇康則さん・2022年)
「私の孫が遊びに来たときには、奥さん(亥聖子さん)が窓から顔を出して『あんた、おいでおいで』って言って、孫におもちゃをくれたことが何回かありましたね。すごく可愛がってもらった。哲也さんとは飲みに行ったこともありました」
事件前を振り返ると、森脇さんは、何かしてあげられたのでは?と後悔する気持ちもあるのだといいます。
(森脇さん)
「哲也さんは、ここ数年目に見えるほどに痩せてきていた。病気もあって『体が痛いんじゃ』と言っていたが、明るく振る舞っていました。事件があった日、私は家の窓から救急車が来ていたのを見ていた。寂しかった」
「村武さんがいつか戻ってくるかと思って、玄関にかかっている傘を毎日見ていたんですよ。帰ってきたら傘を取るだろうから、目印になると思っていた。でもこの傘は誰も使うことはないんですよね」
「町では、コロナ禍になって一堂に会することが減ってしまっていたんですよね。過去を振り返ると立場的には私はつらい。責任を感じている。つっこんで話を聞くべきだったのか…」
亥聖子さんは、元気だったころ花の世話をよくしていたそうです。2人が亡くなって初めての春、こんなことがあったといいます。
「この前、村武さんのところのチューリップが4本くらい咲いたんですよ。立派なチューリップでね、なにかの思いもあったのかもしれん、チューリップにも」
さらに1年がたち、再び、村武夫妻が暮らしていた住宅地に足を運びました。傘は玄関先にぶら下がったまま。村武夫妻の家の様子に、大きな変化はみられません。事件以来、人が出入りする様子は見ないと、複数の住人が話しました。
(近くに住む女性)
「(村武夫妻は)仲がいいご夫婦でした。ご主人が大声で怒っているような声も聞いたことがありませんでしたし、奥さんが病気をしても一緒に散歩をしておられるところも見たことがありました。この辺りはお年寄りが多い。私も夫もまだ介護を必要としていないけれど、あと10年、20年生きると思うと、我が身のこと…と考えてしまいます」
向かいに住む森脇さんは、いまも村武夫妻のことを思い出すことがあるそうです。
(森脇さん)
「いつも私が犬の散歩で家を出るとき、村武(哲也)さんが洗濯ものを干しながら『おはよう』って言ってくれていましたね。夕方は洗濯ものを今度は取り込みよって、あいさつすることもありましたね。いまも散歩をするから、村武さんの家の方を見たときには思い出します」
いっしょに飲みに行ったことや、孫におもちゃをくれたこともあった村武夫婦への思いを聞きました。
(森脇さん)
「身内とは違いますが、こうやって家がある限りは、ここには村武さんというご夫婦がいたなぁ、という思いは、私が死ぬまで消えないと思うんです。小学校の高学年になる孫に、覚えとるかと聞いたら、覚えていましたよ。『あのおばちゃんね、あのおじちゃんね』と」
進む介護の高齢化 夫妻が地域に残したもの
事件をきっかけに、去年、広島市安佐北区では、介護を経験した男性や、これから介護をするかもしれないという男性たちが、気軽に足を運んで話ができる会=「かめやまケアメンの会」が発足しました。
地域のコミュニティセンター「まちづくり四日市役場」で、参加費100円で月に一度、開かれています。地域包括支援センターのケアマネジャーや、栄養士などの資格をもった区役所の職員も参加し介護の当事者と意見交換をして、在宅介護の支援について考えます。毎月、10人ほどが参加しているということです。
この会の立ち上げに関わったのが、この記事の冒頭で話を聞いている山田さんです。
(山田さん)
「私とあの方は、状況に差はあったかもしれないけど、何が違うのか…、何も違わないんじゃないかと。あの方の介護の状況が知りたかったのでコミュニティセンターの人に連絡をしたら、『どんな事情があったのかは分からないが、山田さんと同じように自分の状況と重ねてしまう男性は、他にもいるかもしれない』と。それで、会ができたようです」
(山田さん)
「いまは、介護経験者として参加しとりますが、自分自身も、老いを生きるためにいろんな人の話が聞けて学びがあります」
山田さんは、102歳で亡くなった母親と77歳で亡くなった妻の介護生活を小説にしました。その一節で、山田さんは、家族の最期を看取って感じたことを、次のように振り返っています。
「人は食べよう、飲もうとすることが、最後の生きる、生きようとする力なのではないか」
「歌がうたえなくなっても、言葉がしゃべれなくなっても、まだまだ人として生きている。だが、食べよう、飲もう、それを望んでもできなくなった時、人は命を落としていくのかもしれない」
「だが、それにしても、と私は思う。あまりにも突然にその日がやってくることは何としても理不尽なのではないか」(山田さんの小説「残照日録2」より引用)
去年9月、厚生労働省は2021年の国民生活基礎調査の結果を発表しました。調査によると2021年時点で、65歳以上の高齢者のみの世帯の数は、およそ1506万世帯でした。これは、全世帯の29.0%にあたり、20年前(2001年)の世帯割合(14.6%)と比較すると、ほぼ2倍に膨らんでいたということです。
また厚生労働省によると、2019年、介護をする人もされる人も65歳以上の「老老介護」の世帯の割合は、自宅で介護をしている世帯のおよそ6割(59.7%)に上っていて、2001年の40.6%から20%ほど上昇しました。「介護の高齢化」は年々進んでいます。
家族支援や在宅介護の制度の研究を専門としている、国際医療福祉大学大学院の石山麗子教授は、「介護をしている人の心の負担を和らげるためには、介護支援専門員や医師などスペシャリストの存在以外にも、家族や長い付き合いの知り合いが周りにいることが大切」だとしています。
(中国放送/山崎有貴)

