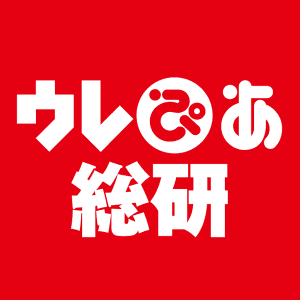「最近、夫の口臭が気になる。でも本人は気づいていないようで指摘しづらい……」
配偶者の口臭に悩んでいる女性は少なくありません。しかし、デリケートな内容なだけに指摘できず、対策をとれていない人も多いようです。
今回は、口臭が発生する原因や、おすすめの対策方法について解説します。
口臭はなぜ発生するの?
口臭が発生する主な原因は、口の中の細菌です。この細菌は嫌気性菌と呼ばれ、タンパク質やアミノ酸を分解してにおいの原因物質を作り出します。
口臭は、においの原因物質が増える要因によって、生理的口臭と病的口臭に分けられます。
生理的口臭は、朝起きた直後や空腹時、緊張しているときなど、唾液の分泌が減るタイミングで発生します。唾液の分泌が減ると口の中の細菌が繁殖しやすくなり、においの原因物質が作り出されるのです。
生理的口臭は一時的なものであり、また、誰にでも当てはまるため、あまり気にする必要はありません。
一方、病的口臭は、歯周病や虫歯などの病気が原因で発生する口臭です。歯石や歯垢(しこう)が、においの発生源となる場合もあります。原因である病気を治療することで、口臭の発生を抑えられます。

口内のにおいを悪化させてしまう悪習慣
普段の何気ない習慣のなかに、口内のにおいを悪化させてしまう原因が潜んでいます。ここでは、注意すべき習慣を3つご紹介します。
1.ドライマウス
ドライマウス(口の中の乾燥)になると唾液の分泌が減り、細菌が増殖しやすくなります。唾液には口内の細菌の繁殖を抑え、口の中を洗浄する役割がありますが、分泌量が減ると十分に役割を果たせず、増殖した細菌が作り出すにおいの原因物質によって口臭が悪化します。
唾液の分泌を促すため、こまめに水を飲んだり、シュガーレスガムを噛んだりすることが重要です。
2.飲食物によるにおいの発生
においの強い飲食物によって、口臭が発生することもあります。
コーヒーやお酒、にんにく、ニラなどは、そのもののにおいが口の中に残って直接においが発生する場合と、体内で分解されるときに発生したにおい物質が、血流を通じて呼吸や汗などで放出される場合があります。
口臭だけでなく体臭の原因にもなるため、摂取のし過ぎには気をつけましょう。においの強い飲食物を摂取した後は、歯磨きやうがい、水分補給を意識するとにおいを軽減できます。
3.たばこによるにおいの付着
たばこに含まれるタールは、歯や舌に付着し口臭となります。また、ニコチンには唾液の分泌を抑える作用があるため、喫煙後の口の中は細菌が増えやすい環境になり、口臭の原因となります。

今すぐできる!おすすめのオーラルケア3つ
口臭対策には、日頃のケアが重要です。毎日の生活にとり入れて、口臭を予防しましょう。
1.歯磨きの見直し
食べかすが残らないよう、歯と歯の間、歯と歯茎の間を丁寧に磨きましょう。さらに、デンタルフロスを使うと、歯の表面にくっついている歯垢をしっかりとり除くことができます。
歯垢とは、歯の表面に付着している細菌のかたまりであり、この細菌によってにおいの原因物質が作り出されます。歯ブラシだけでは、歯や歯茎の隙間の歯垢をとり除くのが難しいため、デンタルフロスの活用がおすすめです。
また、マウスウォッシュやデンタルリンス(液体歯磨き)の併用もおすすめです。マウスウォッシュは口をゆすぐだけなので、時間がなくてもさっと口の中を洗浄できます。デンタルリンスを用いる場合は、口をゆすいだ後に歯ブラシでブラッシングする必要があります。
どちらも口臭の予防効果や口内の洗浄効果が期待できます。使い方を確認したうえで使用しましょう。
2.舌磨き
舌磨きによって、舌に付着している白い苔のようなものをとり除きましょう。
白い苔のようなものは舌苔(ぜったい)と呼ばれ、食べかすや口の中の粘膜が剥がれ落ちたものなど、さまざまな物質がたまって腐敗したものです。口臭の多くは、この舌苔から発生したにおいによるものです。
舌を傷つけないために、歯ブラシではなく舌ブラシの使用がおすすめです。鏡で舌を見ながら、奥から前の方にやさしく動かしましょう。舌ブラシは、薬局やスーパーなどで購入できます。
3.規則正しい食生活
口臭対策には規則正しい食生活も重要です。朝食を抜いたり簡易な食事ばかり摂ったりしていると、唾液の分泌が促進されず、細菌が繁殖しやすい環境になります。
また、流動食や柔らかい食事ばかりの場合も同様に、噛む回数が少ないため唾液があまり分泌されず、洗浄作用が十分に発揮できません。
規則正しいバランスのとれた食生活を心がけ、唾液の分泌を促進しましょう。

口臭対策には漢方薬もおすすめ
口臭対策には、毎日のオーラルケアに加えて、漢方薬もおすすめです。漢方薬は、体質の根本改善にアプローチしていきます。
口臭は、唾液分泌量の減少やストレス、胃腸の不調、口内の病気などが原因と考えられています。
そのため、口臭対策には、
・水分の循環を改善して唾液分泌を増やす
・歯茎の炎症や腫れを抑える
・胃腸の働きをよくして口臭の原因となる消化不良を改善する
・自律神経を整えて、唾液を出やすくする
などの作用を含む漢方薬を選び、根本からの改善を目指します。
漢方薬は、からだ全体のバランスを整えてくれるので、すべての症状にアプローチできます。さらに、体質改善にも役立つので、口臭以外のお悩みの改善にもつながるでしょう。
口臭対策におすすめの漢方薬
排膿散及湯(はいのうさんきゅうとう)
歯肉炎、歯周病の原因となる歯茎の炎症や腫れを鎮め、膿を排出する働きがあります。
麦門冬湯(ばくもんどうとう)
胃の働きを整えて潤いを作り出すことで、のどや気管などの呼吸粘膜を潤し、唾液の分泌も促進させます。
黄連解毒湯(おうれんげどくとう)
口の苦さ、口臭、黄苔のある舌などの症状を伴う胃腸の炎症に用いられます。
漢方薬を選ぶときに重要なのは、その人の状態や体質に合っているか、ということです。うまく合っていないと、効果を感じられないだけでなく、場合によっては副作用が生じることもあります。
スマホで気軽に専門家に相談できる「あんしん漢方」のような、オンライン個別相談も話題です。あんしん漢方はAI(人工知能)を活用し、漢方のプロが効く漢方を見極めて自宅に郵送してくれるオンライン漢方サービス。
スマホで完結できるので、対面では話しづらいことも気軽に相談できますよ。お手頃価格で不調を改善したい人は、医薬品の漢方薬をチェックしてみましょう。
*
口臭を抑えるためには、日々のケアが重要です。口臭を相手に指摘するのはためらわれるかもしれませんが、悪化する前に一緒に対策を始めることで、口臭の軽減が期待できます。
今回ご紹介した方法をぜひとり入れてくださいね。また、口臭が強く気になる場合には、歯科や内科を受診するのもおすすめです。
<この記事を書いた人>

あんしん漢方薬剤師
山形 ゆかり
薬剤師・薬膳アドバイザー・フードコーディネーター。病院薬剤師として在勤中、食養生の大切さに気付き薬膳の道へ入り、牛角・吉野家他薬膳レストラン等15社以上のメニュー開発にも携わる。
症状・体質に合ったパーソナルな漢方をスマホ一つで相談、症状緩和と根本改善を目指すオンラインAI漢方「あんしん漢方」でも薬剤師としてサポートを行う。
(ハピママ*/ あんしん漢方)