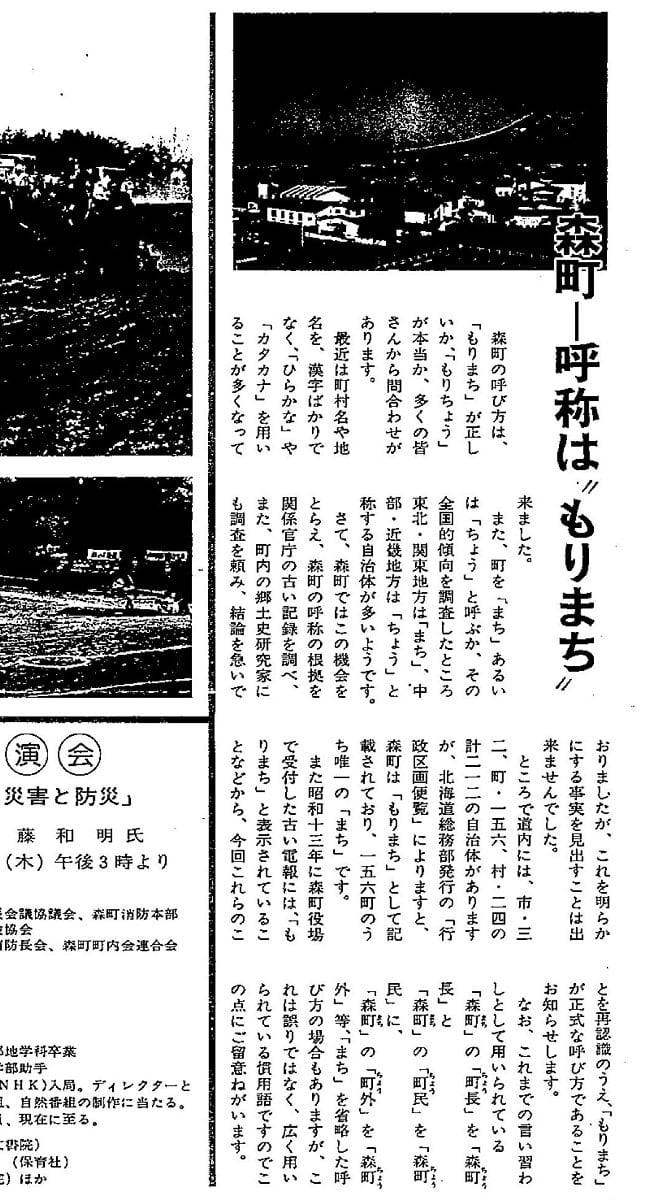
自治体の「町」の読み方が「ちょう」がメジャーか、「まち」がメジャーか地域によって異なる。しかし一つ珍しい事実が…。129町ある北海道と12町の静岡県は「ちょう」派の地域だが、ともに「森町(もりまち)」があり、両道県内で唯一「まち」と読む。由来に共通点はあるのか。北海道の森町総務課によると、以前は「もりまち」と「もりちょう」が混用されていたが、1987年に「まち」に正式決定し、報道発表したり広報誌で周知したりしたという。
北海道森町の当時の広報誌は「森町―呼称は“もりまち”」と題した記事で、「『もりまち』か『もりちょう』か、多くの皆さんから問い合わせがあります」「全国的傾向を調査したところ東北・関東地方は『まち』、中部・近畿地方は『ちょう』と称する自治体が多いようです」と説明している。
同町は本来の読み方をはっきりさせようと、関係省庁の古い記録を調べたり、地元の郷土史研究家に調査を頼んだりしたが、読み方の根拠は見つからなかったという。北海道総務部発行の「行政区画便覧」や1938年に役場で受け付けた電報に「モリマチ」と書かれていたことから、「まち」に正式決定し、87年6月から「もりまち」に統一すると発表した。
一方、静岡県森町社会教育課によると、元々は「森」と呼ばれ、物資や人の集散地として市(いち)が立ち、1604(慶長9)年の検地によって「森町村」となった。この町は栄えた地を指す「町場」の意味だった。明治時代に町村制が導入されたが、「町が二つ続く『森町町』になると不自然なので、『村』が取れて森町になったと考えられる」(稲葉優介主査)という。
「まち」「ちょう」…「町」の読み方はどっち? 調べてみたら石川・福井の県境に分岐があった
北海道森町と静岡県森町は1968年に友好提携し交流を続けている。
