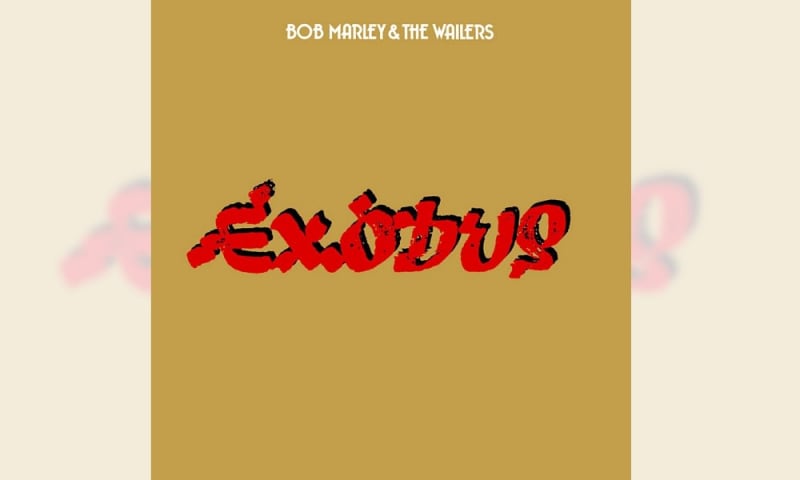
海外で2024年2月14日に劇場公開され全米興行収入2週連続1位を記録、英仏ではあの『ボヘミアン・ラプソディ』を超える初日興行収入、母国ジャマイカでは初日興行収入としては史上最高数を記録したボブ・マーリー(Bob Marley)の伝記映画『ボブ・マーリー:ONE LOVE』。
日本では2024年5月17日に公開されたことを記念して、ライター/翻訳家の池城美菜子さんによるボブ・マーリーの生涯と功績についての連載企画を実施中。
今回はこの連載を締めくくる最終回。劇中にも登場した名盤について解説頂きました。
____
映画公開から約3週間、『ボブ・マーリー:ONE LOVE』の興行成績でアジア圏においてダントツ1位を記録した。予想の範囲内だが、近年は海外作品の興行成績が韓国やフィリピンに負けることもあるので「当たり前」ではない。「日本は熱心なレゲエ・ファンが多い」という認識を、改めて誇示できて喜ばしい。
映画公開を記念して彼の功績や、近年、明らかになった事実に多角的に光を当てるこのシリーズも最終回。社会的なメッセージやジャマイカの政治に及ぼした影響の大きさから堅く紹介されがちな彼を、「ゆるく」コラムにする予定だったが、結局かっちり書き続けてしまった。1月15日から始まった映画の字幕の監修作業中も感じたのだが、ボブ本人のキャラクターと歌詞に宿るスピリチャリティ、半世紀も多くのファンに愛されてきた時間の重さのせいで、気軽に触れられない存在なのだ。最終回は映画の肝となる9作目の『Exodos』を、映画の背景を絡めて分析・解説する。多少のネタバレがあるので、留意してほしい。
1. Natural Mystic
There’s a natural mystic blowing through the air
自然の神秘が宙を抜き抜けて行く
なんとも不思議な歌い出し。シンプルな構成であるにもかかわらず、ジャマイカの大自然を目にし、聖書の『ヨハネの黙示録』を踏まえてやっと手がかりが得られる。「さらに多くの人が苦しみ さらに多くの人が死んでいくだろう」という箇所も、黙示録を終末論と解釈すると理解しやすい。
この曲には、1975年にリー・ペリーと一緒に、ブラックアーク・スタジオでレコーディングされた原曲がある。そちらのクレジットは作曲がペリーだが、2年後にロンドンで改めてレコーディングされたときに大幅にアレンジが施され、コンポーザーもボブに変更された。劇中に出てくるように、新たに加入したジュニア・マーヴィンはこの曲をよく理解していた。彼のうねるようなギターが空中に漂っている「何か」の橋渡しをするようだ。
2. So Much Things to Say
They got so much things to say
奴らは言いたいことがたくさんあるらしい
この曲も聖書の『ヨハネの黙示録』の「エペソ人への手紙 6:12」がベースにある。「わたしたちの戦いは、地肉に対するものではなく、もろもろの支配と、権威と、やみの世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである」から、2つめのヴァースの1行目「わたしたちの戦いは、地肉に対するものではない」が抽出されているのだ。
善対悪の二元論に読めるが、そのあとに異なる視点の真理が歌われる。
When the rain fall, fall, fall now,
It don’t fall on the one mans’s housetop. Remember that
雨が降り続けるときは
ひとりの家の上だけに降るのではない 覚えておけ
つまり、誰かの災いや不幸は等しく人類の不幸につながる、と言っているのだ。また、この部分の直前にコードを変えて曲全体の雰囲気を変えている。
3. Guiltiness
「罪」との強烈な邦題をもつ。1976年12月3日の自宅襲撃事件の数日前に、ボブ・マーリーが書き始めた曲である。己の物欲のために人々を支配しようとする者たちを「嘆きのパンが与えられるであろう」と糾弾する。劇中に出てくるように、本人は「政治的な人間ではない」と明言していた。だが、たびたび預言者のような言動があったことも、権力者に目をつけられた理由だろう。
左腕に弾丸を受けたまま、ボブは観客のためにスマイル・コンサートに立った。当時の首相、マイケル・マンリーに政治利用された面はいなめず、忸怩たる思いが残ったらしい。それもあり、状況の沈静化のためにロンドンに14ヶ月滞在することに。そのあいだにレコーディングした本作が、それまで以上にミリタント(戦闘的)な響きをもつのは必然だろう。
4. The Heathen
こちらは「異教徒」。「異教徒を壁に追い詰めろ」との猛々しいリリックを、チャントのようにくり返している。信奉するラスタファリズムの土台となっている聖書をよく引用しているが、ボブにとっての異教徒はほかの宗教を信じる人々ではなく、権力と拝金主義に取り憑かれた人々だ。独立国家になっても肌色による階級差は残った。ボブ・マーリーは父親が白人であり、肌の色や顔立ちにそれが出ている。ジャマイカの中産階級以上に多い風貌だが、劇中に出てくるように父親に受け入れられなかったため、苦労して育っている。
妻のリタ・マーリーも幼い頃、母親が父親以外の男性のもとへと出ていった際、肌色の薄い兄弟だけを連れていった経験がある。売れるまでのボブとリタ、ザ・ウェイラーズのピーター・トッシュらとの苦労は映画ではさらりと描かれるが、徹底的にリハーサルを重ねるスタイルと、世の中の不平等を正そうとする姿勢はこの時期に培われた。
5. Exodus
映画の肝となるタイトル曲。イスラエルの民を率いてエジプトを後にしたモーセに自分をなぞらえ、ジャーの民へアフリカを目指そうと歌う。行進曲(マーチ)のリズムになっているのはそのため。根底にはマーカス・ガーベイが唱え、奴隷としてさらわれた祖先をもつ人々の心の拠り所となった汎アフリカ主義が横たわる。
中世に植民地主義を推進したヨーロッパ諸国のツアーでの様子がこの曲と重ねられるのは、偶然でも皮肉でもないだろう。『ボブ・マーリー:ONE LOVE』は、ボブ・マーリーの音楽と思想をもとに、人類の歴史をふり返るきっかけになるべくして作られた映画なのだ。
6. Jamming
あまりにも有名な代表曲。くり返しが多く、筆者は最初に聴いたときは妙な曲だと思った。それなりに長い年月を経たいまも、その想いはあまり変わらない。辛い日常を忘れて一緒に歌って踊ろう、と呼びかける、ダンス・ミュージックとしてのレゲエの良さを伝える名曲。
解釈が難しいのは、「ジャミンは過去のものだと思ったかい?」というライン。ジャズの「ジャム・セッション」と同じ意味の、集まって自由に歌ったり演奏したり踊ったりするのが「jamming」なのだが、70年代に録音された時点での「過去」は1950年代や60年代だとは考えづらい。ジャマイカのサウンド・システムを屋外に出してパーティーをする文化は廃れていなかったのだから。太古の昔から人々は一緒に歌い、踊ってきたよね? とボブは歌っているのではないか。
映画のクライマックスとなる、マイケル・マンリーと政敵のエドワード・シアガを握手させたのは、この曲の演奏の最中であった。映画的なカタルシスとしてワンラヴ・ピース・コンサートの演奏シーンを見せてくれても良さそうなのに、というのが正直な感想だが、多くの人が目撃した史実であり、再現しづらい事情があったかもしれない。
スティーヴィー・ワンダーが触発されて「Master Blaster (Jammin’)」を作ったことでも有名だ。1980年のアルバム『Hotter Than July』に収録された曲だ。スティーヴィーのほうがボブよりも5つ年下だが、12歳でモータウンと契約し、1970年代には名盤、名曲の数々を作っていたため、すでに大物であった。彼はボブ・マーリーを非常に高く評価し、ジャマイカで一緒にコンサートを行ったり、アメリカで前座に起用したりしている。
7. Waiting in Vain
I don’t wanna wait in vain for your love
君が愛を返してくれるのに待ちくたびれたよ
3年間アプローチし続けて、ライバルの多さをぼやいている曲。相手は、ミス・ワールドに輝いたシンディ・ブレイクスピアと解釈されている。じつは、ボブ・マーリーはスタジオ・ワン時代に似たコンセプトの「I’m Still Waiting」を書いている。
アメリカのコーラス・グループを思わせるバラードでリタへの曲とも取れるし、ボブが片思いの名手とも考えられる。いずれにしても、ダミアン“ジュニア・ゴング“マーリーの母であるシンディもロンドン滞在のあいだ、ボブを支えたのはまちがいない。
8. Turn Your Lights Down Low
「そっと灯りを消して」との邦題が秀逸だ。じつは、『Exodus』の収録曲で唯一、シングル・カットされなかった曲である。アルバム制作中にボブが恋愛関係にあったのはシンディなので、彼女に向けた曲だと長年のファンは理解している。そのため、リタが作曲シーンにいるのはとても驚いた。だが、この頃のリタは盟友のような存在になっており、ふつうの男女関係で測るほうがまちがえているのかもしれない。リタはボブの妻であると同時に、ビジネス・パートナーでもあったのだ。
リタを演じた、ジャマイカ系イギリス人ラシャーナ・リンチの凛とした演技がすばらしい。007の後継者を演じた『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』のアクションからNETFLIXの『マチルダ・ザ・ミュージカル』(2022)の優しいハニー先生まで演じ分ける注目の俳優である。
ボブの死後に再評価された理由は、ボブ・マーリー・ファミリーの一員でもあるローリン・ヒルのおかげだ。まず、ボブと人気アーティストと息子たちのヴァーチャル共演企画盤『Chant Down Babylon』のリリースに合わせたコンサートで、長男のジギー・マーリーとデュエットして話題に。その後、改めてカヴァー・バージョンをリリースしてヒットさせた。ローリンは3桁近いと言われるボブの孫のうち、5人の母親でもある。そのうちのひとり、YGマーリーの「Praise Jah in Moonlight」の大ヒットも彼女のバックアップによるところが大きい。ここでも「月明かり」を入れているのが興味深い。
2024年、『The Miseducation of Lauryn Hill』がApple Musicが選ぶベストアルバム100で1位となった。意外と知られてない事実だが、このアルバムの一部はキングストンのタフ・ゴング・スタジオでレコーディングされており、ジュリアン・マーリーがギターで参加している。
9. Three Little Birds
スピリチュアルなボブ・マーリーは、小鳥たちとも会話をする。
Everything’s gonna be alright
どんなことでも/うまく行くか
との牧歌的なコーラスで、ボブを知っている人も多いだろう。聖書を引用したヘヴィな曲で始め、後半にラヴソングを配したあと、普遍的なメッセージをもつ2曲で締めるアルバムの構成はさすが。
ホープ・ロード56番地のボブの家に降り立った3羽のカナリアからインスピレーションを得た説と、リタ・マーリー、マーシャ・グリフィス、ジュディ・モワットによるバック・コーラス、アイ・スリーを指している説と両方がある。筆者はどちらでもある気がしている。
10. One Love/People Get Ready
ヴォーカル・トリオだったザ・ウェイラーズのお気に入りのグループが、カーティス・メイフィールドが在籍したジ・インプレッションズだったとバニー・ウェイラーが証言している。「One Love」のオリジナルであるスカ・ヴァージョンは、デビュー作『The Wailing Wailers』に収録されている。ロンドンで再レコーディングされた際はメイフィールドのクレジットはなかったが、ボブの死後、1984年にシングル・カットされたときに著作権を考慮して併記された。
長らくジャマイカの観光局で使われている曲でもある。映画のタイトルとして採用されたのも、
One love, one heart, Let’s get together and feel alright
愛は1つ 心は1つ 一緒になろう そうすれば大丈夫
に彼のメッセージが集約されているからだろう。ラスタファリズムが提唱する「I & I」の概念をすぐに体得するのは難しいかもしれない。だが、レゲエの神様であるボブ・マーリーが半世紀も前から指摘していた分断の愚かさは、すっと入ってくるだろう。
映画にわかりづらい部分があった、と感じた人は『Exodus』を聴き込んでからもう1度観ると、腑に落ちるように思う。
このアルバムにかんして、アメリカの有力誌『タイム』が20世紀最高のアルバムに選出した、という説明がよく引用される。おもに政治や経済を扱う雑誌が評価したのは、サウンドの革新性と歌詞の歴史的な意義が大きいからだろう。
『ボブ・マーリー:ONE LOVE』の日本公開の際、監督のレイナルド・マーカス・グリーンと主演のキングズリー・ベン=アディルとともに長男のジギー・マーリーが来日した。記念イベントや取材を通して、本作がジギーの悲願であったのがよくわかった。その彼が、40周年記念盤『Exodus 40』のエグゼクティヴ・プロデューサーでもあった。それまで世に出ていなかった別テイクの録音を収録した盤であり、印象がちがうので聴き比べてほしい。
Written By 池城 美菜子

