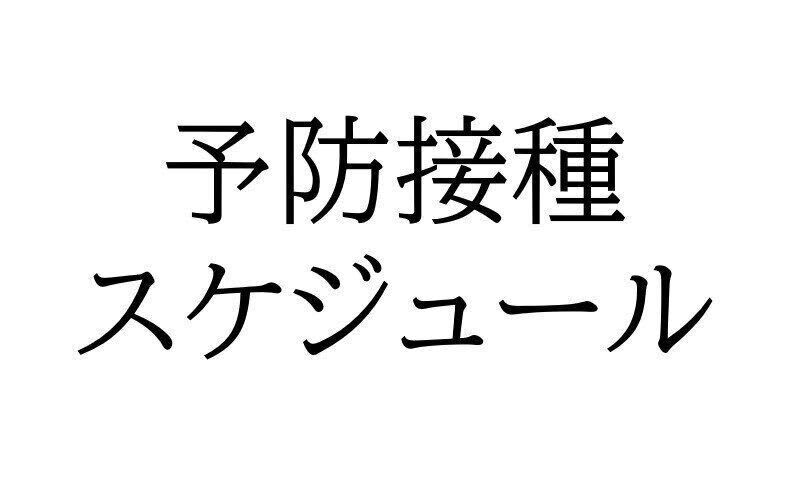
怖い感染症から赤ちゃんを守るためには、予防接種を適切な時期にきちんと受ける必要があります。受けもれがないようにするには、早め早めにスケジュールを立てることが大切です。小児科医で神奈川県衛生研究所 所長多屋馨子先生に、スケジュールの立て方について解説してもらいました。
まず、かかりつけ医を決めましょう
予防接種はできる限り同じ医療機関で受けるようにしたいので、まずかかりつけ医を決めましょう。小児科専門医がベターです。
多くの小児科専門医療機関では、健診やワクチン接種を一般診療と別枠にしていますが、診療時間に行う医療機関もあり、予防接種を受けるために行って病気をうつされてしまう…ということもあり得ます。予防接種のために決められた時間に受診することがおすすめです。
また、かかりつけの医療機関なら、赤ちゃんの体調不良などで予定の日に接種できなくても、スケジュールを立て直しやすいので安心です。
<かかりつけ医を決めるためのチェックポイント>
□任意接種を含め、すべてのワクチンを接種してくれる?
□スタッフや先生はスケジュールの相談に乗ってくれる?
□同時接種を行っている?
<ママのケース別ポイント>
●里帰り予定のママは産前からかかりつけ医を検討
産後2ヶ月以降も里帰りしている場合は、里帰り先で接種することも可能です。だたし「予防接種実施依頼書」の提出などの手続きが必要になるので、必ず産前に自治体に確認しておきましょう。
●仕事復帰予定のママは、復帰後も通いやすい医療機関を選ぶ
仕事に復帰したあとも予防接種に通いやすいように、土曜日や夕方以降も接種が可能で、ネット予約ができるなど、利便性がいいかかりつけ医を選びましょう。近くに住んでいる先輩ママやパパに相談したり、入園を希望する保育所の園医を候補にしてみるのも手。
●引っ越し予定があるママは、転居先の小児科医をチェック
引っ越し先ですぐにかかりつけ医を見つけるのは大変なので、引っ越し前に受けられるものはすべて受けておきましょう。
そして引っ越し先が決まったら、転居先の自治体のホームページなどを参考にして、小児科医を検討します。定期接種は、接種券を役所に取りに行く必要がある場合もあります。転入手続きをする際に自治体に確認してください。
スケジュールの立て方、7つの極意
ワクチンの種類が増え、予防接種のスケジュールは複雑になっています。初めての赤ちゃんだととくにとまどうことも多いと思いますが、「7つの極意」を知っておけば、受けもれを防ぐことができるでしょう。
1 定期接種と任意接種を分けずに受ける
定期接種を優先して任意接種のスタートが遅くなったり、逆に任意接種に気を取られて定期接種を忘れてしまったりというケースがよく見られます。定期、任意と分けずに接種時期が来たものから受ける、と考えるようにしましょう。生後2ヶ月になったら、肺炎球菌(13価または15価結合型)、ロタウイルス、B型肝炎、五種混合のワクチンを始めましょう。
2 接種時期が来たらすぐに受ける
肺炎球菌(13価または15価結合型)、B型肝炎、ロタウイルス、五種混合のワクチンは生後2ヶ月から、MR、水痘は1才からなど、ワクチンは接種できる月齢・年齢が決まっているので、その時期が来たらすぐに受けましょう。早期に対応することで免疫を早く得られるうえ、スケジュールにも余裕が生まれます。
3 集団接種をするものをチェックする
BCGなど、自治体によっては集団接種を行っているものがあります。集団接種は日程が限られていることが多いので、どのワクチンがいつ、どこで受けられるのかを、自治体のホームページや広報誌などで早めに調べておきましょう。
4 注射の生ワクチンのあと、別の種類の注射の生ワクチンを受けるときは27日以上空ける。同時接種はOK
2020年10月1日から、接種間隔の制度が変わりました。接種後、別の種類のワクチンを受けるには、注射の生ワクチンの場合は中27日以上空ける必要があります。一方、それ以外のワクチン(飲む生ワクチン、不活化ワクチン、mRNAワクチン)は、別の種類のワクチンを受ける場合の接種間隔の制限はなくなりました。
なお、同じ種類のワクチンを複数回受ける場合は、ワクチンごとに接種間隔が決まっていますので、注意してください。
間隔が空いてしまっても、免疫をしっかりとつけるために、決められた回数をこなすことが大事です。
5 インフルエンザ・日本脳炎は季節を先取りする
インフルエンザなら冬、日本脳炎なら夏など、流行に季節性があるものは、流行シーズンになる前に受けるようにしましょう。インフルエンザワクチンの効果はワンシーズンのみなので、流行がピークを迎える前の10~11月に毎年受けます。注射で受けるインフルエンザワクチンは6ヶ月以上の赤ちゃんが対象です。また2024年秋からは、鼻から吸うタイプのインフルエンザワクチンが2才以上19才未満の小児を対象に始まります。
日本脳炎は3才の夏前に受けるといいでしょう。なお、日本脳炎ウイルスに感染するリスクがある地域にお住まいの方は、日本脳炎ワクチンの優先度をかかりつけの小児科医に相談してください。6ヶ月以上であれば、定期接種として受けられます。ただし、1回接種量が3才未満(0.25 mL)と3才以上(0.5 mL)で異なります。
6 低月齢のときは休診日の前日は避ける
赤ちゃんの体が予防接種に慣れていない低月齢のころは、副反応が出る心配も考えて、休診日の前日の接種は控えるようにしましょう。
7 わからないことはかかりつけ医に相談する
予防接種についてわからないことがあったら、まずかかりつけ医に相談してください。スケジュールの立て方はもちろん、心配なことなども聞いておきたいもの。納得するまで説明を聞いてから接種してください。
予防接種スケジュールの例
何ヶ月のときに何を受ければいいのか、3才までの見通しを立てておきましょう。同時接種を組み込んだ場合のスケジュール例を紹介します。(ロタウイルスワクチンは2回接種タイプの場合/BCGワクチンは個別接種の場合の例です。注射のインフルエンザワクチンは生後6ヶ月以降から、鼻から吸うタイプのインフルエンザワクチンは2~18才で受けられますが2024年秋以降の開始で、接種の季節があります。10~11月に受けるのがおすすめです。新型コロナワクチンはこれまで特例臨時接種で全額公費で接種が行われてきましたが、2024年4月から任意接種になりました)
【2ヶ月】4種類を同時接種
小児用肺炎球菌(13価または15価結合型)[1回目]+B型肝炎[1回目]+ロタウイルス[1回目]+五種混合Ⅰ期[1回目]
【3ヶ月】4種類を同時接種
小児用肺炎球菌(13価または15価結合型)[2回目]+B型肝炎[2回目]+ロタウイルス[2回目]+五種混合Ⅰ期[2回目]
【4ヶ月】2種類または3種類を同時接種
小児用肺炎球菌(13価または15価結合型)[3回目]+五種混合Ⅰ期[3回目]+3回接種のロタウイルスワクチンの場合[3回目]
【5ヶ月】
BCG
【7ヶ月】B型肝炎[3回目](1回目の接種から20週以上空いていることを確かめて)
【1才】
*1回で受けるなら5種類を同時接種
小児用肺炎球菌(13価または15価結合型)[4回目]+五種混合Ⅰ期[4回目]+MRⅠ期+おたふくかぜ[1回目]+水痘[1回目]
*2回に分けるなら、まず2種類同時接種
小児用肺炎球菌(13価または15価結合型)[4回目]+五種混合Ⅰ期[4回目]
↓
その後に3種類同時接種
MRⅠ期+おたふくかぜ[1回目]+水痘[1回目]
【1才6ヶ月】
水痘[2回目]
【3才】
日本脳炎Ⅰ期[1回目]
↓
4週間後日本脳炎Ⅰ期[2回目]
※約1年後に3回目の接種を忘れずに!
1才になってからの接種は、実際にはいろいろな組み合わせで行われています。かかりつけの小児科医と相談し、子どもの体調にあわせて進めましょう。
追加接種を忘れないようにするには?
複数回受けないと免疫がしっかりつかないワクチンは、決められた回数をきちんと受けることが欠かせません。「受け忘れ」を防ぐための対策を考えましょう。
予防接種のスケジュール表を作り、母子健康手帳にはっておくのがおすすめ。そして、母子健康手帳を開くたびにスケジュールを確認します。
また、かかりつけ医で接種を受けるたびに、次の予約を入れておくと受けもれがなくなります。予定の日に体調を崩して接種できなかったり、都合が悪くなったりしてキャンセルしたときも、その場で次の予約を入れましょう。
大切な赤ちゃんを感染症から守るには、ベストなタイミングで予防接種を受けることが大切。ただし、体調がよいときに受けるのが大切です。赤ちゃんが生まれたらできるだけ早く、予防接種のスケジュールを考えるようにしましょう。
情報提供/多屋馨子先生
取材・文/東裕美、ひよこクラブ編集部
●記事の内容は掲載当時の情報で、現在と異なる場合があります。

