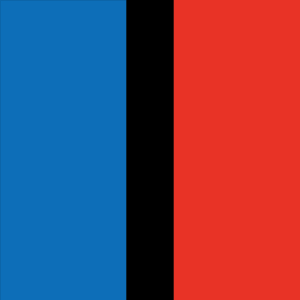韓国紙が1945年の祖国光復(解放)から独立にいたるまでの朝鮮半島をめぐる大国の思惑について触れ、「都合の悪い歴史も見つめなければならい」との立場を示している。
参考記事:韓国紙「韓国人の中国嫌いは政治要因で説明できないヘイト」「死んで当然と嘲笑…無知で愚かなこと」
プレシアン紙は『日帝植民統治35年にも韓国問題は存在した』というタイトル記事において、歴史学者であり『韓国国際関係史研究』の著者であるク・デヨル梨花女子大名誉教授の長文インタビューを載せている。
ク教授は、日本が米国に敗戦し、朝鮮半島が米国の占領された当時の様子について歴史資料をもとに詳細に紐解き「(当時の)米フランクリン・ルーズベルト大統領は韓国に対する信託統治を構想するが、これは西欧の植民地統治士から発展してきた概念だ」とし、「敗戦国である日本の植民地に対して米国のアイデアを実践する可能性があったが、しかし強大国の理解が相反し、《韓国は独立する能力を備えていなかった》という根拠で、四大国(米英ソ中)による信託統治だけを容易に合意しただけ」だったと言及。信託統治期間について「ルースベルトでさえ5年、40年、50年と曖昧で一貫性がなかった」と述べている。
ク教授は、米国のこのような視点が現代にも繋がることを示唆するように、「米国は、自国利益にとって韓国は絶対に重要ではないが、太平洋の平和のために重要であることを重ねて強調する」とし、「日本が米国の国益に不可欠な地域であれば、これを守る上での韓国の地政学的存在は容易に理解されるだろう」と指摘している。
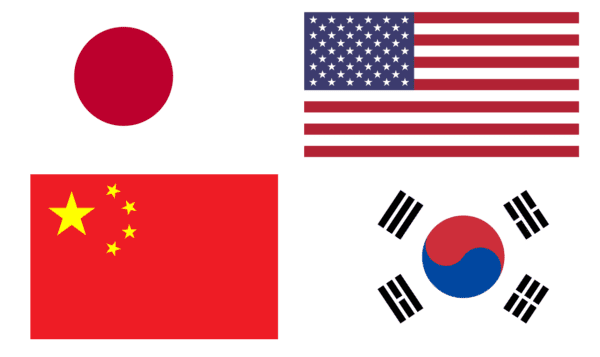
image
そのような文脈で、1945年当時に米国にとって韓国の地位というのは、「単独で」力を注ぐ価値はなくても、ソ連に引き渡すと、日本と太平洋の安全保障に脅威になるというものであったとの見方をク教授は示しており、「ソ連も朝鮮半島を完全に席巻することができたにもかかわらず、38度線で止まったのは、米国を挑発してみなければ戦後処理で得るものがないという計算とともに、朝鮮半島より重要な日本の一部(北海道)を占領して戦後統治に参加しようとする意図だった」との考えを伝えた。
ク教授は、国民党の当時中国政府についても言及し、「当時、蒋介石の中国も(大韓民国)臨時政府の承認を妨害し、むしろ分裂を助長して目立たせ、米国など西方列強が臨時政府に対する否定的な視覚を強化した」と指摘した。
蒋介石が臨時政府の後見人を務め、カイロ会談などで韓国の独立を支持したことについては「実は清日戦争以前のように中国が今後の宗主権的権利を持つもう一つの形態の朝貢体制を念頭に置いた旧時代的世界観ないし野心の産物と理解できる」と指摘している。
続けて「1942年初期の(大韓民国)臨時政府臨正承認をめぐる米国-中国-英国間の対話を細かく検討したみると、中国が臨時政府承認を強く推していたら米国と英国はやむを得ず中国の主張に同意した可能性があったというのが私の立場である」としつつ、「しかし、中国は連合国協調問題、すなわち英国の植民地問題とソ連との関係のため、米国の承認保留に同意することによって臨時政府承認の最後の機会が消えたと言える」と分析している。
ク教授は「腐った蒋介石国民党政府が臨時政府と光復軍の膨張と独自行動を抑圧した状態であり、これを期待することは難しかった」とし、「臨時政府が国民党政府の束縛から抜け出してインドを通じて米国に本拠地を移そうと試みたが、これさえ国民党が阻止した」「独自の力や発言権がなかった韓国の独立運動家たちは左派であれ右派であれ、米国とソ連の圧倒的な影響力から抜け出せず、これが内部分裂をさらに激化させる要因として作用したのだろう」と伝えた。
ク教授はイタリアの歴史学者ベネデット・クローチェの言葉を引用し、「すべての歴史は現代史的意味を持たなければならない」と述べている。
この報道をみた韓国のネットユーザーからは、
「親日と親中、反米は精神病だ」
「最も大きな問題は、歪曲された歴史や、それによる親日、親米派と、親日、親米政党が存在することだ…」
「土地を耕せば貴族が好きなように奪って私有財産を認めなかった朝鮮時代に行って財産を寄付しろ。良くも悪くも今の韓国は日帝時代を経て発展した面もある」
「反日、反中、親米、親露、これが正しい道だ」
「良い記事だ」
などのコメントがネット掲示板に投稿されている。
参考記事:韓国紙「中国の韓国への態度は属国に対するよう」「傍若無人の中国に文政権は抗議一つできず」