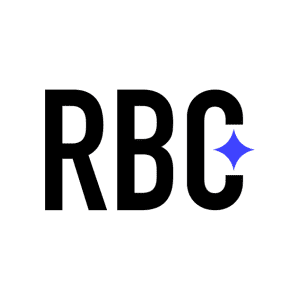日本では死産(妊娠12週以降)を経験する人は年間およそ1万6千人。また、流産は妊娠した人のおよそ15%に起こるとされている。
我が子との別れは女性の心と身体に大きな負担がかかるだけでなく、悲しみを共有できず孤立感を感じる人も少なくない。大きな喪失感を抱える当事者たちに寄り添った支援とはどういったものなのか、ある取り組みを通して考える。
わずか74グラムで「心拍が…」
石塚詩穂さん
「(初めてエコー写真を見た時は)お腹にいるんだなというのがやっとわかったという感じ。嬉しかったですね。」
沖縄市に住む石塚詩穂さん。2019年、妊娠20週の時に流産を経験した。
「妊婦検診のときには性別が分かるかなと思ってワクワクした気持ちで(病院に)行ったんですけど、心拍が確認できなくてそのまま告知を受けた。日にちの感覚がなくなってしまうくらいずっと悲しみに暮れている時間が長くて、今が何日なのかという感覚もずっとなかった」
赤ちゃんはわずか74グラム。手のひらほどの大きさだった。その時にとった足形は、赤ちゃんがそこに存在していたという大切な証。
厚生労働省によると、去年死産した赤ちゃんはおよそ1万6千人。また、働く女性の5人に1人が流産を経験したことがあるという調査結果も出ている。
産婦人科医 竹内正人医師
「流産は妊娠の15%くらいが経験すると言われていますし、最近はやはり妊娠や結婚の高齢化があるので、流産率も高くなっている。しかも体外受精や不妊治療など40歳を過ぎてそういった治療をすると、40%くらいはその年齢になってくると流産する」
産婦人科医の竹内正人医師は、子どもを失った当事者への支援として、悲しみに寄り添う ”グリーフケア” が必要だと話す。
産婦人科医竹内正人医師
「自分の気持ちを抑える、蓋をするということが多くて、周りに心配をかけない、迷惑をかけないようにするなかで、あなたのまま悲しんでいい、怒っていい、表出していいんだという場を繋ぐことで、次の生き方に繋がるということでグリーフケアが必要」
石塚さんは自身の流産経験を通して、少しでも同じ境遇にいる人たちの力になりたいと「ベビーロスオキナワ」を立ち上げた。ともに活動する古澤さや夏さんも大切な我が子を亡くした当事者として参画する。
古澤さや夏さん
「これは生まれたばっかりですか?」「「生まれてNICU(新生児集中治療室)に入ってすぐのころ」
古澤さんは、4年前に生まれつき先天性心疾患のあった長女・環ちゃんを10歳で亡くた。
古澤さや夏さん
「(環ちゃんが)いない未来を生きている実感が薄いというか、当たり前にいない未来を生きているんだけどなんか時々(亡くなったことを)忘れている自分がいて思い出すとすごく悲しくなる」
2人は、当事者が安心して語れる場を作ろうと月に1回、お話会を行っている。那覇市と沖縄市の2か所で開催していて、参加者は当事者に限定しています。
ーお話会の様子ー
「(子どもの)寝顔みるのも怖いのわかります?」「生きてる?みたいな」「今でも子どもがすやすや気持ちよさそうに寝ていると大丈夫?みたいな。」
お話会の参加者
「お会いするだけでもいいな、嬉しいなって。不思議な気持ちなんですけど、悲しい気持ちももちろん思い出しつつも、やっぱり同じ境遇の人とお会いするだけでも元気がもらえるというか、そういう会かな」
石塚さんは、この活動を通して周囲の理解が少しでも深まればと考えています。
石塚詩穂さん
「流産・死産というのは医療が発達していくなかでもなくすことは絶対できなくて、どうしても孤立感だったり、自分を責めてしまう、子どもを守れなかったということで自分を責めてしまうお母さんたちが多いなと思うので、そういう方たちの悲しみを受け入れられる温かい社会が必要なのかなと思います」
大きな喪失感を抱える当事者を孤立させないために、その声を受け止める場所が必要とされています。
【取材後記】
筆者自身も最初の妊娠で流産を経験しました。当時はどうしても自分の感情に蓋をしてしまう部分がありました。
もちろん、無理に話す必要はありませんが、当事者が話したいと思ったときにその声を受け止める場所がもっと増えるといいなと思いますし、悲しみに寄り添える社会であって欲しいなと取材を通して感じました。(仲田紀久子)